コラム「母を撮る」
映画が引き寄せる縁
関口祐加 映画監督
「私が、映画を作るのではない。映画が呼吸をしていて、その映画が私に示唆を与え、作るべき映画を作らせるのだ」。これは、初めて私にオーストラリアで編集助手の仕事をくれた、デニス・オローク監督の言葉です。
映画に真摯(しんし)に向かうと、生まれるべく映画には、色々と不思議なことが起きる……実際、最新作の「毎日がアルツハイマー」を含め、私の過去3作品を通して、そのことを体験してきました。

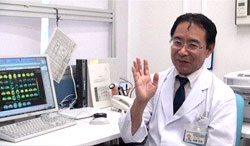
今回の、そんな不思議なご縁は、昨年、順天堂大学大学院の新井平伊教授と国立長寿医療研究センターの遠藤英俊先生に、絶妙なタイミングでまるで映画が引き寄せたように、お会いする事が出来たことです。お二人は、ご紹介するまでもなく、認知症研究の大家でいらしゃいます。新井先生は、この「新時代」を発行している認知症予防財団が、沖縄で開催した認知症シンポジウムで、一方、遠藤先生とは、NHKの番組でご一緒するという、本当に宿命的な出会いとなりました。
ちょうど母を撮り始めてから5カ月から10カ月の頃で、母の閉じこもりや、お金の混乱、入浴問題、医療拒否と次々に課題が、降り掛かっていた時期でした。また、私にとって介護以上に苦しかったのは、そんな母の撮影に追われながら、映画の方向性に迷い、探っていた頃でもありました。
映画は、劇映画だろうと、ドキュメンタリー映画だろうと、監督自身のパーソナルな「何か」から始まるものだと思います。その後の違いは、単なる小さな宇宙のパーソナル・ストーリーで終わるのか、それとも、そこから大きな宇宙の普遍性を持ったストーリーに展開させるのか。もちろん、アルツハイマーの母のパーソナルな世界から普遍性を持つストーリーに昇華させたい! しかし、どうやって?
そんな矢先に遠藤/新井両先生にお会いしたのです。お二人は、認知症について気さくに、忌憚(きたん)なく語ってくださいました。
遠藤先生は、介護を一人で抱え込まず、60点程度の介護で十分、とおっしゃいました。中でも私が一番感銘を受けたのは、本人にも分からない幸せがあるかも知れない、という指摘でした。この言葉に勇気づけられ、私は、母の気持ちを尊重しつつ、反面、積極的に介入をしようと決意したのです。母の週1回の訪問看護は、その現れです。
また、新井先生が、語ってくださった認知症の知識は、まさに目からウロコ、でした。曰く、認知症の脳は、95%以上は、正常であること、そして、周辺症状は、正常な脳の働きの現れであるという指摘には、本当に驚きました。更に新井先生は、はっきりとカメラの前で、認知症で死ぬことは、幸せであるとおっしゃったのです!
お二人のインタビューを撮り終わった瞬間、この映画の普遍性をプレゼントされた事を確信しました。お二人の先生の信念を持った言葉は、従来の認知症の考え方を大きく変えるだろうと理解出来たからです。映像の力と言葉の力が、ドッキングし、アルツハイマーの力を借りて史上最高で、最強の被写体、母主演の「毎日がアルツハイマー」は、全国順次公開されています。是非、お見逃しのないように!
2012年10月