トピックス
「アルツハイマー病新薬誕生 認知症予防はどう変わるか」
新井平伊・アルツクリニック東京院長(認知症予防財団会長)
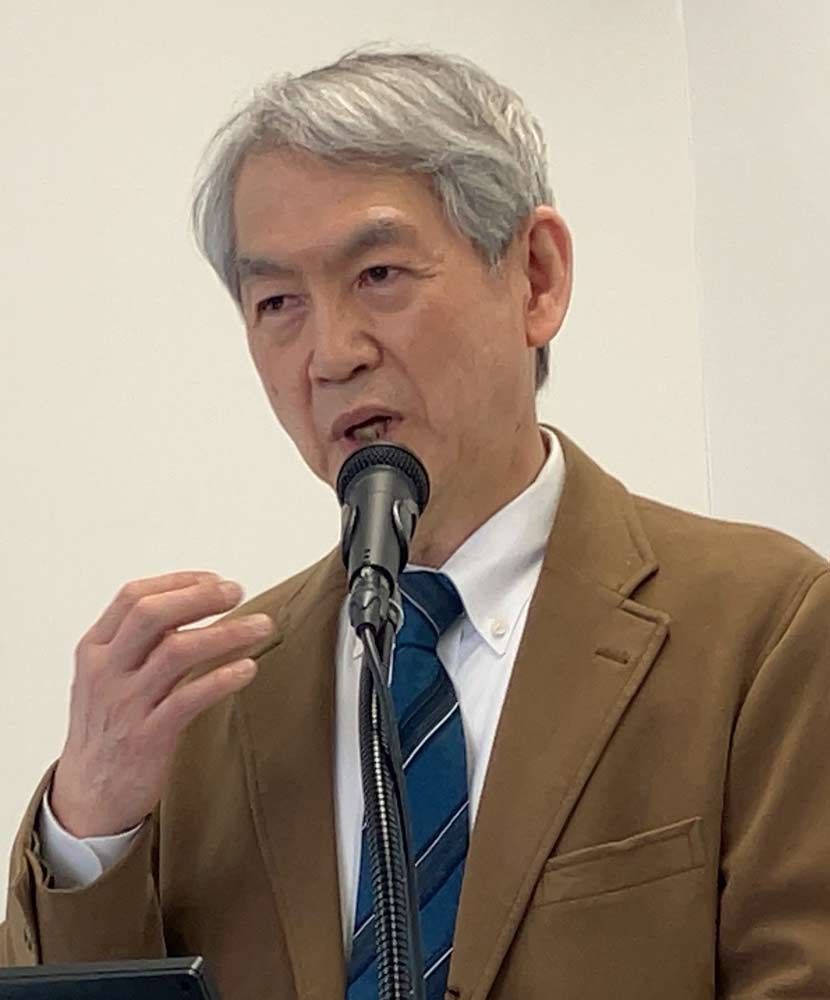
認知症の原因疾患はたくさんありますが、7割を占めるのがアルツハイマー病(AD)です。この病気の克服が人類にとって大きな課題となっているわけです。
以前は元気な方と認知症の方という二分法で、早く見つけて早く治療しましょうという考えでしたが、最近は認知症の前の段階の軽度認知障害(MCI)、主観的な認知機能低下(SCD)という熱で言うと37度台、36度台の微熱や平熱みたいな段階で分かるようになってきました。昔の早期発見、早期治療ではなく、早期予見、早期予防という考え方になっています。
周りからも気づかれ、日常生活や仕事などでも影響が出るのが認知症と呼ばれる段階です。熱で言うと、38度以上の高熱で仕事に行けない。その前のMCIは物忘れが軽くあって、周りからもちょっと気づかれる。ただし仕事や生活の上では全く支障がなく、37度前後だし仕事に行っちゃうか、みたいな状態ですね。
SCDは自分だけが物忘れを感じ、周りには気づかれずに仕事も普通にできる状態です。微熱は感じるけど36度台後半でしょうか。この段階では物忘れの検査やMRI(磁気共鳴画像化装置)検査では異常なしですが、脳の中では少しずつ変化が起きていることが分かってきています。異常なアミロイドβたんぱく(Aβ)というのが20年以上前から脳にたまり始めます。やがて神経細胞の中のタウたんぱくも巻き込まれ、神経細胞が影響を受けて数が減り、脳が縮んでくる。そうなるとMRIでも分かるようになります。物忘れの検査でも少しずつ低下が見られる。つまり通常の脳ドックでのMRI検査では認知症の直前、2〜3年前からしか異常が分かりません。私のクリニックでは脳に変化が起きてきた段階も見つけようと、アミロイドPET(陽電子放射断層撮影)を導入した健脳ドックをしています。
40%は予防可能
既にWHO(世界保健機関)を中心に、認知症の方は40%減る、もしくは予防できるというところまで研究は進んでいます。気をつける点はまず、40〜60代で聴力低下がある人は補聴器をつけ、人とコミュニケーションをとりましょう。頭を打つけが、高血圧、お酒の飲み過ぎ、肥満にも気をつけて。60〜80代の方は、たばことかうつ状態、うつ病にも注意が必要です。またどうしても社会的に孤立しがちなので人との接触を保ってほしい。それから運動不足。デュアルタスクと言いますが、頭を使いながら運動するのがいい。あと、政治的な話で大気汚染、また糖尿病、コレステロールとか中性脂肪が高いといった生活習慣は認知症の危険因子になります。
次に治療薬の話です。ADではアセチルコリンという記憶、情報伝達に役立つ脳内ホルモンが減ります。これに対しアセチルコリンを増やす薬があります。ドネペジル(アリセプト)という有名な薬です。また、Aβが脳内で増えることも分かっています。このAβを減らそうというのが、新薬として昨年12月20日に日本で保険適用されたレカネマブです。
アセチルコリンを増やす治療法は、病気の上流と下流で言えば下流の方で働く対症療法で、10カ月から1年で効果がなくなってしまいます。一方、これから発達するのは根本治療、Aβやタウたんぱくに関わる薬で、上流で止めようとするものです。今までと全く違う画期的な治療法と言えます。
新薬の名はレカネマブ、商品名はレケンビ。エーザイと米国のバイオジェンが世界で初めて開発した(原因物質に働きかける)薬で、MCIや認知症でも軽い人たちが対象です。ある程度進んだ方は対象外です。Aβが脳にたまっていることを確認するため、アミロイドPETか脳脊髄(せきずい)液の検査が義務づけられています。薬は2週間に1回、点滴します。
この薬を使うと、使わない時に比べて6カ月で違いが表れ、18カ月使うと認知機能の悪化を27%防ぐ、言い換えると7・5カ月悪化を遅らせることが分かりました。ずっと使うと2〜3年差がつくだろう、ということです。
今までの薬は10カ月ほど過ぎると効果がなくなるのですが、レカネマブは効果が続くのも特徴です。臨床試験では18カ月でAβが半分以下に減りました。例えるなら、認知症の「火元」のAβを減らします。今までの薬、アリセプトは火が広がっているところを消そうという段階で火元は消えないのに対しレカネマブは火元を消すので、それ以上広がらなくします。
ただ、どんな薬にも副作用があります。脳の中の微小出血、それから浮腫が17〜12%ほど起きています。Aβは脳血管の動脈にも詰まり、これも取り除かれます。古くなった土管の鉄さびがとれ、土管の壁が薄くなってそこから水が漏れ出すイメージです。これをチェックしていくのが大事で、治療中の2、3、6カ月あたりでMRIを撮って副作用が起きていないかを確認します。1600人ほどを対象とした臨床試験で、血管の障害で亡くなった人は1人もいない点も大事なことと思います。
新薬使用に難条件
ただ日本は健康保険制度で使うため、非常に厳しい条件があります。MMSEという知能検査で22点以上、(認知症の重症度を診る)CDR検査が0・5〜1。MCIに該当し、認知症の前段階などでしか使えません。さらに専門医が2人いて、10年以上の臨床経験があり、研修を受け、MRIを備え、認知症疾患センターと連携、との条件もあります。Aβがたまっている人で、これらをクリアできる場合だけ使える状況です。
最後に今後の展望を話します。今、実に多くの薬が開発中で人のデータで確認する「第3相」の臨床試験も(30弱の薬と)多く、レカネマブより効果のある薬が生まれてくるのは確実です。我々担当医としては(認知機能が緩やかに低下してしまう)レカネマブでもまだ弱い。もっと(認知機能の推移を)水平に保つ薬が欲しい。そうした薬をもっと前の段階で使えば、認知症を発症させずに済むことも現実味を帯びてきます。
司会 ここからは視聴者の質問です。早期発見のポイントは。
新井氏 自分が一番先に気づく変化です。今までできていた趣味や仕事に何か時間がかかるとか、うまく考えがまとまらないとか、計算がちょっと苦手になるとか。
司会 薬以外の予防法として気をつけることは。
新井氏 WHOも声明を出していて、生活習慣病、高血圧、糖尿病、高脂血症などの方はきちっと治療しておくのが一番大事。二つ目は、運動、睡眠、食事です。運動は負担をかけず継続が大切。食事はバランスよく。睡眠は最低6時間は寝る、リズムを作り、夜寝て昼は起きている。三つ目は社会生活、引きこもらず外に出て人と交流する、特に会話です。サプリメントは当てにしなくていい。ドリルは注意力は高まりますが、頭の同じ場所しか使わないので、囲碁、将棋、マージャンなど人相手のゲームの方が頭を活性化します。
司会 老化含め全ての認知症で同様の希望を持てますか。
新井氏 老化は正常な生理現象なのに対しADは病気です。ADの克服が間接的に老化防止にもなるとは思いますが、老化という生理現象まで防ぐのは難しいです。
司会 嗅覚の低下も認知症につながると聞きましたが。
新井氏 聴覚は、低下すると人と十分会話ができないなどいろいろな要素があって、高い危険因子とされています。一方、嗅覚は嗅覚神経がダメージを受けるため、初期症状、認知症の早期発見にはいいポイントですが、嗅覚を保つことが予防につながるかは研究成果として上がっていません。
司会 MRI検査を受けたくないなら新薬は使えませんか。
新井氏 MRIは閉鎖空間でガンガン音がして皆さん嫌がるのですが、副作用の確認が必須条件なので我慢して受けてもらうしかないんです。CT(コンピュータ断層撮影)ではダメなんです。
2024年4月