トピックス
アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」と「ドナネマブ」
アルツハイマー型認知症(AD)の治療薬「ドナネマブ」(※注1)について、厚生労働省は近く公的医療保険の対象とする見通しだ。ADの原因物質とされる異常たんぱく「アミロイドβ(Aβ)」を取り除き認知症の進行を抑える薬としては、昨年12月に保険適用された「レカネマブ」(※注2)に次いで2例目となる。認知症治療の現場でレカネマブを処方している専門医、新井平伊・アルツクリニック東京院長(順天堂大名誉教授)に二つの薬の違いや共通点、課題などを聞いた。
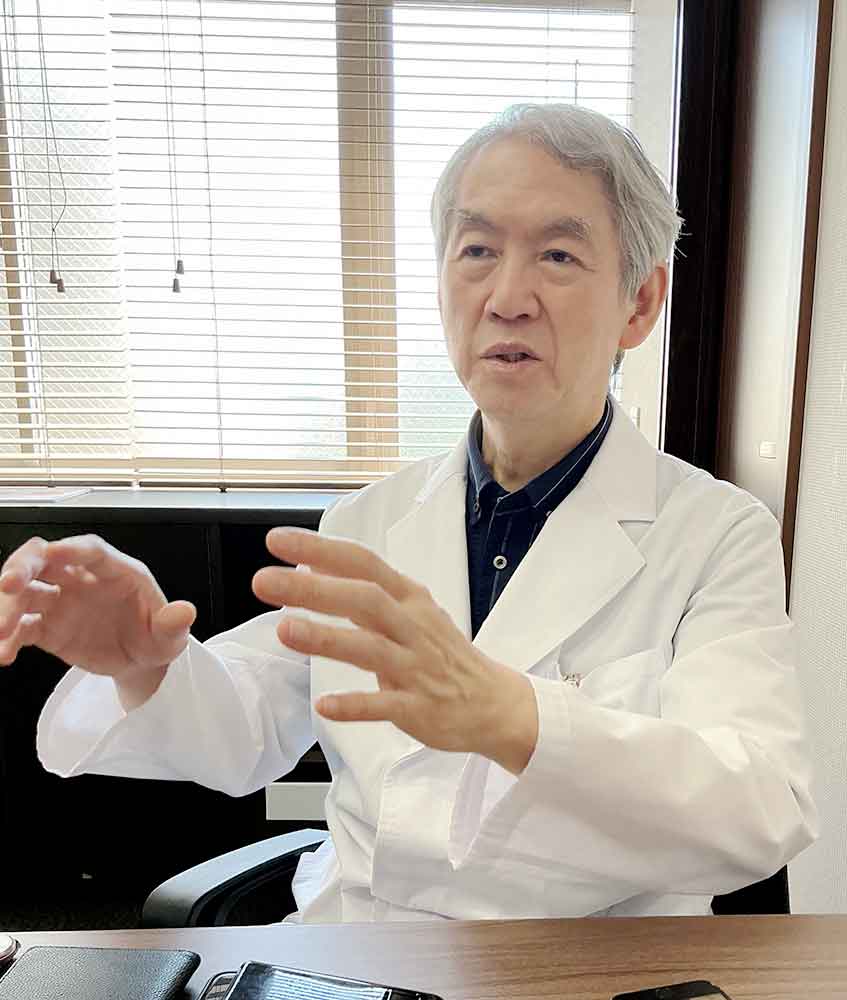
アルツハイマー型認知症(AD)の治療薬「ドナネマブ」(※注1)について、厚生労働省は近く公的医療保険の対象とする見通しだ。ADの原因物質とされる異常たんぱく「アミロイドβ(Aβ)」を取り除き認知症の進行を抑える薬としては、昨年12月に保険適用された「レカネマブ」(※注2)に次いで2例目となる。認知症治療の現場でレカネマブを処方している専門医、新井平伊・アルツクリニック東京院長(順天堂大名誉教授)に二つの薬の違いや共通点、課題などを聞いた。
◆有効性や副作用は同等
−−レカネマブとドナネマブの共通点と違いは何でしょうか。
新井平伊氏 共通点は大まかに言って、有効性と副作用ですね。また機序(薬が働く仕組み)もほとんど同じ。脳内に蓄積したAβを減少させる生物製剤で、(一つのたんぱく質の一つの場所にだけ反応する)モノクローナル抗体を点滴で投与する点も同じです。
抗体はAβにくっついて除去しますが、くっつき方に違いがあります。Aβは時間の経過とともに塊になっていきます。レカネマブは塊になる前のプロトフィブリルという段階でくっつきます。プロトフィブリルは毒性が一番強いと言われていて、神経細胞にダメージを与えます。
一方、ドナネマブはもう少し後、Aβが線維状の塊になった段階の老人斑にくっつく抗体です。それぞれ抗体の反応する場所がちょっと違います。臨床試験の結果で見る限り、有効性はほぼ同じです。ただ対象者を脳内の(ADのもうひとつの原因物質とされる)タウたんぱくの蓄積が少ない人に絞ったケースでは、ドナネマブに優位なデータもあります。
−−副作用はどうですか。
新井氏 インジェクションリアクション(投与後に起きる合併症)や、ARIA(脳からAβが除去される際に血液や血漿が血管外に漏れ出すことで起こる脳のむくみや微少出血など)といった副作用も大きくは変わりません。ドナネマブは臨床試験では脳の出血や腫れがレカネマブよりやや高い頻度で出ていましたが、同じ患者さんで比べたわけでなくどちらがいい、悪いとは言えません。
効果も副作用もあくまで臨床試験のデータであり、実臨床(実際の治療の現場)で使う場合はまた別です。私が実臨床でレカネマブを使っている例で言うと、臨床試験のデータよりARIAや発熱の割合は高いです。臨床試験では他国の人より日本人の副作用は少なく、インジェクションリアクションの頻度で見ると全体のデータのざっと半分です。それが私のクリニックでの実績だと臨床試験の日本人データの2倍の頻度で副作用が出ています。管理されている臨床試験と、いろんな要素が入ってくる実臨床では違うのです。
−−そもそも副作用はどういうメカニズムで起きるのですか。
新井氏 土管は古くなると内側に鉄さびができます。血管で言うと鉄さびに該当するのが血管壁にたまるAβです。Aβを除去する際に血管壁が薄くなり、出血するわけです。副作用は動脈硬化などのある人の方が出やすいです。
◆違いは点滴の頻度
−−レカネマブとドナネマブの大きな違いは何ですか。
新井氏 一番の違いは、点滴の頻度ですね。レカネマブは2週間に1回、月2回なのに対し、ドナネマブは月1回でいい。治療期間は両剤とも原則1年半ですが、ドナネマブは治療期間中にアミロイド沈着が除去できたと確認できた場合はその時点で治療を終了するとも定められています。
−−レカネマブの保険適用から約9カ月過ぎました。アルツクリニック東京における現時点(9月6日)での処方は何例ですか。
新井氏 保険診療下分で約60例ですね。
−−ドナネマブ同様、レカネマブにも軽度(早期)認知症とその一歩手前の軽度認知障害(MCI)の人にしか使えない、というハードルがあります。
新井氏 前から通院している方の中には病歴が長い分、徐々に進行してしまってレカネマブを使えない人が出てきます。ただ、そもそもレカネマブの使用基準がおかしいのです。基準は「MMSE(国際標準の認知機能検査、30点満点)で22点以上」などとなっていますが、「22点以上」は臨床的にはほとんどMCIの人です。レカネマブは「MCIまたは軽度認知症」の人を対象にした薬なのに、軽度認知症の人の多くが適応外ということにもなります。初期の認知症の方で18〜21点の方はしばしばいらっしゃいます。この方々には使えないのです。
−−ドナネマブは違うのですか。
新井氏 臨床試験段階の基準ですが、ドナネマブはMMSEで20点以上の人が対象でした。ドナネマブの薬価が決まりガイドラインが出ると実際の治療で使用できる基準も決まります。実臨床でも20点以上の人に使えるなら、レカネマブを使えない20点、21点の人への救いとなり、この違いは臨床的に重要です。ただしドナネマブは28点以下でないと使えず、30点満点の人は対象外です。一方、レカネマブはAβの蓄積があれば30点満点の人も使えます。
AβがたまっていてもMMSEは30点満点とまだ認知機能が正常な人もいます。早期治療の観点から、こういう人こそターゲットにするべきです。それなのに臨床試験の基準ではドナネマブは30点の人が外されています。本当は基準を両方の薬で統一してくれた方がいいのですが。
−−実臨床では臨床試験より副作用の頻度が高いという話でしたが、現場で使われていて重篤な副作用は出ていますか。
新井氏 60の投与例のうち、ある程度傾向が出る6カ月経過した方は25例です。副作用のARIAに関しては25例中、軽・中等度の方が3例、重篤な方は2例です。脳浮腫(むくみ)とか微少出血で、重篤な方の脳を画像で見るとインパクトがあります。ただ、今までの概念からするともっと頭痛や精神症状が出てもおかしくない状況なのに、ほとんど無症状です。まだ症例が少なく何とも言えませんが、4カ月休むと治療をせずとも浮腫などがきれいに消えていました。臨床試験では「ほとんどが無症状」とされていて、それを実感しています。
−−レカネマブの効果について実感はいかがですか。
新井氏 まだ投与から半年で、判定する段階ではありません。MCIの人が中心で、認知機能にそう変化は起きませんから。(薬を使わず)自然に認知機能が低下した場合とどう違うかと言われると非常に難しいですが、やはり1年、1年半で判定すべきです。症例も増やす必要があります。
◆過大な期待は禁物
−−2つの薬とも認知機能の悪化を遅らせる薬であり、改善するものではないため、効果を実感できないという指摘があります。
新井氏 当院の例で言うと、半年経過した25例中、症状が少し進んだかな、という方が数名おられ、お一人は「効かないから」と止められた。自然経過による症状の進行と思います。期待を持ちすぎるのはよくないので、そこは前もって説明しないといけません。
効果を発揮するにはなるべく早期に使える方がいいのです。MCIの手前の(他人は気づかず自分だけが認知機能の低下を感じつつも生活や仕事は普通にできる)「SCD」(主観的認知機能低下)の段階が重要です。この時点でのMMSEは30点満点ですが、SCD段階で検査を受けてAβがたまっていれば治療できますから。
−−どちらかと言えばレカネマブ推しと聞きました。
新井氏 点滴の頻度がレカネマブは2週間に1度なので、月に1度のドナネマブより通院回数が多くなり、より生活のリズムができます。全国から患者さんが来られる当院の特徴かもしれませんが、遠方から通院してきた際に、東京でおいしいものを食べよう、買い物をしようと、楽しみも増えます。通院を機に盆と正月しか会えなかった東京の子ども、お孫さんと会い、食事などをする機会を作っている人が何人もいらっしゃいます。そうしたプラスアルファの人生の喜びが主目的で、ついでに点滴もしようというのが理想的。人生を充実させるのが一番の進行予防で、次の上京時は何をしようと計画するようになれば、脳の活性化にもよっぽどいいですから。
−−認知機能を改善させる、本当の意味での根本治療薬の出現に期待できるでしょうか。
新井氏 もちろん期待しています。なぜAβがたまるのか、なぜ元々膜タンパクとしてあるものが普通に代謝されずにたまるのか、最初の時点、上流の原因がまだ分かりません。ここが分かれば、Aβをたまらないようにする薬も開発されていくでしょう。
Aβについて私は、正義の味方だった物質が闘いに敗れてたまった残骸と考えています。脳梗塞とか脳挫傷が起きるとAβがパッと出てきて、その後消えます。切り傷から感染したら白血球が戦って死骸が膿になりますが、Aβにも最初は白血球のような保護作用があり、やがて膿のようにたまるのではと想像しています。膿と違い、蓄積すると毒性を持つAβには早期に手を打つことが大切です。
神経細胞の代謝を改善させる別ルートの手段もあります。再生医療、神経回路網を再生させる方向もあります。ただ元通りの回路網を作ってくれるのか心配だし、再生医療は難しい面があります。
いずれにせよ、レカネマブやドナマネブは第一歩です。壁に一つ穴が開き、光が見えました。壁はまだ厚いですが、大きな一歩です。最も広く使われている認知症薬「アリセプト」は、神経伝達物質のアセチルコリンが減るのを抑える画期的な機序でした。レカネマブやドナネマブの開発で原因物質のAβに作用する段階まで来ました。大元のAβがどのように出てきてたまるのか、最上流の部分がまだ分かりません。これの解明が今後の展開となります。
※横にスクロールすると全体が見られます
| 医薬品名 | レカネマブ(衆品名レケンビ) | ドナネマブ(商品名ケサンラ) |
|---|---|---|
| 投与対象 | 軽度認知症及び軽度認知障害の人(MMSE22点以上など) Aβの脳内蓄積が必須 | 軽度認知症及び軽度認知障害の人(臨床試験の基準でMMSE20~28点) Aβの脳内蓄積が必須になる見通し |
| 投与方法 | 静脈点滴(週1回、自宅でもできる自己注射製剤の承認を米国で申請済み) | 静脈点滴 |
| 投与期間と頻度 | 1年半 2週間に1回 | 1年半(ただしAβ除去の成果が確認できた時点で終了) 1カ月に1回 |
| 効果 | 1年半で認知機能の低下を27%抑制(偽薬投与群との比較) | 1年半で認知機能の低下を29%抑制(偽薬投与群との比較) |
| 副作用 | 脳浮腫、微小出血など | 脳浮腫、微小出血など |
| 薬の働き | Aβが一定の塊になる前段階で除去 | Aβが一定の塊になった段階で除去 |
| 価格 | 年約298万円(日本の薬価) | 年3万2000ドル(約460万円、米国での価格)日本の薬価は近く決定 |
※注1、2 ドナネマブは米国製薬大手イーライリリーが、レカネマブは日本のエーザイと米国のバイオジェンが共同で開発した。
アルツハイマー型認知症の発症原因は解明されていないものの、異常たんぱくのアミロイドβ(Aβ)が20〜30年かけて脳内にたまり、脳で炎症を起こして脳神経細胞を破壊し、脳の病変を引き起こす、とのAβ仮説が最有力。両製剤はこの仮説に基づき、Aβを除去する薬として開発された。
ただどちらも壊れた脳神経細胞を元に戻す薬効はなく、症状が進んだ人には使えない。投与対象は軽度(早期)認知症とその前段の軽度認知障害(MCI)の人だ。いずれも認知機能や自立生活を送る能力の低下を3割ほど遅らせる効能が認められた。
新井平伊氏経歴 1953年生まれ。順天堂大大学院医学研究科精神・行動科学教授、日本老年精神医学会理事長などを経てアルツクリニック東京院長。若年性認知症研究の第一人者であり、認知症予防財団の会長も務める。
2024年10月