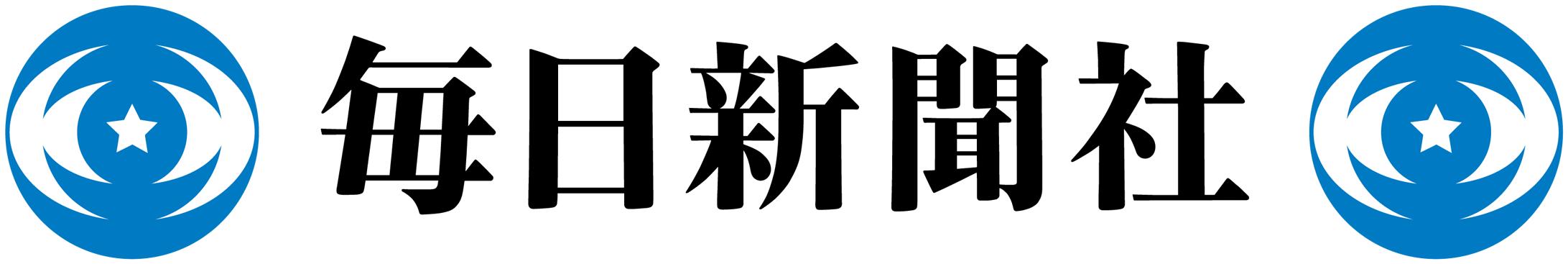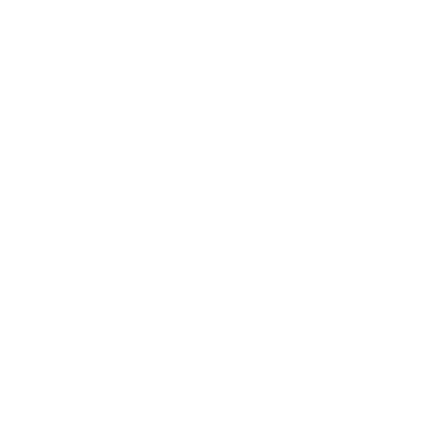織田作之助賞 U-18賞受賞作品
U-18賞受賞作品
「池から帰るふたり」 中原らいひ
夏休みが残り一週間を切った日、僕はリビングのソファーに座っていた。壁にかけられた時計は午前十時半を示している。隣では母さんが煎餅をかじり、目を細めてテレビの通販番組を見ていた。今日は天気が悪いが、まあいいだろう。机の端に置いていた携帯をズボンのポケットに突っ込むと、膝に手を置き、ゆっくりと立ち上がった。
「T池に行ってくる」
え、と母さんがこちらを向いた。
「今から池行くの? 昼から大雨降るのに」
「知ってるよ。降り出す前に帰ってくるから」
背中を向けて答えた。暗い廊下を渡り、玄関への角を曲がる。靴箱の扉に手をかけると、隣に置かれた釣り竿のケースが目に入った。埃をかぶったナイロン生地には、いくつもの黒いシミ汚れがある。もう三年もここに放ったらかしたままだ。最後に使ったのは、たしか小学校六年の夏休み最終日。あの日は帰りに――
浮かんできた光景を振り払うようにして、扉を乱暴に開けた。今のは、思い出したくない記憶だ。取り出したスニーカーに足を通し、玄関の扉を押し開ける。外に出て顔を上げてみると、母の言葉通り、いまにも雨を降らしそうな灰色の雲が空を覆っていた。湿った空気が肌にまとわりついてくるようだ。普段なら出かけるような天候ではないが、なぜか家にこもっている気にはなれない。僕は軽く伸びをすると、家から十分ほど歩いたところにある池へと向かった。
T池は、周長二キロほどの大きなため池だ。周りの土地は公園として管理されていて、緑豊かな木々の中を整備された道が通り、いくつか東屋も置かれていた。
この池は上から見ると、腕と頭のない人間のような形をしている。西半分が二又に分かれていて、それが足のように見えるのだ。その片方、細くて長いほうの足にはコンクリート製の低い橋がかかっており、いま僕はその上に立っていた。組んだ腕を柵に乗せ、足を曲げてもたれている。
僕はこうして、何をするでもなく、ただぼうっと池を眺めるのが好きだ。特に予定のない休日には、今日のようにここへ来て、柵にもたれて池を見る。それが習慣となっていた。
音のない水面をわずかに波立たせて吹いてくる風には、池のにおいがかすかに含まれている。その風が体を撫ぜると、なぜだかとても心が落ち着く。晴れた日に波があると、水面が陽光を受けてきらきらと輝き、とても美しい。だが今日の空は依然として暗く、いまにも雨を降らさんとしているようだ。
水面から岸へ目を移すと、芝生の緑が眼に映った。誰か人がいないかと思い、池の淵をなぞるように見渡してみるが、岸に人の影はなかった。魚というのは基本的に晴れよりも曇りのほうがよく釣れるので、釣り人が竿を垂らすか振るかしていそうなものだ。なのに誰も居ないのは、やはり豪雨を警戒してのことだろう。
ここへ来ると、毎回釣り人を探してしまう。なぜなのかはよく分からない。ただ自然と、視線が岸をさまよい、竿を持った人間を見つけ出そうとする。僕自身小学生のころ何度も釣りに来た場所だが、それが関係あるのだろうか……もしかすると、自分は――
ふと湧いてきた考えを、目元をこすって意識の外へと追いやった。こんなことは考えなくていい。思い出さなくていい。
人を探して目を凝らすのに疲れたので、僕はどこにもピントを合わそうとせず、遠くを見ることにした。目の前に広がるうすぼんやりとした世界をしばらく眺めていると、徐々にまぶたが重くなってきた。眠気に抵抗しようという気も、あまり起こらない。首の力が抜け、頭の位置が下がっていく。視界はさらにぼやけ、光度を落とし、範囲を狭め、そしてーーーー
ハッとして目が覚めた。柵に置いた腕に頭を乗せ、そのまま眠ってしまったらしい。目をこすって辺りを見回すが、眠る前と特に変わった様子はない。携帯を取り出して時刻を確認すると、午前十一時二十五分だった。ここに来たとき何時だったかは知らないが、二十分程度は眠っていたようだ。
そろそろ帰らないといけない。携帯をしまうと、家へと続く東の道のほうを向いた。すると、そこにはひとりの男子が立っていた。知った顔だ。縦にひょろりと伸びた細くて高い体の上には、男にしては長い髪型をした頭が乗っている。その顔にあるふたつの瞳がこちらをじっと見ているが、視線からは一切の感情が読み取れなかった。
吉川達治。三年になって転校してきた男子で、僕と同校同クラスの中学三年生だ。クラスメイトといっても、決して仲がいいわけじゃない。悪いのかというと、そういうわけでもない。ただ同じ教室で勉強しているというだけの顔見知りだ。こいつは変わったやつだった。学校で授業の一時間が終わっても、どこかへ遊びに行くこともなく、いつも窓際の席に座り、どこか遠くを見るような視線を外に投げてじっとする。飽きもせずに毎日毎時間こんなことを繰り返していた。授業開始のチャイムが鳴ると、ひとまずは視線を教室の中に戻すのだが、しばらくすると窓の外へ吸い寄せられるように眼が動き、首も左を向いていく。そしてまたじいっと眺めはじめるのだ。どう見ても授業を聞いている態度ではないので、先生たちは吉川に「今なんの話をしていましたか?」なんて質問をするのだが、彼はそれに、一言一句違わず先生の台詞を暗唱してみせた。心ここにあらずという感じでも、授業はちゃんと聞いているらしい。その記憶力のおかげか、吉川は成績も優秀だった。三年の一学期が始まったころは彼を気味悪がる生徒も多くいたが、次第に慣れ、話しかける人も増えた(返事は一言だけの場合が多いが)。顔が割りと整っているおかげかもしれない。 吉川はこちらを見て、すこし驚いたように目を見開くと、にっ、と微笑を浮かべてこちらへ歩いてきた。こいつがハッキリとした表情を見るのは初めてだ。彼は僕との距離を五メートルほどに縮めたあたりで、
「よう」
さっきよりもずっと屈託のない笑みで、こちらへ軽く手を挙げて挨拶してきた。
よう? いつ僕とお前がそんなほがらかに挨拶する間柄になったんだ。完全に面食らってしまった僕は、頭に無数の疑問符を浮かべながら、吉川がこちらへ歩いてくるのをじっと見ていた。彼は落ち着いた足取りで道を進んでくると、まるで長年の大親友の悩みを聞こうとでもするかのように、僕の右隣へと立った。
「お前、同じクラスの加藤だよな?」
フランクに言ってきた。いったい何なんだ? 学校にいるときとはまるで別人じゃないか。
「あ、う、うん」
声が困惑で震え、そのうえ吃ってしまったのは仕方のないことだろう。
「やっぱそうだよな……俺のこと知ってる? 吉川っていって、三年で転校してきたんだけど」
「知ってるよ」
池へと目を逸らしながら答えた。自分が有名人だという自覚は無いのか。
「ああ知ってたのか。俺とお前ってさ、話したことあったっけ」
「いや……」
ない。いちどもない。学校で吉川とは、言葉はおろか、視線すら交わしたことはない。外の景色を眺める彼に、近いものを感じた僕のほうから、様子をチラチラ窺うことはあっても、その逆は無かった。あくまでただのクラスメイトという関係であって、決してこんなふうに会話をすることはない。それなのになぜ吉川は、こんなにも気さくに話しかけてくるんだ。なにか企んでいるんじゃないだろうか。そうやって勘ぐりはじめると、緊張でじっとりと汗がにじむ。様子を窺うように吉川の方を見た。隣に立つとあらためて思う、こいつは背が高い。僕もクラスでは比較的身長の高いほうだが、吉川はそれよりさらに数センチ高い。175cmはゆうにあるだろう。細いので威圧感はないが、また別の空気を纏っている。 「ここでなにしてんの?」
悶々と考えをめぐらしているところに、また吉川が訊いてきた。
「池、見てる」
「おお、俺と同じだな」
「吉川も?」
「俺もここからの眺め好きだからな。今日は景色を見に来たんじゃないが」
彼もここからの眺めが好きなのか。前から思っていた通り、すこし気が合いそうだ。体を包んでいた緊張が解けてゆくのがわかる。しかし今日の目的は違うらしい。
「吉川の方こそさ、なんでここ来たの」
彼はなぜか胸を張ると、
「俺? 俺はさ、雨に濡れに来たんだよ。朝天気予報見たら昼からすげえ豪雨だっていうから、これはずぶ濡れになるしかねーなって思ってさあ」
何を言ってるのかさっぱりわからない。濡れに来た? 吉川の服装はTシャツにハーフパンツ、サンダルというシンプルなものだった。水で駄目になるようなものはないだろうが、それにしても本当におかしなやつだ。
変人の思考をわざわざ理解しようとは思わないが、話を聞いてひとつ気になる点があった。
「濡れたいなら庭にでも出ればいいだろ。わざわざここまで来ることない」
吉川は首を傾げてすこし唸ると、
「そこはほら、なんとなくだよなんとなく。散歩がてら、雨を浴びるのにいい場所を探してたら、自然と足がこの橋に向いたんだよ」
「ふーん……まあ、足が自然と向くってのはわかるな」
たしかにここはいい場所だ。水面を滑って冷やされた風は夏でも涼しく、広がる緑は目にやさしい。
しばしの沈黙の後、ずっと気になっていたことを訊いた。
「なあ……お前、学校と全然態度違うけどさ、どうかしたのか」
吉川が、池から僕へと視線を移した。
「もしかして何かあったのか? そんな、別人みたいに話してさ」
ひどく辛いことがあると人は落ち込むが、中には無理に明るく振る舞って、嫌な気持ちを忘れようとする者もいる。吉川は変人だが、彼のような人間こそが、意外とそういうタイプなんじゃないだろうか。
吉川の顔をあらためて見ると、なぜか、頭の上に疑問符を浮かべたような表情をしていた。
「何かあった、って……別になんもねえよ。俺学校の外ではいつもこんな感じだぜ? まあ今日は雨降るからテンション上がってるのもあるけどな」
「え、それだけ?」
正直拍子抜けだった。記憶の中とあまりに態度が違うので、夏休みの間なにか大きな出来事があったのではと勘ぐっていたが、考えすぎだったようだ。校外ではいつもこうなのか。
「心配して損したよ……」
「お前心配してくれてたのか。……何を?」
「いや別に」
そのあと僕たちは、学校や遊びのことで話に花を咲かせた。教科の得手不得手、嫌いな教師の悪口、好きなゲームや漫画、気になっている女子のこと……どこか違う生き物のように思っていた吉川も、話してみれば僕と同じ、ただの男子中学生だった。そして吉川と喋るうちに、テンションの高い彼に慣れてきている自分がいた。これはこれで、案外楽しいかもしれない。
しばらく話していると、池のほうから、ぼちゃん、と音がした。魚がはねたのだ。僕達は言葉を止め、ふたりして音の方を向いた。暗い空を映した池の水面には、幾重もの円が広がっている。
「いまの魚なに」
音がしてからすこし経って、吉川が訊いてきた。
「たぶん鯉だよ」
池にすむ魚で、あれほど大きな波紋と音をたててはねるのは鯉ぐらいだ。小学生のころに大物を釣り上げたことがある。僕にとっては印象深い魚だ。
「へえ、詳しいんだな」
感心したように吉川が言う。
「鯉ぐらい知ってて当たり前だろ」
「いや鯉は知ってるけどさ、はねるのを見てもわからないだろ普通」
成績優秀な彼ならそれぐらい知っていそうなものだが、授業で習うこと以外には、案外疎いのかもしれなかった。
「魚好きなのか?」
「昔は好きだったよ。小学生のころは」
「全然昔じゃねーじゃん」
「僕にとっては昔だよ」
あの頃のことは、ものすごく遠く、はるかに前のことのように思える。
「じゃあ釣りとかすんの?」
「小学生の時にやってたよ。今はやめたけど」
「やめたって……なんでだよ」
吉川の言葉に、僕は答えることができなかった。いったいなんでだろう。なぜ、釣りをやめてしまったんだろう。あんなに好きだったのに。竿を通して伝わる魚の重みを手に感じて、それを陸へと引き上げるときの興奮はいまでもはっきりと心に残っている。それがなぜ……
「あ、」
そうか、あれがあった。
「父さんが……死んだからかもしれない」
「父さんが死んだから……ふーん」
吉川は僕の言葉を復唱すると、そのまま黙りこんでしまった。こいつも、亡くなった親の話をさせてしまったことを、申し訳なく思ったりするのだろうか。
「お前の親父なんで死んだの?」
そんなことはないようだ。彼はデリカシーというものを持ちあわせていないらしい。ただ、不躾な質問ではあったが、なぜか訊かれて悪い気はしなかった。
「交通事故で死んだんだよ。釣りの帰りに、自動車に撥ねられてさ」
より正確に言うと、撥ねられたというより潰された。あの時の記憶は、なるべく思い出さないようにしている。
「あ、こういうのって訊かないほうがいいか?」
「べつに気にしなくていいよ。悲しくはないから」
すこし、自分に言い聞かせるように言った。
それから僕たちは言葉を発さず、場にはしばらくの沈黙が流れた。その間僕の頭の中では、父との思い出が、走馬灯のように流れ始めていた。いままで考えないようにしていたものが、吉川の言葉をきっかけに湧いてきたようだった。普段なら気分が悪くなるのに、不思議と心は穏やかだ。
「――事故の時のことさ、話そうか」
そんな言葉がふいに口をついて出たのは、五分ほど経ったあたりだった。
何を言ってるんだ僕は。
「いいのか? そういうのって思い出したくないんじゃ」
ようやくデリカシーというものを理解し始めた吉川に、「大丈夫」と答えてしまった。
止めようとする意識とは裏腹に、口は勝手に動いてしまう。頭の中で慌てている間にも、蘇ったいくつもの記憶はあふれ、許容量を超えようとしている。
――ああ、もしかすると、
「聞いて欲しいんだ」
そうか。僕は、無意識のうちに、自分から、
「長くなるけどいいかな」
父のことを思い出して、話したがっているんだ。
「全然構わん」
吉川は真剣味を帯びた瞳でこちらを見つめてくる。
「じゃあ、話すよ」
僕は、心の奥にある鍵をゆっくりと開け、中にしまっていたものを、少しずつ取り出していった。そして、それを語り始めた。
初めて釣りに連れて行ってもらったのは、小学校三年生のときだった。玄関で釣具の手入れをしている父を隣でじっと見ていると、お前もやってみるか、と言われたのがきっかけだ。その次の日僕は父についていき、T池へ向かった。池の岸に立った父は、肩にかけていたケースを下ろし、黒い竿を抜き出すと、それをするすると伸ばしていった。僕は言われるままに、仕掛けを付けて池へと垂らした。すると、にわかに竿が震えはじめ、上げると鮒がかかっていた。これが初めて釣った魚だった。
その後も僕と父は、車で川や海にも出かけ、釣った魚を持ち帰っては母に調理してもらった。四年生になると、僕専用のリールロッドも買ってもらった。毎日が楽しみで、とても幸せな日々だった。
しかしそんな生活は、唐突に終わりを迎えた。
忘れもしない、八月三十一日の夕暮れ。夏の最後の煌きを見せる夕日が、街全体に落としていた影の中を、僕と父のふたりは家へと歩いていた。T池で釣りを終えた帰りだった。
父と自分の、ふたつの釣り竿ケースを腕に抱え、前の背中を追いかけている僕の、三歩ほど先をゆくのは父だ。左手に釣りの仕掛けや小物を入れたバッグを持ち、右手には大きなバケツを持っていた。その中では、僕が初めて釣った80cmオーバーの鯉が泳いでいた。それまで一匹も釣れず、今日はもう日が暮れるから帰ろうとした所で竿にかかり、二十分にもおよぶ格闘のすえ釣り上げた大物だった。
「鯉持って帰ってどうするの?」
「食べるんだよ」
「え、鯉って食べられるの!?」
「食べられるよ。数日桶にでも入れて、泥を吐かせれば大丈夫」
食べたことのない鯉の味を想像して目を輝かせる僕を見て、父は「ははは」と笑った。
そんなふうに話しながら帰路をたどっていると、住宅地を割るように通る道路が現れた。ここの交差点を渡ってすこし歩けば、もう自宅に着く。父は押しボタンの横に立ち、信号が変わるのを待った。僕はというと、そこから三歩うしろで立ち止まっていた。父のそばに行ってもよかったのだが、なんとなくこの距離感が気に入っていた。
やがて車両側の信号が、青から黄、黄から赤へと変わり、歩行者側の信号が青く点こうとした、その時だった。
西から狂ったようなスピードで走ってきた一台のワゴン車が、僕達のいる交差点に突っ込んできた。歩行者道へとハンドルを切った車は、目の前の父をフロントにぶち当て、そのまま民家の塀に衝突した。何か水のようなものが飛んできたので体を見ると、赤黒い無数の斑点が付いていた。
民家に目をやると、前が完全にひしゃげて、長さが三分の二ほどになったワゴンがあった。その大きな鉄屑と塀に挟まれ、父は息絶えていた。姿は車体に隠れて見えなかったが、血しぶきの広がった塀と、車との間から流れ出るおびただしい量の血液が、目に焼き付いている。一度静まり返った交差点が、人の叫び声で満たされていくなか、僕はただ呆然と、釣り竿ケースを抱えて立っていた。
その後のことは、はっきりとした記憶が無い。ただ、道端にひっくり返ったバケツから飛び出した鯉が、アスファルトの上でびちびちと跳ねていたのを覚えている。
車を運転していた男も、父と同じく即死だったそうだ。あとで警察から聞いた話によると、飲酒運転の上、スピード違反でパトカーに追いかけられてたらしい。
親の死というものを上手く処理できるほど、十一歳の脳は完成されていない。当時の僕は、いままでそばにいた父が死んだことを頭では理解できても、心では受け入れられず、葬式でも全く泣くことはなかった。呆けたような顔で僧侶の読経を聴き、母に勧められるまま棺桶に花を入れ、骨を骨壷に詰め込んだ記憶がある。
「……砕く必要はなさそうだな」
火葬炉から出てきたものを見た叔父がボソリとつぶやいた台詞は、いまでも耳からはなれない。
結局僕は、一滴も涙を流すことなく、父との別れを終えてしまった。そして時が経つにつれ、父との思い出は楽しいものではなく、考えただけで凄惨な光景が浮かんでくる”きっかけ”として認識するようになっていった。
「……まあ、こんな感じかな」
ひと通り話し終えて右を向くと、吉川はキョトンとした顔でこちらを見て、しきりに目を瞬かせていた。いったい何だ。
「顔に汚れでもついてる?」
「いや汚れっていうか……」
どこか困惑したような表情を浮かべる吉川。
「お前さ、親父のことで泣いたことがないって言ったよな」
「ああ、うん。そうだよ」
たしかにそう言った。父の死以来、僕は感動や悲哀のような情動で涙を流したことがない。
「けどお前、泣いてるぞ」
「……え?」
頬に手をやった。……たしかに濡れている。空を仰いでみるが、まだ雨は降っていない。僕は本当に、泣いているのか。
そう思うと急に、胸の奥が熱くなった。そして、吉川に話していない父との思い出が蘇ってきた。思い出そうとしたわけでもないのに、どんどんと溢れてきては洪水のように流れてくる。夢中で対戦したテレビゲーム、家族で行った旅行や遊園地、一緒に食卓を囲んで食べた夕食……僕自身どこかへ忘れ去ってしまっていた記憶が無数に浮かんでくた。
思い出に比例して涙の量も増えていき、泣き方もひどくなってゆく。しまいには、鼻水を垂らしてしゃくりあげてしまうほどになった。
「大丈夫か?」
横から吉川が心配そうに声をかけてくる。大丈夫、と言おうとしたが、大泣きしているせいで「らい、じょ、ぶ」となってしまった。そして、
「お、雨降ってきたな」
吉川がそういうと、背中をいくつかの小さな粒が打つのを感じた。やがてその数は増えていき、辺りは雨音でいっぱいになった。
雨にまぎれて涙を流す僕の隣では、吉川がなにやら騒いでいる。ふたりともびしょびしょだ。風邪をひくかもしれない。そんなことを頭の片隅で考えながら、父との思い出を回想していた。
どれほどそうしていただろう。ひとしきり泣いて顔を上げると、雨はすでにやみ、流れる雲の端からは太陽が顔を出し始めていた。
「目赤くなってるぞ」
隣でずぶ濡れになった吉川が、顔を見て笑った。僕も笑った。
なぜ吉川に話そうと思ったのか、雨も涙もやんだ今ならわかる。僕自身が、父の記憶をふり返りたかったんだ。怖がって封印してしまった思い出と、正面から向き合いたかった。けど、ひとりでそれをするのは恐ろしかった。だから、吉川に話そうと思ったんだ。こいつに横で聞いてもらったおかげで、僕は落ち着いて、父と過ごした日々を思い起こすことができた。
顔の水を拭うと、彼の目を見て「ありがとう」と礼を言った。
「え、なにが? 俺なんかした?」
戸惑う吉川を見て僕はまた笑い、池を眺めた。波立つ池の水面には、陽光が無数の星となって輝いている。土砂降りが終わったあとの空気は澄み、ほのかに流れる風は涼しい。数年ぶりに泣いた僕の全身にも、晴れやかな清々しさが流れていた。
「じゃあ俺、雨終わったし帰るわ」
そう言うと吉川は踵を返し、東の道へ歩きはじめた。ひょろりと高い体が、徐々に遠ざかっていく。
「ちょっと待って」
その背中に声をかけた。今日のような、おしゃべりでデリカシーのないこいつと、また話してみたい。そう思うと、呼び止めずにはいられなかった。
「メアド交換してよ」
吉川はこちらへ振り向くと、
「俺、携帯持ってねーぞ」
「え」
しばらく固まったあと、思いきり吹き出してしまった。なぜだか無性におかしく思えた。腹を抱えて吉川を見ると、すこし恥ずかしそうに口をモゴモゴさせている。
「使う予定ねーし……」
「ごめんごめん」と謝ると、家がどこにあるか尋ねた。
「N町だぞ」
「じゃあ途中まで一緒に帰ろうよ」
「ああいいぞ。俺と家近いのか?」
自分からこんなことを言い出すのは初めてだ。不思議な感慨を覚えていると、ズボンのポケットの中で携帯が震えた。メールを確認すると母さんからだった。
「雨が降ったけど濡れてない?」
「大丈夫」とだけ返し、携帯をしまった。前では吉川がこっちを見て、早く来いと言っている。一週間後の教室にいる彼は、きっと今までどおりの、静かで変な吉川なんだろう。彼がどんな反応を返してくれるかはわからないけど、声をかけてみよう。そう思った。
僕は最後に池を見つめたあと、小走りで吉川の横に並んだ。
夏の終わり、大雨を浴びた橋の上を、びしょ濡れの中学生がふたり歩いていった。