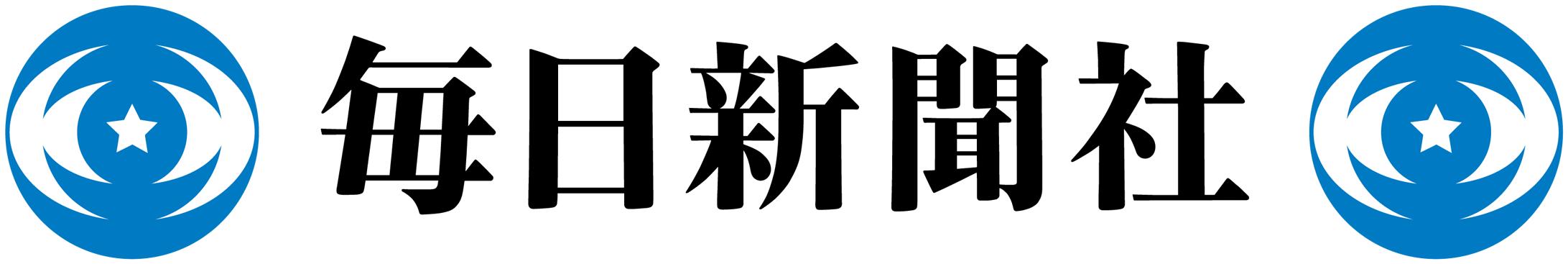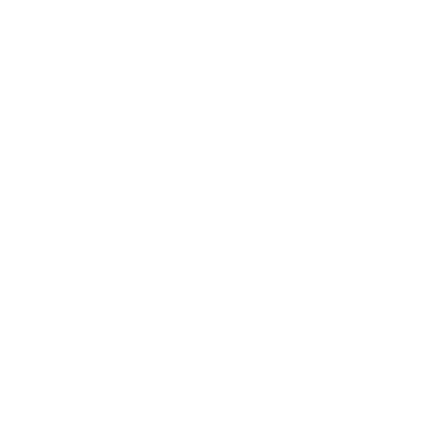織田作之助賞 U-18賞受賞作品
U-18賞受賞作品
「パチンコ玉はUFO、ブルーのビー玉は地球」 烏月 にひる
七年前の今日、ぼくはUFOを拾った。話はそこから始まるんだ。これはぼくがUFOを拾ったことで体験した、ちょっと不思議な出来事をまとめたものだ。この物語を聞いて君がどう思うかは君の自由だ。でも一つだけ間違えてほしくないのは、ぼくがこの物語を君に話すにあたって、ぼくは一つたりとも嘘をついていないという事なんだ。つまりこれは〝本当にあった〟出来事なんだな。まあとにかく話そうと思う。
そいつは直径一センチにも満たない銀色の球体だった。そいつっていうのはUFOのことさ。ぼくはそいつを通学路の途中にある田んぼで拾ったんだ。でも田んぼと言っても、あの水が溜まった夏の田んぼじゃなくって、稲刈りもすでに済んでいた秋の田んぼだよ。むしろ畑と言ったほうがいいかもしれないね。何もない、茶色の土地だもん。それで、ぼくがUFOを拾った時の状況だけど、ぼくは学校から家に向かって石を蹴りながら歩いていたんだ。つまり下校中だったってわけ。そしてぼくが田んぼのところにさしかかった時に、力の入れ方を間違ったのか、蹴るところが悪かったのか、蹴っていた石はまっすぐ転がらずに、田んぼのほうに転がって行っちゃったんだ。石はそのまま用水路の中に落ちてしまった。そこでぼくは新しい手ごろな石がないかあたりを見回した。それで田んぼの中できらきら光る物体を発見したってことなんだ。ぼくは急いで近寄って拾ってそいつをポケットにしまった。見た目以上にずっしりしていたな。とにかくUFOを拾ったぼくは、走って家まで帰ったよ。
家についたぼくはママンに見つからないようにこっそりと自分の部屋がある二階へと向かった。そしてポケットからUFOを取り出すと、そいつを宝箱の中にそっとしまいこんだんだ。ぼおっと窓の外を見ると、沈みかけた夕日が山の向こう側を燃やしているみたいで、きれいだったな。
夜、月が太陽の光を受けて輝いていた。そう考えると、UFOは月に似ているかもしれない。9歳のぼくは思ったみたいだ。UFOのことが気になったぼくは、再び宝箱を引っ張り出してきて、中からUFOを取り出した。田んぼにあった時と何の変化もない銀色の塊だった。やっぱり重かったな。ぼくはUFOに魅了されていたんだ。この大きさといい、つやつやとしたさわり心地といい、中に何かが詰まっているような重さといい、すべてが愛おしかったね。ぼくはUFOを持ったまま窓辺に行った。当時のぼくの部屋からは、月以外にも様々な星が見えたんだ。ぼくはその星々を眺めながら、手の中で眠っているUFOをうっとりと見つめた。この星の中のどこからこのUFOはやってきたのだろう。そんなことを考えていた時だったと思う、突然手の中のUFOがぶるぶると振動し始めたんだ。それと同時にぼくの手のひらに激痛が走った。ぼくは反射的に手を開いてしまったんだな。その瞬間、UFOが窓を突き破って夜空へと飛び込んで行ったんだ。何してるの? 一階のキッチンで夕飯を作っているであろうママンの声がした。何でもないよ。今考えればばれていたのかもしれないけど、当時のぼくはそう言えば大丈夫だと思っていたみたいだ。ママンはそれっきり何も言わなかった。その時ぼくが考えていたのは割れた窓のことなんかじゃなく、もちろん消えたUFOのことだった。今から探しに行ってもこんな暗闇じゃ見つけられないだろう。それにママンが怪しむはずだった。やれやれ、とぼくはため息をついて、その日は諦めることにしたんだ。窓にあいた穴から夜が液体となって入ってくる気がしたよ。
次の日の朝、ぼくはまずは家の周りを探すことにしたんだ。何をって、UFOをだよ。一時間探したところでぼくは諦めた。とりあえずは、諦めた。だってその日は平日で普通に学校がある日だったんだもん。それにちょっと考えればわかることだった。あんなに小さいものを見つけるのは容易なことではないってことが。昨日は偶然見つけられただけだ。もし季節が夏だったら、稲が邪魔をして絶対に見つけられなかったはずだよ。UFOが草むらに落ちていないなんていう確証はなかった。事実、当時ぼくの家の周りには草むらがいっぱいあったんだ。そういうこともあって、ぼくは泣く泣く学校へと向かった。
その日、クラスではいつもと少し違うことがあった。そのためにクラスのみんなも少しばかりそわそわしていた。そう、転校生がやってきたんだ。それはショートボブの明るい髪をした女の子だった。
「初めまして、××町から来たQです。よろしくお願いします」
クラスの半分が男の子ではなかったことに落胆し、クラスの半分がそれとは反対の理由で喜んだ。ほら、9歳ってまだそういうのが表に出ちゃう歳でしょ? でも、どちらにせよ転校生のことを快く受け入れていたことに変わりはないよ。これも9歳くらいの特徴だよね。誰とでも仲良くなれる。ただQが入ってきたときに、クラスの空気が一瞬にして変わったことは事実だった。それには二つのわけがあったんだ。一つ目はQがとてつもなく可愛かったということだ。例えるなら春の野うさぎだね。春の野うさぎみたいに可愛かったよ。当時ももちろんそう思ったけど、今振り返ってみてつくづく思う。そして二つ目の理由なんだけど、それはQが眼帯をしているってことだった。いやいや、誤解するかもしれないから断っておくけど、それがQの可愛さを損なうことは決してなかったよ。むしろミステリアスな印象を与えてさらに魅力的だった。問題はそういう事ではなかった。そのミステリアスさの陰にぼくは(たぶんほかのみんなも)異質な何かを見たんだ。その異質なものの正体とはなんなのか、これはこの物語のいうなればオチの部分だから、言うべき時が来たら、言うよ。
先生はQについて一通り説明した後、Qの新しい席を指示した。君の席はあそこだ。そういって指したのはぼくの隣の席だった。うすうす予想はしていたんだけど──だってクラスに入ったら、ぼくの隣に新しい席が置いてあったんだもん──いざ言われると不思議な気持ちになったな。嬉しいような、緊張するような、そんな感情だったよ。それはQがこっちに近づいてくるに従って、大きくなり、Qが席に着いたときに最高潮に達した。
「Kです。よろしく」
ぼくは軽く自己紹介をして手を差し出したんだ。自分でも驚くほどすらすらとした喋りと滑らかな動作だったね。まるで自分以外の誰かがぼくのことを遠隔操作しているみたいだ。
「よろしく」
彼女は静かに言って、少し悩んでから手を握った。不思議な握り方だったよ。握るというよりも触れるという感じで、感触もまるでガラスを触っているみたいだったな。それから一日ぼくは雲の上を歩いているようなふわふわした感覚で過ごした気がする。
UFOは簡単に見つかった。ぼくは学校が終わったら、すぐ家に帰ってまた家の周りを捜索するつもりだったんだけど、なんと帰り道の途中でUFOを見つけちゃったんだ。どこで見つけたと思う? 正解は田んぼだよ。前と同じところに前と同じように落ちていたんだ。ぼくは今度こそ逃がさないようにしっかりつかんで、そのあとでそいつを太陽にかざしてみたんだ。まるで金環日食みたいにUFOの周りを太陽が縁取った。それからぼくはしばらく様々な角度からUFOを見ていたんだけど、やがてそうしてることにも飽きて、ぼくは家へと向かったんだ。すると風がふうっと吹いて、ぼくの前髪を撫でた。
「ガラス、あれはいったい何?」
家に入った瞬間、玄関のところでママンに怒鳴られちゃった。ごめんなさい。ぼくはとりあえず謝った。
「謝る前にどうしてガラスが割れてるのか説明しなさい」
こういう時のママンは厳しいんだ。きっと何もかもお見通しなんだろう。それでもぼくは知らないふりをした。
「ぼくにもわからないよ。朝起きたら割れてたんだ」
「何もしてないのにガラスが割れるわけないでしょ。嘘をつかないで、ちゃんと説明しなさい」
ぼくは困ったことになったなと思ったよ。だって本当のこと──UFOが割っただなんて言ったところで、嘘をつくなと怒鳴られるに決まってるからだ。
「野球のボールを投げて遊んでたら、割っちゃったんだ」
ぼくはとにかく思いついたことを口にしたよ。
「野球ボール? あんた野球なんてやってないでしょ。どうしてボールなんて持ってるのよ」
ママンは怪訝そうな顔をした。
「ひ、拾ったんだよ」
「あんたはなんでも拾ってくるんだから……」
何とか信じてもらえたようだ。本当にごめんなさい。
「もう今回限りだからね。次同じようなことをやったら、許さないから。それともう何も拾ってこないこと」
なんだかんだ言って、ママンはやさしい。あるいは甘いと言うべきかもね。ぼくはもう一度ごめんなさいと言ってから、自分の部屋へと続く階段を駆け上がった。ポケットに拾ってきたUFOを忍ばせながら。
夜、夢の中。Qがぼくに向かって話しかけてきたんだ。
「ねえ、月の裏側ってどうなってると思う?」
わからないな。しばらく悩んでから出た回答がそれだった。それにしてもQは何でそんなことを聞いてくるんだろう。
「知りたい?」
うん。知りたい。ぼくは知りたいよ、Qのことが!
「じゃあ教えてあげる」
そういって彼女は語りだしたんだ。
「月にウサギがいることは知ってるよね? でもK君が知っているのはきっと、月の表側で餅をついているウサギのことだけだと思う。本当は月には101羽のウサギがいるの。1羽はさっき言った餅をついているウサギ。残りの100羽のウサギはみんな月の裏側にいるの。そこは地獄よ。だってあんな狭い場所に100羽ものウサギがいるんだもの。当然のごとく土地の奪い合いを始めるわ。つまり殺し合いよ。満月の夜、そこで最後まで生き残ったウサギが、次の月の表側のウサギになれるの。そうそう、なんでウサギが餅つきなんてしているかわかる? 実はあれは餅つきじゃないの。あれは自分が殺してきた99羽のウサギと、自分の前に月の表側にいたウサギの死骸をついてるの。なぜならその死骸から新しい100羽のウサギを生み出すため。あれは新しい100羽を生むための儀式なのよ。そして最後に新月が訪れて、月の表側のウサギも死に、新しく勝ち残ったウサギが月の表側で餅つきを始めるの。月はそのサイクルを私たちが生まれてくるずっとずっと前から繰り返しているのよ。そしてわたしたちが死んだ後もずっと……」
Qはそれだけ言うと静かに微笑んでぼくの前から姿を消したんだ。あとには闇だけが残った。黒に黒を混ぜたような闇だけが。
朝起きるとぼくはまずシャッターを開けて空を見たんだ。そこには青い空の一部分を漂白したみたいに月がかかっていた。あそこではぼくの想像を絶するようなことが起こっている。そう考えると怖かったな。なぜ夢の中にQが出てきて、しかもそんな話をしたんだろう。ぼくは学校に着いたらQに聞いてみることにしたんだ。
「それは夢じゃないよ」
昨日の夢のことを一通り話したぼくに、Qは言った。
「夢じゃない? それはどういうこと?」
ぼくが言うとQはうつむいた。
「言えないようなことなの? それとも説明するのが難しいとか?」
ううん、そういうわけじゃないの。Qは首を横に振った。そして
「わかった。放課後、屋上に来てくれる?」
と言った。
「うん放課後に屋上だね。行くよ」
風が強く吹いていたのを覚えている。屋上に着くとそこにはすでにQがいた。
「ごめん、待った?」
ぼくは柵を掴んで遠くを眺めているQの背中に向かって言った。
「大丈夫、私も今来たところだから」
Qが振り返って言う。
「それで、夢じゃないってどういうこと?」
「その前にこれを見てくれる?」
そう言ってQはぼくのほうに手を差し出したんだ。そこには――UFOが乗っていた。
「それは……」
「これはK君も知ってのとおりUFOだよ」
「なんでQさんが持っているの?」
「昨日K君の家から持ってきたの」
ぼくの家から持ってきた? ぼくは驚いてしまったよ。だってぼくはQさんを家にあげた覚えなんてなかったんだもん。
「驚くのも無理はないよ。私はK君が寝ているときにUFOをあの田んぼに呼び寄せたの。一昨日も同じようにUFOを呼び寄せたんだけど、私が回収しに行く前にまたK君に取られちゃったの」
「ど、どうしてそんなことができるの?」
ぼくが恐る恐る聞くと、Qは一呼吸開けてから言ったんだ。
「私は宇宙人なの」
そしてQは眼帯を外した。その瞬間Qが光に包まれたんだ。ぼくは眩しさに耐えられなくて、目を瞑ってしまった。そして再び目を開けた時、そこに立っていたのは紛れもない、宇宙人だった。
「これが私の本当の姿なの」
ぼくはあまりの衝撃に言葉を失ってしまったよ。ぼくがずっと会いたいと思っていた宇宙人が、今、目の前にいる!
「ほ、本当にいたんだ……」
「あの田んぼはUFOの発着地点なの」
Qは、宇宙人の姿をしたQは話し始めた。
「ほら、ミステリーサークルって知ってるでしょ? あそこの田んぼにもミステリーサークルが作られたって事件、覚えてる? あれは私の仲間が作ったものなの」
そういわれて思い出したよ。何か月か前、あの田んぼにまだ稲があった時、確かにそんなことがあった。
「それで、あの夢はなんなの?」
ぼくは聞いたよ。
「あれはテレパシーよ」
「何のためにあんなことをぼくに話してくれたの?」
「特に意味はないよ。でも、それが口実になって呼び出せればいいと思ったの」
「そんな……でもどうして呼び出す必要なんてあったの?」
ぼくはさらに聞いた。
「Kくん、宇宙に行ってみたい?」
どうして突然そんなことを言い出したんだろう?
「行きたい?」
Qがもう一度言う。
「い、行きたい」
宇宙に行くのは当時のぼくの夢だったんだ。
「うん、わかった。じゃあ今からあの田んぼに行こう」
そういってQはぼくの手を握って屋上の出口へと歩き出したんだ。ぼくは最初は引っ張られるような体勢になって、そのあとで一緒に並んで歩いた。Qの手は相変わらず不思議な感触がしたな。
「さあ、行くよ」
田んぼの真ん中にUFOを置いたQが、ぼくに向かって言った。そして気が付くとぼくたち二人はUFOの中にいたんだ。UFOの中は温かい水のようなもので満たされていて、とても気持ちがよかったよ。やがてUFOがゆっくりと飛び立った。
ブルーのビー玉のような地球を見下ろしながら、ぼくたちは一つになったんだ。
ぼくの話はこれでおしまい。あのあと……あのあとってのはぼくとQが宇宙に行ったあとのことだけれど、あのあとぼくとQがどうなったかは、秘密だ。残念ながらね。でも僕はもうあの町に住んでいないし、あの田んぼもぼくが引っ越す前に新しい家がたくさん建って消えてしまった。それは事実だ。
そもそもなんでぼくが君にこんな話をしたのかと言うと、七年の時を経て、ぼくの心に整理がついたからなんだ。そこでぼくはこの話を誰かにしたい。しなくてはならない。そう思ったんだな。もしも君がこの話を気に入ってくれたんだとしたら、それだけでもうぼくは君にこの話をした価値があると思っている。でも、もしも気に入ってもらえなかったとしても、それはそれでいいとも思っているんだ。だけどね、気に入ってもらえようがもらえなかろうが、十年後、二十年後、君がふと夜空を見上げた時に、そこに月が輝いていて、その月を見た時にきみがこの話を思い出してくれたとしたら、そんなにうれしいことはない。そうだ、今日はちょうど満月じゃないかな? ほら、見てごらん。