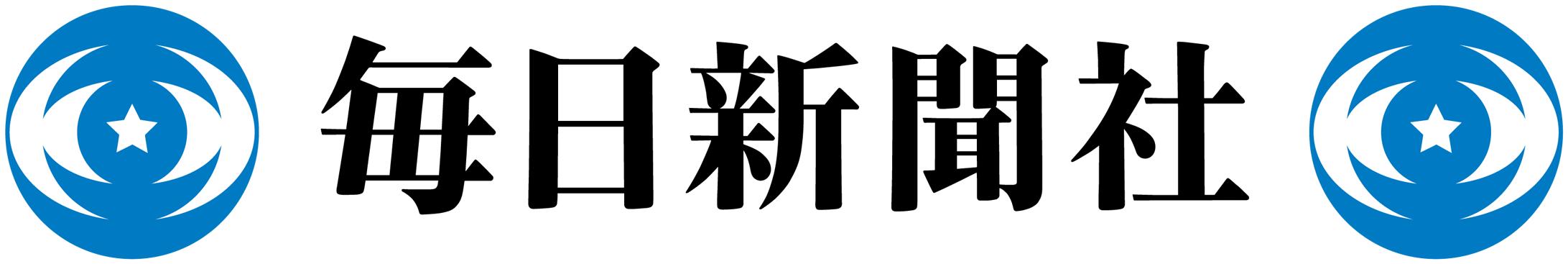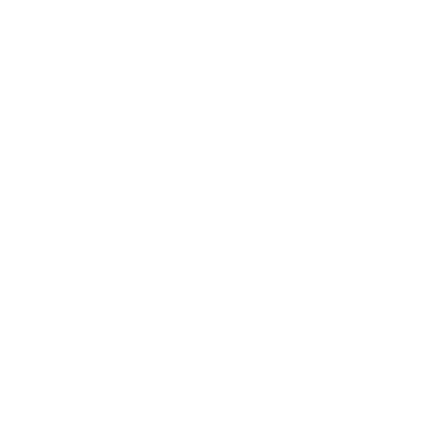織田作之助賞 U-18賞受賞作品
U-18賞受賞作品
「思い出屋と私」 浅田 紗希
その日のことを、私はもうほとんど覚えていない。
当たり前かもしれない。もう二年も前のことなのだから。そう割り切るのは簡単だった。
でも私は、忘れたくなかった。
だから今、これを書いている。
その日は、夏休みが間近にせまった暑い日だった。
太陽の位置の関係で、登校したときは影だらけだった道が、下校しているときには真っ白に輝いて見えた。
「……」
日の光が反射する道を通るのは、きつい。遠回りでもいいから、日陰を歩きたい。そう思って、路地に入った。
路地に入ると、いろいろな音が消える。ランドセルで殴り合う低学年の子たちの声や、テストを見せ合う同級生の奇声などが、すっと遠のいていく。正直、ちょっとこわい。
路地は広くない。が、決してせまくもない。ときどき野良ネコや迷いアライグマと会えるこの道が、きらいではなかった。
さびれた感じのビルや和風の家が並ぶ道。意外と木が多い。今の時期はセミがとてつもなくうるさい。耳をふさごうかの思った。
そんなとき。
空が急に曇ったかと思うと、ザアッ、とすごい勢いで雨が降り出した。
傘持ってない。とっさにハンカチを取り出して頭からかぶり、屋根を求めて走った。ずいぶん変なところを走った。白や水色やピンクの光の横を通ったような気がして、変には思ったものの雨のせいで顔が上げられなかった。その次に、緑の光があやしく光る店の前を通りすぎた。あやしすぎて入る気になれなかった。
緑の光が視界から消えたとき、嫌なことを思い出した。唐突に。
コピー機の下に、見つからないように押しこまれていたもの。見つけて絶句し、姉に見せてから細かくやぶいて捨てた。それ以来、同じものがどこかに隠されていないか、血眼になって探している。
嫌な思い出が、次々にひっぱり出されてくる。五年生のときのこと。一年生のときのこと、二年生のときのこと。時間がめちゃくちゃになり、ついにずっと封じ込めていた思い出がうかんだ。
あれは確か、八歳のときのこと。家族四人で海に行って、泳いだ。浮き輪につかまって、深いところへも行った。海水が日焼けにしみたが、楽しかった。そう、途中までは。でもだんだんつかれてきて、そして。
思い出していたら、目眩がした。一瞬くらっとして、ぬれた地面で足が滑った。え、うそ、と思ったときには、こけていた。地面でひざを打ち、力がぬけた。
「いったぁ〜」
涙声でつぶやき、よろよろ立ち上がる。打った足をひきずるようにして、ちょうど近くにあった店の軒下に近づいた。
軒下に入る前に、ちらっと見上げておく。大きな木の看板があった。筆で書かれた「思い出屋」という文字が上手かった。
身をかがめてひざを見る。皮ふがちょっとむけてあざができていた。あー、痛い。
かぶっていたハンカチをとり、あざを軽くたたいてみる。……痛い。
傷を見ながら、さりげなく店を見てみる。思い出屋、だっけ。
和風のお店。大きく開かれた引き戸にはガラスがはまっていて、「仲介料 いただきます」というはり紙がはられていた。仲介料って何だろう。変な店じゃなさそうだけど。
「大丈夫かね?」
いきなり声をかけられたので、びっくりして肩がはねた。
声のした方を見ると、店の奥のほう、カウンターらしき机のそばに、おじいさんがいた。店の人だろうか。
「びしょぬれじゃないか」
おじいさんはそう言うと、カウンターの下を探り、白いタオルを取り出した。そして、こちらに差し出してくれた。ありがたく貸していただく。
「ありがとうございます」
「いやいや。いつの間に降りだしたのかね」
「えっと、さっきです」
髪やうでをふきながら答えると、おじいさんは「うーん」とうなった。
「天気調節屋が失敗したかねぇ。暑さに耐えかねて小雨を降らそうとしたのじゃろうが、これじゃ大雨だ。跡継ぎだろうね、失敗したのは。ま、修行中だからねぇ……」
何を言っているのかわからない。やばい人なのかも。思わずタオルをにぎりしめ、おじいさんをしげしげと眺めてしまう。
「とはいえ、陽も悪いね。風も。さっさと雲を追い払って、地面を乾かさんかい。陽は居眠りじゃな。風は、昼寝の時間かのう」
「あのう、何の話です?」
勇気をふりしぼってきいてみると、おじいさんはなぜか申し訳なさそうに私を見た。
「いやね、最近はどこも年寄りだから。風は違うがね。あ、タオルもういいかい」
「あ、はい」
タオルを返した私は、また勇気をふりしぼって、きいてみた。
「天気調節屋って何ですか」
「その名の通りだよ。ここら辺の天気をつくってる」
天気って、つくれるようなものだっただろうか。
「水関係の天気をつくってるやつは修行中じゃから、調合する割合を間違えたんじゃ」 調合? 割合? あ、そうやってつくるの?
空想の話だろうか。すぐにここをでていきたくても、まだ雨が降っていて飛び出せない。おまけに、ひざも痛い。どうしよう。
ぬれきったハンカチをポケットに戻してポケットまでぬれるのがいやで、にぎりしめたままでいると、おじいさんが言った。
「申し遅れたが、わしはここの店主で、言本という」
「こともと、さんですか」
「言葉のことに、本と書く。お嬢さんは、何とよべばいいかね」
「ええと、北木マキです」
知らない人には名前を教えないこと。とっさに、偽名を口にしていた。
「ほう。して、本名は」
「え」
心臓の音が一瞬大きくなった。
「ハンカチのイニシャルと違うがね」
はっとして、手に持ったままのハンカチに目を落とす。薄桃色のハンカチに、黄色の糸で「S・K」と刺繍されている。
ポケットに戻さなかったばっかりに……Kだけは合っているのに。
「……織間輝起です」
「しきまきた? 珍しい名前じゃ」
おじいさんだって。言本っていうのに。
「どういう字を書くのかね?」
「組織のしきに、あいだで織間。輝起は、輝きが起こる、です」
起こるの起を「た」と読むのは、けっこう珍しいと思う。
「ほう。ところで織間さん、ここに来る途中、緑の光のある店の前を通ったかね」
「え、はい」
「そのすぐ後、嫌なことを思い出したね?」
なぜ知っている。口を閉じてうなずいておく。
「緑の光のある店は進め屋といってな。進め屋の緑の光を見ると、皆、つらい記憶、嫌な記憶を思い出す」
「最低じゃないですか」
「そしてその記憶を、乗り越えるしかない者は進め屋で足がとまる。いい思い出に変えられる可能性のある者は、ここ、思い出屋にたどりつく」
「本当の話ですか? それ」
言本さんは微笑んだ。
「もしそうだとしたら、どうするね?」
どうするねと言われても。
「本当の話じゃよ。表ではないこちらでは、物事はこうやって進んでいく」
「どうやってですか」
「織間さん、思い当たることがあるんじゃろ」
無視された。
「記憶をいい思い出に変えるのに、決まった方法はない。じっくり店にあるものを見ていきなさい」
「はぁ」
言本さんは混乱しかける私を見てひとつうなずき、店の奥に去っていった。
ひとり残される私。まずハンカチを畳んでポケットにしまう。ポケットが冷たくなって、不快だ。
店を見回す。……まぁ、雨がやむまでくらいなら……。
店の中はごちゃごちゃだった。いや、整理してあるのだろうが、とにかくものが多い。それも、不思議なものが。
鳩の体丸々(剥製だろう)がついた大きすぎるブローチ、持ち手がなぜかにんじんでできている新品の鍋はぎりぎりいいとして、さびた水道の蛇口や、持ち手しかないティーカップはどうだろう。不思議というより変だった。
変じゃないものも当然ある。ちょっと安心した。
見ていて気になったのだが、ここにあるものには値札がついていない。どれひとつとして。なぜだろう。
店を一回りしかけた時、ふとまともそうなオレンジの手ぬぐいの下に目がいった。オレンジと真逆の色、深い青が見えた。
色がきれいだったので、端をつかんでひっぱり出してみる。それはひっぱられて畳まれていた状態ではなくなり、大きく広がった。
ハンカチのようだ。不思議なことに、色が変わっていく。青から緑、また青、しわの部分は白。特に、白い色が大きく揺れ動く。まるで、海のように、手触りもさらさらとして、つめたい。
海か。
緑の光のせいで思い出したことが蘇る。
私は八歳だった。家族で海に行き、深いところで浮き輪を使って泳いでいた。そしてつかれたところで浮き輪をつかんでいた手がすべり、頭まで海水にしずんだ。運の悪いことに、しずんだ時ゴーグルをしていなかった。海水は目にしみる。目が痛いのと急なことだったのとでパニックになった私は、がむしゃらに足を動かし、すぐに浮かぶことができた。
しずんだのはほんの一瞬。かなり水をのんだので、しばらくは学校のプールもこわかった。今はもうトラウマはないが、嫌な思い出として記憶に残っている。
そこまで思い出したとき、青いハンカチの変化に気がついた。
ハンカチの真ん中あたりに、何かいる。小さいもの。このシルエットは……魚?
まさか、と思った瞬間、ハンカチから何かが飛び出してきた。銀色のもの。
それは親指の爪に落ち、ぴちっとはねてハンカチの中にちゃぽんと戻っていった。
魚だ。間違いなく。
種類はよく分からない。いやよれよりも、なんでハンカチから魚が?
棚にランドセルがあたらないようにゆっくり動き、言本さんを探す。意外と近くにいた。
「それが気になったかね」
品の整理をしていたらしい言本さんが言った。私は曖昧にうなずく。
「それは四年前につくられた。だいぶ昔のことじゃが、持ち主はまだ現れん。きっとその思い出が嫌いなんじゃろうな」
「へぇ」
さりげなく、ハンカチを自分から遠ざける。
「持ち主はその記憶をすでに乗り越えておる。じゃからそれは、持ち主にとっていい思い出でも悪い思い出でもないのじゃ」
「ならなぜ、ここにあるんですか?」
おそるおそる、きいてみる。
「ごく最近、持ち主の環境に変化が起きたからじゃ」
「……」
「その変化によって、その思い出はいい思い出になるかもしれない可能性をもった」
「そうですか」
会話をぶった切る。青いハンカチを畳み、もとの場所に戻す。
「気になったものは買わないのかね?」
「買いません」
きっぱり言う私を見て、言本さんはほっはっと笑った。その目が、私の額のあたりにとまった、気がした。
「……それで、コピー機の下から見つかったのは、何じゃったんじゃ?」
心臓がはねた。
立ち位置を後ろにずらす。すると、ランドセルが棚にあたった。がちゃがちゃと物が揺れる音がする。
この人は、一体、何者?
「織間さんは、見つけたもののせいで嫌な思い出を切り捨てている。違うかね」
言本さんは続けた。私の反応を無視して。
「今の織間さんのすべての中心には、そのものがある。それは、一体なんじゃ?」
私は長めにまばたきをした。
コピー機の下。汚れていそうだったので、汚れ具合を調べようとつっこんだ指は、何かの紙にあたった。特に考えもせずひっぱり出し、見た。そして。
最初は、何の紙か分からなかった。でも理解した。その瞬間、固まった。
言本さんはなぜ知っているのだろう。考えながら、私は答えをさらりと口にした。
「離婚届です」
言本さんがまばたきした。
見つけたときの衝撃は、並のものではなかった。鳴りやまない心臓をおさえ、姉に見せた。姉は、見たことがない表情をした。それは姉妹の間で細かくやぶられ、捨てられた。離婚届には、まだ何も書かれていなかった。それを唯一の希望に、私たちは隠され続ける離婚届をやぶき続けている。
「……なるほど。だから、これまでの家族の失敗した思い出を嫌ったと」
「はい。何で知ってるんですか?」
「わしら記憶を扱う者たちは、人の心や古い記憶を読めるのじゃよ」
「本当ですか?」
「つじつまが合うじゃろ。それより、ハンカチが気になったと見えるが、本当にいらないのかね?」
「いらないです」
「そうかい」
言本さんは納得していないようだった。
雨がやんだので帰ります、と言うと、引きとめることもなく見送ってくれた。が、店を一歩出たところで、こう言われた。
「明日も来て、考えるといいよ」
私はただ頭をさげて、その場を去った。
ここまで書いて、シャーペンをとめた。
たしか、こうだったよな。
記憶を引きずり出して、考える。このあとは、どうしたっけ。
シャーペンを持ち直したところで、何気なく後ろをふり返る。後ろの棚のハンカチ入れに、他とは明らかに質の違う青いハンカチがある。
私は微笑んで、目の前のノートに向き直り、続きを書こうとシャーペンをたてた。
次の日学校が終わると、またあの路地に向かった。理由はひとつ、思い出屋に行くためだ。
行かなくてもいいんだけど、昨日はちょっと失礼だったかなと思った。それだけ。
途中、緑の光がまたたく進め屋を見ないようにしながら通り過ぎる。そして思い出屋にたどりつき、店に一歩足を踏み入れた私は、驚いて立ち止まった。
言本さんがいない。それだけじゃなく、知らない女の人がいる。誰?
肩までの黒い髪、ちょっとぎょっとするほど白い肌。真っ白のワンピースを着ている。
私の気配を感じたのか、その人がふり返った。
「もしかして、織間さん?」
「あ、はい」
けっこう美人。大学生ぐらいだろうか。
「言本お爺から聞いてるわ。私は若葉香。言本お爺の知り合い」
「言本お爺?」
「うん。私はそうよんでる」
「はぁ。あの、言本さんは?」
「後継者探しの旅に出てる」
後継者?
「この辺はどこもけっこう高齢だからね」
ああ、そういえば昨日も、どこも年寄りだと言本さんが言っていたっけ。
「私バイトだから分かんないこと多いけど。まぁ、ゆっくり見てってよ」
「はい」
それだけ言うと、また背中を向けて何かの整理を始めてしまう。私はそれを見つめ、それからあの青いハンカチの所へ急いだ。
まだあった。相変わらず、青と緑が混ざったような色で、ときどき波のような白い色があらわれる。きれいだ。
手に取って、迷う。ほしいのか、ほしくないのか、よく分からない。
「へぇ、それ?」
「わっ」
真後ろに若葉さんがいた。いつの間に。
私の驚きを無視して、若葉さんは続ける。
「そのハンカチ、本当にどこかの海とつながってるんだって。だから色が変わったり、波がたったり、クジラが言えたりする、らしいよ」
「はぁ」
昨日爪に落ちてきたごく小さな魚を思い出す。
「実体験あるんじゃない?」
その一言で私をぎょっとさせてから、若葉さんはカウンターのほうに去っていった。
手の中のハンカチを見つめる。ひんやりとして、白い泡が見える。さっきの話は本当のこと?
考えてみる。離婚届と、おぼれた思い出を。
離婚届を見つけてから、今までの家族の失敗のせいで、親が離婚する気になったのだと思った。違うだろうが、完全には否定できない。だから私は、嫌な思い出をさらに憎むようになったのだ。
離婚届を見たあとの、姉の表情を思い出す。離婚のことを知って以来、家族で笑うようなことがあると、姉は決まって同じ顔になる。
「これははりぼての笑いなんだ」という顔。
離婚届を用意するほど、仲が悪い両親。子どもの前ではそのことを隠す両親。そして隠されていることを知りながら、大きな行動を起こせない姉妹。その間でかわされる笑顔は、確かにはりぼてだった。
ふとそこで、姉が一度だけ言っていたことが蘇る。「はりぼてじゃなかったころの思い出がほしい」と。
私もだ。ほしい。
嫌な思い出でも苦しい思い出でもなんでもいい。家族だったころの思い出がほしい。 意外とはやい心変わりだ。
そんなことを考えつつ、ハンカチを見つめる。これだけ持っていても、体温がうつらない不思議なハンカチ。
ハンカチの青がにじみ、四方に広がった気がした。
気がつけば、私は海の中。音のない世界は心地いい。こぽり、と音がして、空気の泡が上っていく。美しい。が、私にとってはトラウマの残る場所。
目を閉じて、また開ける。
もとの思い出屋の中。ハンカチも、もとと同じ。
まわりを見ると、若葉さんが興味深そうにじっと見ていた。
「ふうん。はじめて見た」
満足げだ。「何をですか?」
「人が記憶に落ちていくところ」
「え」
「思い出から戻ってこれない人、少なくないらしいけど。織間さんは、大丈夫そうね」
「そうですか」
うんうんとうなずく若葉さん。どうもこの路地のあたりの人はみんな変らしい。
「あの、このハンカチいくらですか?」
「うちは思い出をその持ち主に紹介しただけなので、品物の代金はいただきません。その代わり、紹介した分の仲介料をいただきます」
引き戸にはってあったはり紙を思い出す。そうか、「仲介料 いただきます」って、そういう意味だったのか。
「いくらですか?」
「ちょっと待ってね」
若葉さんはカウンターのほうに行き、下から電卓のようなものを取り出して、なにやらかたかた打ち始めた。そして、それを見ながら言う。
「時間も手間もかかってないし、代金は格安だね。えっと、何か他人の思い出が詰まってそうなものをいただきます」
「お金じゃないんですか」
「うん、お金なんかもらってもあんまり使わないしね。ノートの一ページとか、ねじとか、そんなんでいいよ」
「そうなんですか」
あったかな。最悪、ノートの一ページにしよう。
「ハンカチ貸して。包むから」
「あ、はい」
ハンカチを渡し、若葉さんが薄い包み紙に手こずっている間に、ランドセルを下ろして中を探る。くっ、適当なものがない。教科書はだめ、えんぴつは思い出が詰まってない。
あ、そうだ。
「できたよ〜」
包み紙に苦戦した若葉さんが、若干しわのよった小さな包みを差し出してきた。私は、ランドセルにつけていた小さなストラップを差し出す。イルカの形で、木彫りである。
「これ、いいの?」
「はい。拾ったもので持ち主がみつからなかったやつだし、このイルカ、あんまり顔かわいくないし」
「そうだね。じゃ、これが支払い、ということで。返金不可能ですよ」
「しませんよ」
包みをランドセルにしまう。ランドセルをかついでから、店の引き戸の近くで若葉さんをふり返る。
「言本さんに、ありがとうございましたって言っておいてください」
「うん、お爺に伝えとく。気をつけてね」
「はい。じゃ、さようなら」
「さよならー」
こうして私は思い出屋を去った。青いハンカチを買って。正確には、思い出を受け取って。
こんなもんかな。
シャーペンを置いて、ノートの上の消しゴムのかすをはらう。完成だ。
私が小学校を、姉が中学校を卒業すると同時に、両親が離婚した。私は父と、姉は母と暮らしている。
姉とは今でもこっそり会っている。なのであまりさびしくはない。ただ、離婚で姉の名字が変わってしまったことだけが残念だった。
あの後、思い出屋には二度と行くことができなかった。なぜだろう。もう私には受け取るべき思い出がないだろうか。
ふり返って青いハンカチを見る。ときどき魚やクジラの影が見えるのだ。夕暮れ時にはオレンジ色に変わる。本当に、不思議なハンカチだ。
目を閉じてみる。あたりが青一色になり、音が消えるように錯覚する。
目を開けると、もとの部屋。
死ぬまでには、もう一度くらい言本さんや若葉さんに会えるかな。そのときには、私が払った仲介料がどうなったか、教えてもらおう。たぶん売られているのだろうが。
私はそう思ってから、気持ちをきりかえ、シャーペンの芯をカチカチ出した。