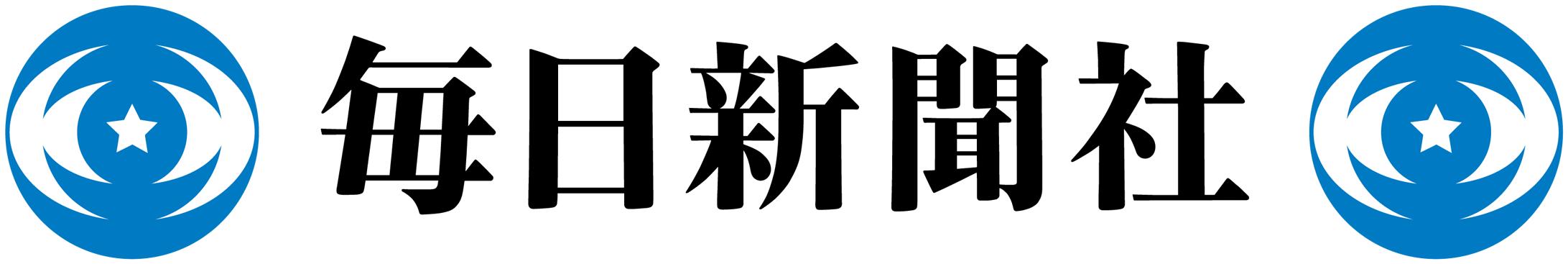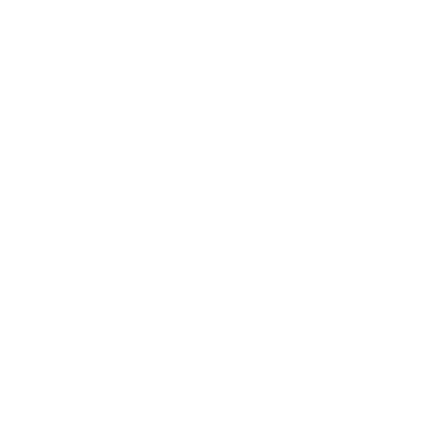織田作之助賞 U-18賞受賞作品
U-18賞受賞作品
「サイコロバレンタイン」 吉田菜々穂
「おっ、今朝はメロンパンか」
部屋からのっそりと出てきた小太りのおじさんが、ネクタイを締めながら椅子に腰かける。この人は、メロンパンが大好きな、私の父親。パパは曲がったままのネクタイから手を離すと、メロンパンを手に取って微笑んだ。
「今何時?」
パパが、パンの袋を不器用に開きながら尋ねた。私はケータイの画面を睨むように、冷たく見下ろして答える。
「……八時」
「えっ、もうそんな時間か」
ようやく取り出したパンを強引に口の中にねじ込んで、カバンを手に慌てて玄関に。
「今日は遅くなるだろうから、先に夕飯食べておくんだぞ」
「……」
「……それと」
ああ、まただ。毎日聞かされてもううんざり。
「今日こそは、その…、気が向いたら学校に……」
「早く行けば?」
私の冷たい言葉にパパは苦笑いをして、そそくさとドアを開けた。
「行ってきます」
扉が閉まった瞬間、私はカチャッと施錠した。こぼれるめ息を飲み込んで、手に握っていたケータイにちらりと目をやる。時計はちょうど七時五十分を指したところだった。
私は所謂(いわゆる)不登校というやつで、ここ半年ほど学校に通えていない。きっかけは、仲がいいと思っていた女の子が悪口を言っている現場に遭遇した。ただ、それだけ。でも、そのショックで一日学校を休んだら、もう登校できなくなってしまっていた。ローファーを履いただけで嘔吐は当然。ひどいときなんて制服を見て失神した。その女の子は今までに一度も連絡をくれないし、会いに来たこともない。きっとその程度の友情だったんだ、と自分に説明しつつ、パパにイライラをぶつけては部屋にこもる日々が続いている。
今日は、違う。別に、何か特別な日という訳でもない。ただ、今朝はパパが出張で家にいなかった。パパが「学校に行け」と言わなかった。それだけのことだ。軽く被ったホコリをパッパッと払って、重たい鞄を持ち上げた。まだあの日の時間割通りに、教科書たちが背中をのぞかせている。今日の時間割なんて知らない。もうこのままでいいや、と、鞄を持ち上げたところで、ふと思いつく。お弁当がいるかもしれない。いやいや、お弁当の時間まで教室に居続けられる自信なんてない。どうせ早退するんだ。お弁当なんていらないに決まってる。そんな考えがグルリと頭の中を回ったけど、私はブンブンと首を振って、冷蔵庫にしまっておいた卵焼きを取り出した。食器棚の奥から、もう何か月も使っていないお弁当箱を取り出して、卵焼きを一つずつ丁寧に詰めていった。近くにあったうさぎの風呂敷で綺麗に包んで、それをそっと鞄の底に押し込んだ。鞄のチャックをサッと閉めると、私はそれを肩にしっかりとかけた。
ゆっくりと玄関の扉を開ける。冷凍庫みたいな冷気が私を前から包み込んでいく。二月の、それも朝となると、外はしっかりと冷えた空気が待ち構えていた。今日はイケる。そんな気がした。一歩、踏み出した。ローファーのカツンという音が懐かしい。カツン、カツンと早まる足音に、胸が躍る。頬を撫でる風がなんだか優しい。目の前に広がる裸の街路樹のトンネルも、温かい。途中で鍵をかけ忘れたのを思い出して急いで玄関まで戻ったけど、今日またここに戻るのはしばらく先になるかもしれないと思った。だけど、そう呑気でいられたのも束の間だった。
私の心音のような足音は、ぴったりと止んでしまっていた。あと十歩ほどで、校門。門の少し奥に建った、ちょっと大きめの物置みたいな小屋から、警備員のおじさんがこちらを不思議そうに見つめている。パパより少し年上くらいの、ちょっぴり怖い顔の警備員さん。ちゃんと学校に通っていたころは毎日目を合わせて挨拶していた。相変わらずのしかめっ面で私のことをしばらく眺めてから、おじさんは小屋の奥へと入っていってしまった。そりゃそうだ。女子中学生が、それもこんな朝早くに、校門の前で硬直しているなんて気味が悪い。もう、帰ろうかな。今なら引き返せる。私はコンクリートに埋め固められたように動かない足を持ち上げようとした。その瞬間、私の背中に高らかな笑い声が反響して、体がじんじんと振動した。まずい、誰か来た。女の子の声。途端、両膝ががくがくと震えだした。足が動いてくれない。息もうまく吸えない。それになんだか寒い。そこで私はようやく、コートも着ずに家を飛び出してきてしまったことに気付いた。画面がフリーズしたケータイみたいに、自分の体が言うことをきいてくれない。おまけに胃が、梅干しを食べたときの唇のようにすっかりしぼんでしまって、苦しい。朝食べたヨーグルトが口から出てきそうだ。ああ、きっと、吐瀉物にまみれて震える私を見て、後ろの女の子たちが悲鳴を上げるんだ。そして学校中で噂になって、私はもう二度とここへは来られないんだろう。こんなことなら外に出るんじゃなかった。学校になんて、来るんじゃなかった。
「お嬢さん、こっちにおいで」
その時だった。ケータイやら梅干しやら、もう訳のわからなくなった私の体が、一本の腕に軽々と引き寄せられた。私はその腕に連れられて、十歩ほどヨロヨロ歩いた。歩いたというか、それはもう操り人形が足を交差させて躍っているような、そんな進み方だった。
気が付けば私は、ひんやりとした壁に背中をくっつけて、座り込んでいた。ほんのりと温かい空気が私の鼻から肺へと行き渡る。どうにか落ち着いて、ゆっくりとまわりを見渡す。天井は灰色で、低い。それにどうも狭くて、机と棚が一つずつに椅子が二つ、窮屈そうに並んでいた。棚の上にはポットが置いてあって、湯気が白い手を伸ばして天井に触れている。そうか、ここはあの警備員室だ。
「佐藤君。彼女、気が付いたみたいだ」
「あ、本当だ」
二人の男の人の声が、上から聞こえる。ん? 上から…?
「わあっ」
「わ、ごめん、驚かせちゃったかな」
見上げた先に、若い男の人とおじさんの顔が一つずつ、浮かんでいた。よく見たら、小屋の窓に外から顔を出していただけだった。
「俺が外を見ておくから、佐藤君は彼女といてやりな」
怖いおじさんの声を合図に、二つの頭が同時に引っ込んでどこかへ消えてしまった。すぐに小屋の扉が開いて、佐藤さん、と呼ばれた、若くて体の大きな男の人がニコニコしながら入ってきた。
「あ、あの、私帰ります」
えっ、と戸惑う警備員さんにぺこりと頭を下げた。近くに寝かせておいてくれていた鞄を肩にかけて勢いよく立ち上がる。そんな私を、警備員さんが、その長い腕で優しく掴んで引っ張った。さっき私を引き寄せた腕だ。
「もう少しここにいなよ。顔色がよくないよ」
反論しようと顔を上げると、そこには笑顔があった。改めて見ると、初めて会う顔だった。おじさんというよりはお兄さんって感じで、爽やかに私を見つめている。不覚にもドキッとしてしまうけど、それどころじゃない。早くここから出ないと、登校する生徒たちがどんどん増えて、帰るに帰れなくなってしまう。私は黙って腕を振り払うと、扉に手をかけた。でもその時、扉の向こうでおじさんの素っ気ない挨拶が聞こえた。挨拶の返事と一緒に、扉の隙間から笑い声が漏れてくる。今このタイミングで外に出たら、笑っている誰かに見られてしまう。そんなことを考えて固まる私の頭にポンと大きな手を乗せて、
「ここで少しゆっくりするといいよ」
とお兄さんは微笑んだ。私は小さくうなずいて、さっきと同じ場所にストンと座り込んだ。
ポットがゴーッと危うい音を吐き出す。お兄さんは、微妙にダサい花柄のマグカップにココアをなみなみと注いで渡してくれた。そっと受け取って、唇を近づける。噴きこぼれるほどの湯気にしては、随分とぬるい。
「待ってね、今暖房入れるから」
「……入れてなかったんですか」
「うん。僕たちも今来たところだしね」
道理で、ここは外と大して温度が変わらない。あれ、ならどうしてさっき私は、温かいと思ったんだろう。
「おはようございます」
ビクリと肩が揺れた。お兄さんが突然大きな声を出すんだもん。でもそれは、私じゃなくて外を歩く学生に向けられた言葉だった。
「はよーございまーす」
何人かの男の子たちの声だ。誰だろう。
「お嬢さんお嬢さん」
「はいっ」
突然呼ばれてまた肩が揺れる。
「そこにね、穴があるんだ。壁穴」
お兄さんはいたずらっぽい顔で、こっそりと耳打ちするように教えてくれた。穴に右目をのぞかせてみると、ちょうど校門が端から端まで見渡せて、さっき通った男の子たちの姿もよく見えた。野球部の集団だ。白い息を顔の前にいっぱい吐き出しながら、駆けるように校舎へ向かっていく。こんな朝早くから練習だろうか。熱心なんだな、うちの野球部。
「どう? こういうの結構楽しくない?」
お兄さんがニコッとして尋ねる。
「いえ、まあ…はい……」
曖昧な返事をしてから、私は壁にもたれかかって、再び穴から外を覗いた。
「おはようございます」
髪の長い女の子が愛想よく挨拶していく。きっと優しくて、モテるタイプの子だ。
「おはようございます」
「おはようございまーす」
今度は大きな楽器を抱えた女の子たちだ。四、五人でおそろいのマフラーを巻いている。よっぽど仲良しなんだ。ゲラゲラと笑いながら通り過ぎていく。吹奏楽部だろうか。
「おはようございます」
「あら、お兄さん。今日もお早くて」
あれは男たらしで有名な音楽の先生だ。女子生徒からはかなり嫌われてたけど、手入れの行き届いた綺麗な爪は、努力家な彼女の姿を思わせた。その後も流れるように人が入ってきて、それぞれに校門をくぐっていった。
よく耳を澄ませると聞こえてくるのは、二日後に控えたバレンタインの話題。機嫌のいい人、悪い人、寒そうな人、汗ばんでいる人。壁穴からなら、それこそ穴が開くほど見つめていても気づかれないから、なんだか安心して眺めていられた。
いつの間にか始業時間を迎えて、リュックの肩ひもを両手で握り、息を切らして校門をくぐった生徒を最後に、人通りがすっかり減った。時々訪れるお客さんをおじさんとお兄さんが交互に対応しながら、何やら書類の整理なんかをやっていた。私はと言うと、暖かい部屋で鞄を抱いて、壁穴からぼんやりと野良猫や雀が門をくぐる様子を眺めていた。
「お昼だ」
うーん、とお兄さんが伸びをする。ただでさえ長い体が狭い小屋を埋め尽くす。
「休憩ですか?」
「正式な休憩時間ってわけじゃないんだけどね。十二時半はご飯タイムにしてるんだ」
お兄さんは自分のリュックを膝にのせると、そこから黒いお弁当箱を手に取った。
「お嬢さんは、食べるものはあるの?」
「……一応」
鞄のチャックを開いて、うさぎの風呂敷を取り出した。布の結び目を丁寧にほどいて、箱のふたをゆっくりと外す。
「わあ、おいしそうだね」
お兄さんの瞳が黄色く輝く。
「それで足りるの? 僕の少し分けてあげるよ」
「そんな、申し訳ないです」
「その代わり、僕にこれ、ひとつちょうだい」
「……こんなもので良ければ」
お兄さんは小さくガッツポーズをして、ありがとう、と笑いかけてくれた。おじさんの方は校内のパトロールに出かけてしまって、警備員室には私とお兄さんの二人だけだった。
「経験上この時間帯は人がほとんど通らないんだ。もちろん、不審者が入らないようにちゃんと見張ってはいるけどね」
確かに、外を見ると、校門を通っていくのは枯れ葉くらいで、辺りはしんとしている。
「なんか楽しそうですね。ここに住めそう」
「はは、住むにはちょっと不便かな」
お兄さんは私のお弁当箱に、ミニトマトとブロッコリーを乗せた。
「……お兄さん、野菜嫌いなんですか?」
「ばれた?」
意外。好き嫌いとかなさそうなのに。
「意外だと思ったでしょ」
「あ、はい」
「はは。やっぱり」
お兄さんのお弁当箱に卵焼きをひとつ、乗せてあげた。少年みたいにキラキラした瞳で卵焼きをつまむと、パクリとおいしそうに飲み込んだ。
「僕、卵焼き上手く焼けないから、尊敬するよ」
「自炊してるんですか?」
「まあ、母親は小さいときに亡くなったし、彼女も奥さんもいないからね。自分で作るしかないんだよ」
「そうなんですね……」
お母さんいないんだ。私と一緒だ。お兄さんはどうしてこの仕事に就いたんだろう。子供好きなのかな。こんなにいい人なのに、まだ結婚してないなんて、なんだかちょっと、寂しい。
それからは、しばらく二人でぬるいココアを飲みながら会話した。戻ってきたおじさんに、残しておいた卵焼きをひとつあげて、私はうとうとと眠りについてしまった。夢を見たけど、あまりいい夢じゃなかった。学校から逃げ出した、あの日の夢。
目が覚めると、入口から茄子色の夕焼けに染まった空気が差し込んでいた。
「おはよう。みんなそろそろ帰る時間だよ」
お兄さんが、朝と同じ窓から顔を出して教えてくれた。私もそろそろ帰らねばと思って、外の様子を伺おうと壁穴に目を近づけた。
「さよならー」
「さようならー」
色んなさようならがこだまのように飛び交う。あ、朝見た髪の長い女の子だ。誰かの悪口を叫んでる。あんな感じの子だったんだ……。
「行きと帰りとで、人って全然違うんだ」
ふと、お兄さんがポツリと呟いた。私が首を傾げて見上げると、彼は微笑んで続けた。
「日が違えばなお違う。この場所からはみんなの一部分しか見えないけど、毎回違う面が見えて面白いんだよ」
確かに、今日一日だけでかなり、みんなの色々な面を見られた気がする。きっと人間っていうのは、サイコロなんだ。いくつかの面を持っていて、それぞれに優しい所やわがままな所、真面目な所をコロコロと転がして生きているんだ。じゃあパパも、少しはかっこいい面なんかも持っているんだろうか。少しは鋭くて、少しは空気の読める面なんかもあるんだろうか。……いや、ないな。あんな加齢臭纏ったおじさんに、そんなのあるわけない。
「もう暗いけど、家の人心配しない?」
お兄さんが私に尋ねた。
「ずっとここにいたい……」
「ええー! 絶対やめた方がいいよこんな場所! 夏は暑いし冬は寒いし狭いし男しかいないし」
「そんなに、ですか?」
「うん。この時期の夜なんて絶対凍えちゃう」
ああ、そっか。私にいてほしくないのか。いや、普通そうだよね。警備のお仕事してる人の職場に居座って、ただ寝て喋るだけなんてどう考えても邪魔だし迷惑だ。さっさと帰ろう。人通りを確認してから鞄を胸に抱いて、入口から飛び出した。
「お嬢さん」
そんな私を、お兄さんは優しく呼び止めた。立ち止まって少しだけ振り向く。
「また明日も卵焼き、待ってるね」
はにかむように、笑っていた。その笑顔が瞼の裏に焼き付いてしまって、帰り道でする瞬きは、いちいちくすぐったくて仕方なかった。あの警備員さんたちのためなら、チョコを作ってあげてもいいかもしれない。
「お、今日はパンじゃないんだな」
白髪混じりの頭をボリボリと搔きながら、パパは椅子にドスンと腰を下ろした。
「出張中は夕陽(ゆうひ)のご飯が食べられなくて寂しかったんだ。いただきます」
ピンと張られたラップを汚く丸めると、パパはシチューを口へと運んだ。昨日の晩ご飯の残りを温めただけなんだけど。
「昨日はなあ、夜中の一時に帰ってきたんだ」
「早く出て行ってよ。もう八時半だよ」
「な、なんだって?! 大遅刻じゃないか!」
パパは風を切るように廊下を走り抜けて飛び出していった。嘘に決まってるじゃん。まだ七時四十分だし。やっぱりあのボケおじさんには、魅力的な面なんてない。絶対ない。でも、ボケてるおかげで台所に寝かせてあるトレイにも気づかれなくて良かった。何せあそこには、昨日の夜作ったチョコレートのお菓子たちが、所せましと並んでいるんだから。
今日も私は、警備員室の隅っこに座り込んで、壁穴を覗いていた。外は相変わらずの寒さだったけど、お兄さんがいれてくれたぬるいココアを手に、校門を眺めた。生徒たちの会話は、明日に迫ったバレンタインの話題で持ち切りだ。私も、台所に寝かせたお菓子たちを思い出しながらぼんやり過ごしていた。
「昨日の話の続きなんだけどね」
人通りが途絶えたお昼時も過ぎて、気づけばもう夕方だった。ちらほらと生徒が下校し始めたころ、パソコンで何やら作業をしていたお兄さんが口を開いた。
「昨日?」
私は少し首を傾げて昨日を思い出した。
「人は一目じゃわからないって話ですか」
「そうそう。いい例を思いついたんだよ」
「いい例?」
「この人、南さんっていうんだけどね」
お兄さんは、向かい合ってパソコンを触っていたおじさんを指さして説明してくれた。おじさんは困ったように俯いている。
「昨日の朝、君をここに連れ込んであげようって言ったのは、南さんなんだ」
「え……」
「でも、自分は若い子の気持ちなんて全然わからないから後は任せたって、僕に」
「そうだったんですか」
「余計なことを言いおって……」
南さんはお兄さんを睨んでいるけど、どこか照れ隠しのように見えた。
「この人、怖い顔してて不愛想だけど、本当は人見知りで優しい普通のおじさんなんだ」
「……半年前に校門を泣きながら駆け抜けるところを見て以来、ようやく見つけたからな」
私のこと、知ってくれてたんだ。しかも心配までしてくれてたなんて。なんだか、胸に湯たんぽを押し当てられたみたい。
「おじさん、ありがとう……」
「いや、まあ……」
南さんがゴニョゴニョと口を動かしている。人見知り全開で、可愛いとさえ思えてしまう。
「僕もね、いい例なんだよ」
「え?」
「僕はね、学生時代に勉強をしなかったんだ。気づけば大学受験は諦めてた。そんな僕を唯一雇ってくれたのがここだったんだよ」
聞けば、お兄さんはつい最近までニート生活を送っていたんだって。すごく、意外。
「どう? ちょっと印象変わったでしょ」
「はい」
お兄さんは恥ずかしそうに俯いて、おじさんと一緒にパソコンの作業に戻った。よく見れば、おじさんのタイピングの方が速くて正確だ。お兄さんは指をもつれさせながら不器用にキーを打ち込んでいる。その姿がなんだか可愛くて思わず笑ってしまう。と、その時、一陣の風がドアの隙間から入ってきて、書類を二、三枚外へ攫(さら)っていった。
「あ、私とってきますよ」
「助かるよ」
散らばった書類を集めながら礼を言う二人を背に、私は扉を開いて外に出た。一枚二枚と拾っていると、聞きなれた声が私を呼んだ。
「あれ、もしかして夕陽…?」
「あ……」
振り向いて声の主が分かった途端、体がピタリと止まった。
「み、瑞樹(みずき)」
「なんで、夕陽、ここに…?」
瑞樹が少しずつ近づいてくる。あまりに突然の出来事に、ただ震える自分の膝を見つめることしかできなかった。それも当然だ。瑞樹は私を不登校にした張本人なのだから。
「来ないで!」
「夕陽……」
私の叫び声に一歩後ずさってから、瑞樹は校門を一気に駆け抜けて行ってしまった。やっぱり、私とは話したくないんだ。はあ、はあ、と荒い息が白くなって消える。ポタリ、と頬を伝って液体が滴った。冷や汗だ。
「あれ、夕陽じゃん」
「えっ」
頭を持ち上げると、目の前に見覚えのある女の子の顔があった。裕子(ゆうこ)だ。
「久しぶり! 来てたの、学校」
「す、少しだけ。……いつもメールありがとう」
彼女とは、瑞樹と私の三人で仲良しだった。裕子だけは今でも私を気にかけてくれている。
「いえいえ。……瑞樹見なかった? 私あの子と一緒に帰る約束してたんだけど……」
「あ、うん。さっき走っていった」
「そっか。何か喋った?」
「……ううん」
「……夕陽と話したいって、ずっと言ってたよ」
裕子は私の表情を伺うように覗き込んだ。二人の間に沈黙が流れる。裕子は気まずそうに手を振って、またね、と微笑んで瑞樹の後を追っていった。瑞樹が……話したい? 私と?
しばらく立ち尽くして、私は警備員室に戻った。するとそこには、心配そうに、でもやわらかく笑うお兄さんが立っていた。
「行っておいで」
お兄さんは、私の背中をポンと押した。
「お嬢さんの知ってる一面が全てじゃないよ」
私はその言葉に弾かれるように、警備員室から駆け出した。
ローファーの音だけが、カツカツと響いている。朝聞いた音よりも重くて、低い。それでも私は、一歩一歩足を無理やり持ち上げて、追いつくかもわからない友達を追いかけた。
どれくらい走っただろう。いつしか私の向かう先に、小さく座り込む二人の女の子の影が見えていた。
「私、夕陽に謝りたかった」
小さな声だったけど、聞こえた。お兄さんの手のぬくもりを背中に思い出しながら、少しずつ近づいていく。澄んだ冬の空気が、彼女のすすり泣く声をしっとりと運んでくる。
「でも夕陽はきっと、私を見たら苦しくなっちゃう……」
裕子が瑞樹の背中をさすって慰めているけど、瑞樹はしゃがみこんで動かない。
「下手にメールもできないし、会いに行ったら迷惑だろうし……。ようやく会えたのに、あの様子じゃ、きっと、もう二度と……」
瑞樹は嗚咽交じりに、苦しそうに叫んだ。
「夕陽に謝りたい。他の女子に嫌われたくなくて夕陽の悪口に乗ったこと、謝りたい。私はどんな女友達よりも、夕陽を失うことが一番嫌だったはずなのに…!」
「今の、本当なの?」
気づけば私は、二人に話しかけていた。
「瑞樹は私のこと、嫌いじゃなかったの…?」
瑞樹は私を抱きしめて、何度も何度も耳元で謝った。サイコロが転がる音がした。瑞樹がこんなにか弱く泣くなんて知らなかった。こんなに素直に謝ることのできる子だったなんて知らなかった。どうして自分の見たものだけで彼女を嫌いになんてなれたんだろう。
その後しばらく、瑞樹は私と一緒に泣いてくれた。裕子も私たちを包むように抱きしめて、ずっと一緒にいてくれた。どのくらい経ったか、あまりに暗くなった周囲に驚いて笑いあった後、明日改めてゆっくり話す約束をして、一人警備員室に荷物を取りに戻った。お兄さんは、湯気すらたっていないココアを片手に、お帰り、と鞄を手渡してくれた。
「その顔は、吹っ切れた顔かな?」
「……うん。お兄さんのおかげ」
お兄さんは照れくさそうに頭を掻いて、私に笑いかけた。
「明日は、卵焼きは彼女たちにあげてね」
「……ありがとう。でも、ポットの使い方もわかってないお兄さんの分も、持ってくるよ」
「ばれてたか!」
頭を抱えて叫ぶお兄さんに手を振って、私は警備員室を飛び出した。通学路を駆け抜ける。軽い。軽い。今ならどこにだって行ける。明日だって、きっと。
「夕陽!」
「パ、パパ」
玄関の前にたどり着いた瞬間、大きな声で名前を呼ばれた。
「こんな時間まで何してたんだ」
やばい、怒られる。そう思って目を瞑る。
「早くしないと牛肉が焦げちゃうぞ」
「……は?」
「今夜はすき焼きなんだぞ」
何を言ってるんだろ、このおじさんは。
「……怒んないの」
「なんで怒るんだよ。今日も学校に行っていたんだろう」
今日も、って言った。
「……気づいてたの」
「ベランダに制服が干してあった」
ボケてると思ってた。鋭いとこあるんだ。
「夕陽の快挙を祝うために奮発したんだ。いい肉ばっかりだぞ。さ、早く手洗ってこい」
「……うるさいな、快挙とか」
私は後ろ手にドアを閉めて中に入った。薄味の汁にまみれた牛肉は決して美味しいとは言えない状態にまで煮えていたけど、優しい味がした。大きな鍋は、すぐに空になった。
「……パパ、これ」
私は台所の戸棚から取り出したお菓子たちを可愛らしい小袋に入れて、乱暴に手渡した。
「ん? 何だそれ」
「……自分で開けなよハゲ親父ッ」
「や、やっぱりハゲてるか?! 進行してるのか いや、侵攻か!」
「いいから早く開けなってば!」
青ざめながら不器用にリボンをほどいたパパは、中を見るなりパアッと瞳を輝かせた。
「夕陽! これは?!」
「一日早いけど……今あげたくなった」
「ん? 明日は何かの記念日だったか?」
呆れた。侵攻されて完全にハゲればいいのに。
「……バレンタインだよ」
「ああ! 道理で会社の女の子たちが『社交辞令めんどくさい』と叫ぶわけだ」
ああ……会社の女性方、こんなハゲにも社交辞令、お疲れ様です。
「食べてもいいのか?」
「だから渡したんじゃん」
もう付き合いきれない。テーブルに置かれた大きな鍋を両手で抱えて台所へと運んだ。ジャーッと勢いよく、空っぽの鍋を濯ぐ。その時、水道の音にも負けない大きな声が。
「美味いッ」
「うるさいな。そんなのわかってるよ」
私はスポンジにシャアッと雑に洗剤をかけて、鍋に強引にこすりつけた。ゴシゴシ、ジャージャーという音が響く中、パパは相変わらず美味い美味いとチョコクッキーを頬張っている。
「もっと奥にマカロン入ってるよ」
私の言葉に、パパはゴソゴソと大きな手を袋に突っ込んで、本当だ、と目を大きくした。
その大きな瞳が映すピンク色のマカロンは、実は失敗作第三号。
「何だ、今年はやけに気合入れてるんだな」
「うん、まあね」
失敗作一号と二号は自分で食べちゃった。四号、五号は瑞樹と裕子に、六号は南さんに。そして、たった一つの成功作、ハート形のマカロンは……。
「何せ今年は、本命チョコのために練習したものですから」
「な、何だってー?!」
「だから、パパはうるさいんだってば!」
いつの間にか水音はもう聞こえなくて、私の笑い声だけが、小さな家を満たしていた。
明日はこのボケ親父に何を作ってあげよう。薄毛用の新しいシャンプーでも買ってあげようかな。メロンパンもまた買ってこよう。おすすめのパン屋さんを、クラスメイトに聞いてみようかな。明日は何時に家を出よう。たまには一緒に出てあげるのも悪くないかな。でも明日だけは加齢臭移されたら困っちゃう。
やりたいことがいっぱいある。
でもまずは、成功作をあの人に。サイコロの転がし方を教えてくれた、あの人に。