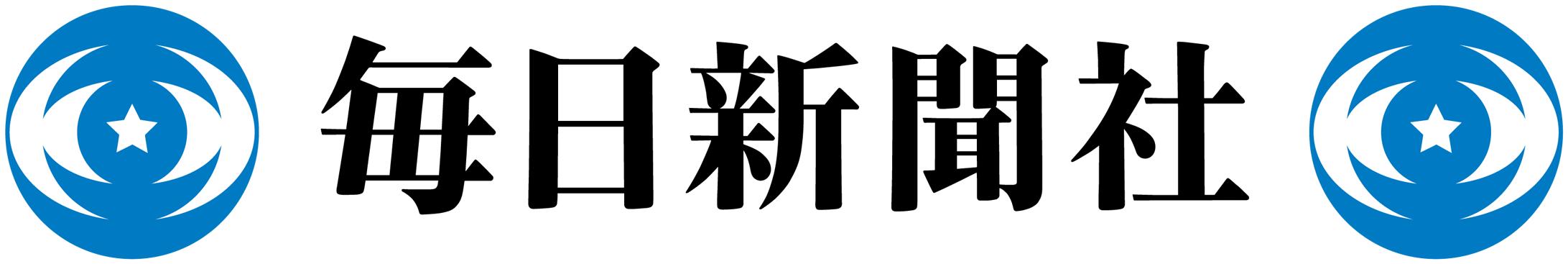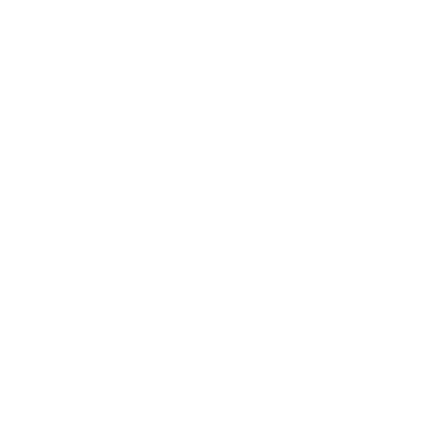第52回毎日農業記録賞《一般部門》優秀賞
我が儘のために
佐久間萌(22)=千葉県大網白里市、県立農業大学校1年

実家は3代にわたる梨農家。「将来は梨園を継ぐことになるのかな」とぼんやり考えていた。中学になり、何をしたいのかという問いに明確な答えを出せず、興味のあった心理学を大学で勉強した。梨園を継ぐという選択肢が引っかかっているような気がした。家を継がなかったことを後悔すると考えているからだ、と気づいた。農業大学校に入るにあたり、違った思いも生まれた。全てのものには終わりがある。梨園も例外ではない。慢性的な人手不足。温暖化。高騰する肥料代。小さな一農家が存続していくには問題が多すぎる。いつか終わることが分かっているなら、その終わりには自分が立ち会いたい。「自分の手で終わらせたいから」という我が儘(まま)をかなえるために、継ぐ選択肢を選んでもいいのではないか。努力の結晶を父の代で終わりにしてしまうのは非常にもったいないことだと思う。多くの知識や技術だけではなく、折れない心の強さや他人との関係をうまく管理できる社会性、計画力も身につけたい。
小さいけれど大きな田んぼ
雪森まさ子(75)=東京都江東区、ボランティア

東陽町の地下鉄の駅から徒歩10分の所に3枚の小さな田んぼがある。1986年に横十間川親水公園として整備された。体験学習の場として活用され、2002年からは区民が稲作に挑戦する「田んぼの学校」が始まった。毎年抽選で小学生のいる30家族が全10回の活動をする。無農薬・有機肥料・人力が基本。自然への関心を深め、昔ながらの米作りや農行事を体験し、食育の場にする。水を張った田んぼにみんなで入る「どろんこオリンピック」で田んぼの土をトロトロに仕上げる。スタッフは先生による研修を受け、田植えの指導者になる。早乙女コンテスト、田植えの祝い行事「さなぶり」、かかしづくり、稲刈り、脱穀……。ボランティアの活動は年間30回を超えるが、それでも続けられるのは生徒たちの成長があるからだ。手をかければ応えてくれる米や野菜。雑草の小さな草花が懸命に種を次代につなげる。成長した生徒がボランティアになる。デジタルが当たり前の時代に、リアルな体験が育てる心を大切にしたい。
家庭菜園から見えたこと
菅沼博子(82)=愛知県新城市、無職

標高500メートルの山間の村で、家庭菜園に挑戦してきた。結婚10年ほどで、荒れた田や畑が目につくようになった。きっかけは小学校の臨時教員時代に出合った2年生の作文だった。台風予報で夜の暗闇の中を家族総出でトマトの苗をハウスに避難させたという内容で、心を打たれた。自然との深いかかわりの中で自分の子育てをしたいと思った。有吉佐和子の「複合汚染」がベストセラーで、農薬まみれの野菜の恐ろしさが話題になり、「家族には無農薬の野菜を食べさせたい」という思いがあった。食糧難の記憶は残っていた。人の良い義母は好きなようにさせてくれ、いつもほめてくれた。子育てと、なんと共通点が多いことかと驚いた。早く育て、と肥料を与えすぎると枯れてしまう。ウクライナ、パレスチナ戦争の時代になり、突然、食糧自給率について真剣に考えるようになっている。土と触れ合う暮らしを続けてこなかったら、ここまで農業の危機を我が事として実感することができただろうか。
ここでしか、できないこと
冨田美和(47)=福井県坂井市、農業
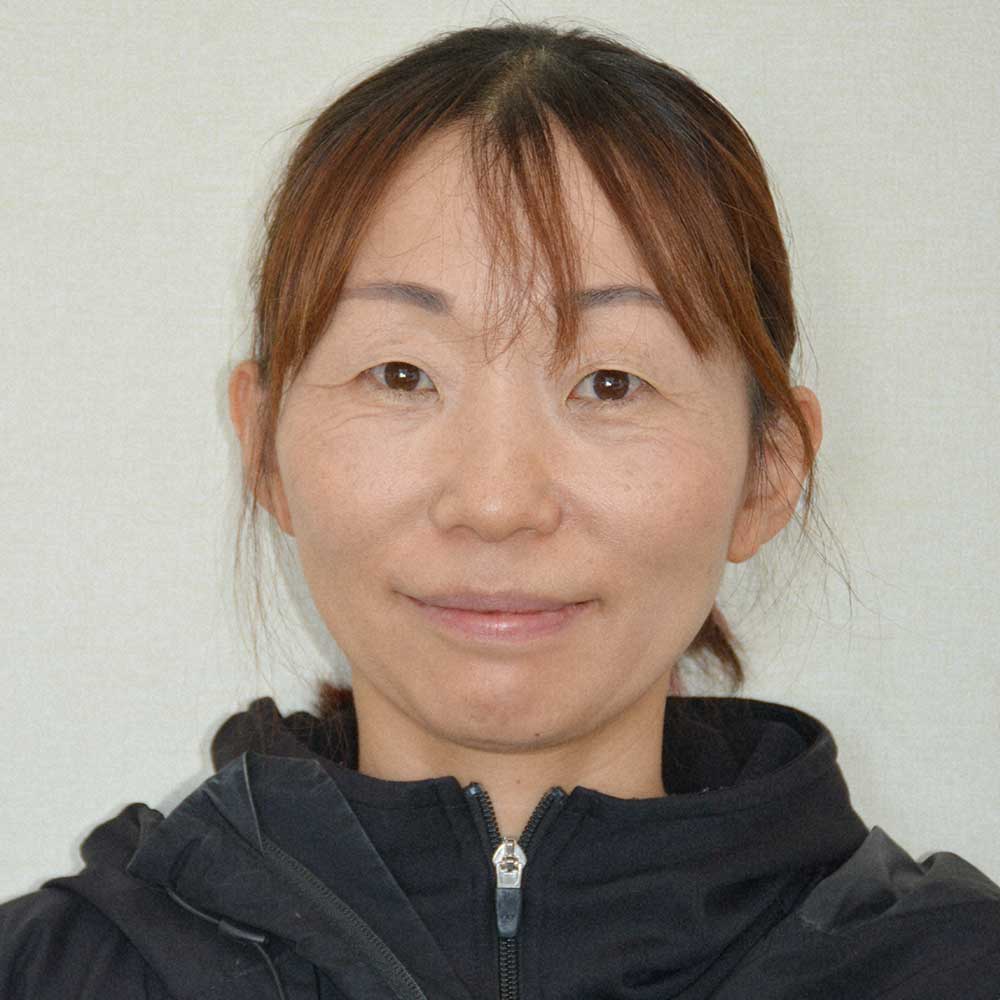
「お義母(かあ)さんが倒れた!」。義実家からの電話が人生を変えた。2014年春、家族は大阪から夫の故郷の福井へ移住した。ただ青く、大きな空とはるかに広がる水田。名古屋で生まれ、京都、大阪で暮らした自分には異世界のようだった。SNSには、都会的に暮らし仕事をこなす友達の姿があった。置いていかれる感にさいなまれる日々が続いたが、村の人たちと触れ合う中で、変化が生じた。ここでしかできない、田舎だからこそできることをやりがいにしよう、と。県の「ふくい園芸カレッジ」に入校。園芸農家として17年に独立就農した。翌年には法人化した。50アールの連棟ハウスでトマト栽培を始め、耕作が難しくなったほ場を借りながらの白ネギ露地栽培面積は8ヘクタール以上に拡大。従業員12人で、外国人や障害者も仕事をしている。農業に導いてくれたおじいちゃん、おばあちゃんたちと若者たちとの小さなバトンになれた時、「ここでしかできないこと」は完結したと胸を張って言えるのではないか。
挫折の先のご飯の味
八森光宏(26)=和歌山県かつらぎ町、農業
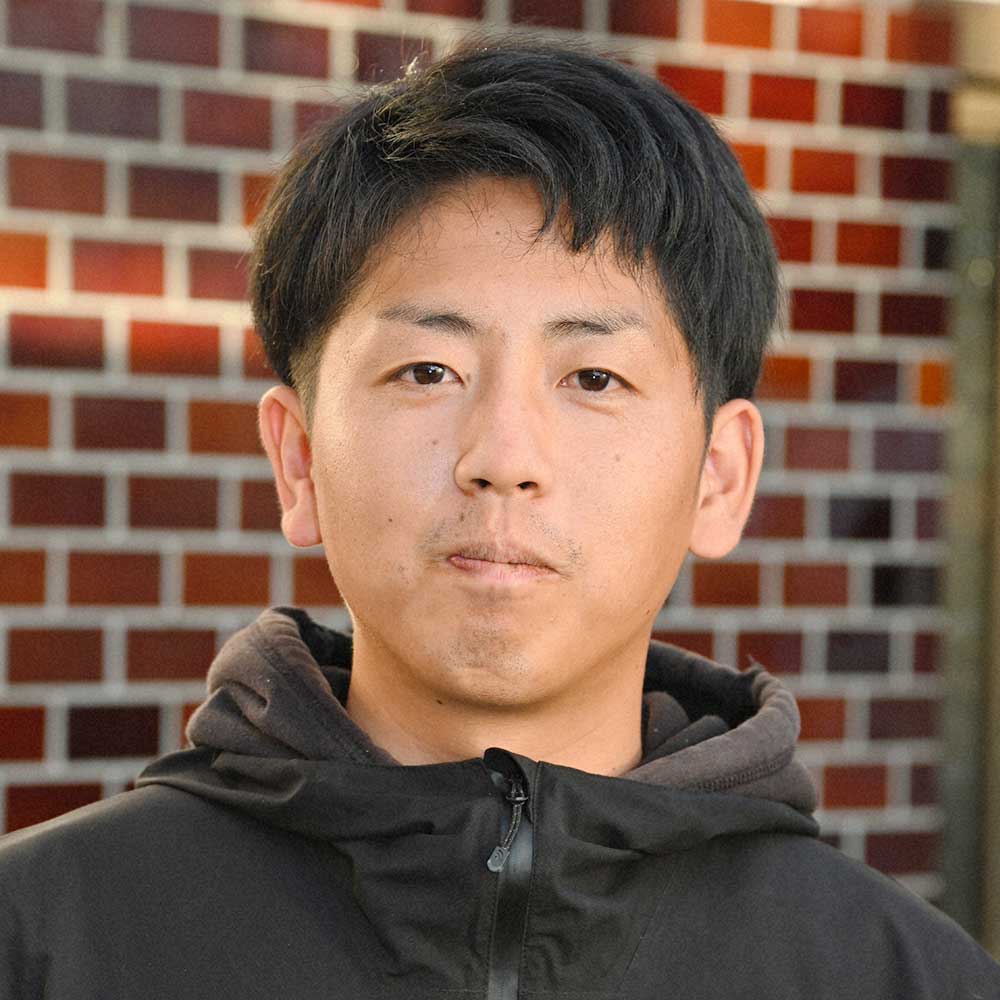
和歌山県紀の川市で育ち、3年前に移住し新規就農した。高校ではジャズに魅了された。プロ養成に合格し、海外の著名音楽家のレッスンを受けたが、才能と技術のなさを痛感し諦めた。人生で2回あったご飯の「味がしない」経験の1回目だ。父がタマネギを2反ほど栽培しており、農家になりたい気持ちが芽生えた。管理や病害虫の知識がなく困難に直面したが、営農指導員が見に来てくれた。同世代の非農家出身の農家を紹介され、JA青年部にも入った。現場の話を聞くことで視野が広がった。青年部の食育活動で小学生の笑顔に触れ、人を幸せにする力を持っているんだなと実感した。中古ハウスを買ったが、昨年の川の氾濫で倒壊。その夜もご飯の味がしなかった。営農指導員がグチャグチャになったハウスの解体方法や水につかったナスの消毒を教えてくれた。先輩も相談にのってくれて、再建の補助金がおりた。一人で農業をしていたら、立ち直れなかっただろう。地域社会や青年部活動に貢献することが自分の目標だ。
ハイブリッド思考な農業をめざして
渡部八恵(48)=愛媛県八幡浜市、農業

「富士柿」を中心に栽培している。昭和天皇の即位記念として地域農家に配られた苗が始まりで、特別大きい富士山のような形の柿が実った枝を曽祖父が見つけ、人と違うことに挑戦するのが大好きだった曽祖父が一本一本接ぎ木して増やしていった。周辺は日本唯一の「富士柿」の産地に成長。経営を継いだ祖父は流通網を広げ、父とともに農協の協力で組合を設立した。自分は教員として就職したが、結婚出産を機に実家の手伝いを決意。日本一の柿として売りたいという思いがあった。息子にもつながり、高校1年の冬、加工販売を手がける「えもんファーム」を設立。出荷がむずかしい果実をジュースにするアイデアで、すべて1人で行った。業者と連携して柿のアイスクリームも開発。収穫したダイダイのマーマレード作りにも挑戦し、大学3年になった今年のマーマレードアワードの学生部門で、ベストカテゴリー賞を受けた。伝統を守り、新しい発見にも目を向けるハイブリッドな思考の農業を家族全員で目指す。
和牛を愛して、和牛を考える
藤井琴未(21)=宮崎市、宮崎大3年

A5ランクの和牛肉に半額シールが貼られている。お客さんは安い外国産牛肉の方が好きなのか。複雑な気持ちだ。農業高1年で牛と出会った。あごをなでると気持ちよさそうに首を伸ばす姿に心を奪われた。入学後、牧場でアルバイトをし、肉の目利きを競う「ミートジャッジング競技会」の豪州大会に出場した。現地の食肉市場は、枝肉の大きさや色沢まで統一された日本の市場とは大きく異なっていた。農家に、肥育期間を延ばして肉質を向上させないのかと聞くと「肥育期間を短くすれば餌代などを削減でき、消費者に低価格で提供できる」との答えだった。日本では品質を求め過ぎるあまりに、消費者への食糧供給という本来の目的意識が薄れているのではないかと、疑問を抱いた。豪州では家畜し尿のバイオマス発電や温室効果ガス抑制のための飼料開発など、持続可能な経営のための対応が進む。牛の飼育環境が、食肉を選ぶポイントだそうだ。和牛の海外消費のためには、生産管理から改善すべき点があると感じた。
決めた!ハルサーになる‼
~南の島で有機に挑戦~
大城明子(39)=沖縄県恩納村、農業

滋賀で育った。沖縄出身の母と里帰りのたびに海にひかれた。恩納村でマリンスポーツのインストラクターになり12年働いた。温暖化で海水温が上がり、大雨で流れ込んだ大量の赤土がサンゴの白化現象に拍車をかける。陸の環境が大事だと考えた。農業を始めた転機は二つ。一つは結婚。義父は農家(ハルサー)だ。二つ目は結婚後の大病で、食の安全安心に深く興味を持った。有機栽培だ。義父にパッションフルーツとアテモヤを勧められた。ミツバチを使った環境保全活動「ハニー&コーラルプロジェクト」を知る。畑の周囲に花や赤土対策の植物を植え、養蜂の収益性で持続的な対策を目指す村の取り組みだ。ミツバチは農薬に弱い。1度だけ「もう薬を使おう」と心が折れかけたことがある。ハウス内にヨトウムシが大発生した時で別のキシモフリクチブトカメムシが現れ、ヨトウムシの幼虫を食べてくれた。何かが極端に増えれば、それを抑える力が働く。自然界のバランスに触れた気がした。楽しいからチャレンジしたいのだ。
第52回入賞者一覧に戻る