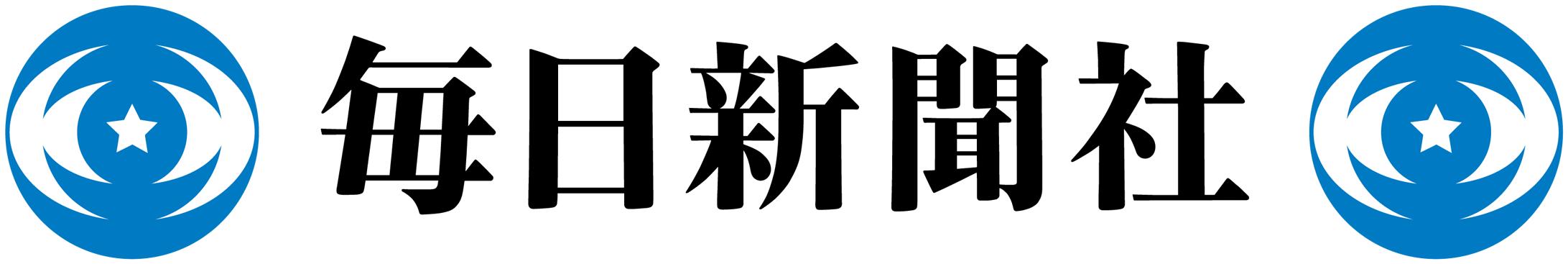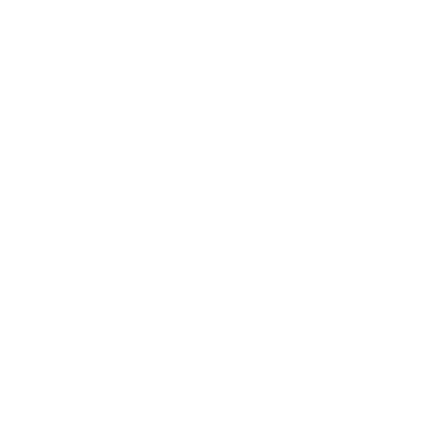第59回毎日芸術賞 受賞者決まる
第59回(2017年度)毎日芸術賞(特別協賛・信越化学工業株式会社)と第20回千田是也賞の受賞者が決まり、1月25日に東京都文京区のホテル椿山荘東京で賞を贈呈しました。
毎日芸術賞を受賞したのは、髙村薫さん(文学Ⅰ部門=小説・評論)▽有馬朗人さん(文学Ⅱ部門=詩・短歌・俳句)▽熊川哲也さん(音楽Ⅰ部門=クラシック・洋舞=特別賞)▽山路和弘さん(演劇・演芸・邦舞部門)▽遠藤利克さん(美術Ⅰ部門=絵画・彫刻・工芸・グラフィック)▽仲川恭司さん(美術Ⅲ部門=書道)――の6人。
気鋭の舞台演出家に贈る千田是也賞は、野村萬斎さんが受賞しました。

贈呈式での受賞者のあいさつを紹介します。
文学Ⅰ部門(小説・評論)
小説「土の記」 高村薫さん(64)

◇身体感覚が原動力
物書きになり27年、時代や社会はものすごいスピードで変化し、それと共に小説の姿も変わっていくことを考えますと、随分と遠くまで来たというのが今の実感です。
阪神大震災直後に連載した「レディ・ジョーカー」を最後に、エンターテインメント小説から純文学に転向しました。けれど小説に対する向き合い方は同じです。同時代を生きる身体感覚をよりどころにしています。「レディ・ジョーカー」は戦後の繁栄が揺らぎ始めたという一生活者の切実な実感と、一流といわれた日本経済に対する素朴な疑問が書かせた小説でした。
「土の記」でも同じです。東日本大震災を経験した一日本人の心身に深く刻まれた傷と、それでも命が絶えることのない地球の営みへの感慨と、還暦を超えた私の身体の日々の実感、この三つがこの小説を書かせたのです。
同時代を自分の足で歩いて、自分の手で物をつかんで、それを原動力とすることで私の小説は他の誰でもない私の小説になっているのだと自負しています。明日からまたこの身体で生き、身体で書くという作家人生を続けさせていただきたいと思っています。
文学Ⅱ部門(詩・短歌・俳句)
句集「黙示」 有馬朗人さん(87)

◇素晴らしいごほうび
この度は第59回毎日芸術賞をいただき、まことにありがとうございます。このような賞をいただけるとは思いもよらず、選考委員の中でも詩人の松浦寿輝先生には、私のくわしいご紹介をはじめ、心よりお礼申し上げます。
詩人の方に句集「黙示」を認めていただいたのはびっくり仰天でした(笑い)。これまでの人生を振り返ってみても、詩人からは怒られることはあっても、ほめられたことはほとんどなかったように思います。
「黙示」の編集では(主宰する)俳句雑誌「天為」の仲間たちが大いに手伝ってくれました。毎日の俳句作りでも、仲間が一生懸命やってくれていることに力をもらっています。この場を借りてお礼申し上げたい。
私は漢字をよく間違える男でして(笑い)。句の季節の順序を直してもらい、「角川 俳句」編集部の方々にも大変お世話になりました。もう一つ、尊敬する鷹羽狩行さん(俳人協会名誉会長)をはじめ、俳壇の方々が後ろから推薦してくださいました。そうでなければ、こんな素晴らしいごほうびをいただくことはあり得ないと思っています。
音楽Ⅰ部門(クラシック・洋舞=特別賞)
バレエ「クレオパトラ」の制作・演出に至る長年の功績 熊川哲也さん(45)

◇バレエに恋して35年
全2幕の「クレオパトラ」を仕上げた時、何か賞を頂けるのでは、という予感めいたものがありました。それが現実になり、本当にうれしく思っています。
1982年。10歳の僕はクラシックバレエと出会い、初めての恋に落ちました。それから35年。身も心もいちずにバレエにささげ、人生でいちばん長い恋が続いています。女性との恋愛は長続きしないのですが。
そして昨年、クレオパトラに出会いました。素晴らしい女性ですが扱いが難しく、気も荒く……。苦労もありましたが、音楽、美術、衣装や照明など一流のスタッフが僕を支え、万全の環境を作ってくれたおかげで、何とか彼女も気持ちよく、舞台に立ってくれたようです。
多くの先人の努力で隆盛してきたクラシックバレエ。その伝統を継承しながら、劇場という場をもり立て、後に続く世代にも一流の芸術として誇りに思ってもらえる、そんなバレエ界でありたいと思います。そして僕は40年後、有馬(朗人)先生のようにチャーミングなあいさつができるよう、これからも頑張ってまいります。ありがとうございました。
演劇・演芸・邦舞部門
「江戸怪奇譚~ムカサリ」「喝采」での演技 山路和弘さん(63)

◇身に余る賞、不安に
40年ちょっと役者稼業を細々とやってまいりました。身に余る賞をいただき大変喜んでいます。最初は喜んでいたのですが、歴代の演劇部門の受賞者の方々を見ましたら顔が青ざめました。雲の上の方ばかりなので、私のようなチンピラ役者がもらっていいのか、だんだん不安になってきました。
25年近く前、2013年度にこの賞を受賞なさった、亡くなった平幹二朗さんと初めて「樅ノ木は残った」という芝居でご一緒しました。あの立派な体躯(たいく)、あの立派な声、あのメリハリといい、こういう方が一流の役者さんなんだなと思いました。こういう人とやっていくには、どうしたらいいんだろう。職人と言われるような役者になっていくしかないなと思いました。だったらなんでもやってみようと、時代劇からミュージカルから、落語まがいから、声優の仕事とかいろいろやらせていただきました。
還暦も過ぎてふと思うと、中途半端なままできたんですけど、今回賞をいただいて、こういうチンピラ役者も、もうちょっとやってていいかなと思いました。
美術Ⅰ部門(絵画・彫刻・工芸・グラフィック)
個展「遠藤利克展―聖性の考古学」 遠藤利克さん(67)

◇侵犯的に境界越えて
去年の暮れにアトリエが火災で焼失しまして作品をつくる場所がなくなってしまいました。絵画や彫刻はフィクショナル(虚構的)なものと考えていますが、制作場所がなくなるとその考えが非常にリアルに感じられます。
表現をフィクショナルに考えるきっかけは制作の初期に(心理学者の)フロイトやユングに影響されたのが大きいと思います。自分流に解釈すると脳の底の方に無限の世界が広がって複雑なイメージの構築物がある。それは内的現実でもあり、フィクショナルなものでもある。
ある時、美術評論家の故赤塚行雄さんから不思議な話を聞きました。立てた柱や床の間は聖なる場所なんだ、と。衝撃を受けて世界が違って見えるようになった。その後、さらに掘り下げて日常世界の向こう側には反転した世界や見えない境界があり、境界を侵犯的に越えることで聖なる領域やアートの本質につながっていけるのではないかと解釈するようになりました。
自分は危険な侵犯者との意識が強く、一時は賞の話があってもお断りしていましたが、それも一面的な見方だと考えるようになりまして、今回はありがたく頂きました。
美術Ⅲ部門(書道)
仲川恭司書作展 仲川恭司さん(72)

◇この道をまっしぐら
実は私の師匠が50年前に毎日芸術賞をいただいております。当時は書道という分野はなく、美術の分野での受賞でした。私たちにとっての誇りで、酒を酌み交わして喜び合った。今回、偶然私に賞が舞い降りた。今は書道という分野があるわけですから、この道をまっしぐらに進んでいかなければならないと思います。
受賞対象は昨年の個展です。少字数に挑みました。私の出身は佐渡で、書といえば、漢詩を書いたものばかり。どう読むのか、どんな意味があるのか分からないままに書いているものもあったように思います。もっと字数が少なくて海外でも評価されるような作品が書けないか、と思いました。大学に進学すると、美学を担当した彫刻家がいらした。毎回「作品を持ってきたのか」と言われる。3カ月くらい過ぎ「書はむずかしいね。私は周りを回って作品を造る。だけど書は片面から書いていって裏面までみせなければいけない」と話された。芸術というものの不思議さに魅惑されていったわけです。
個展に向かっていき、私の中で燃えるものがたくさん湧き出した。こんな世界を求めてきたのだと自分自身感動しました。
千田是也賞
「子午線の祀り」の演出 野村萬斎さん(51)

◇めぐり合えた幸せ
千田是也賞を20回の締めくくりに頂戴することを本当にありがたく存じます。世田谷パブリックシアター20周年公演として取り上げた作品ですので、芸術監督を務めている私としても節目にいただけ、木下順二先生の作品にめぐり合えたことに幸せを感じます。
「子午線の祀(まつ)り」の第1次公演は1979年度の毎日芸術賞を頂戴しています。私が小学生ぐらいから、あたかも古典芸能に接するかのごとく拝見していた作品を、再構築、再創造していくことは、狂言をやっている古典芸能の人間としては当然ですが、それも芸術のひとつのあり方と考えます。
自分は天頂に支えられ、そこに座標軸がある、という意識で始まる戯曲であることを今回の演出のポイントにもしましたが、まるで今のGPS(全地球測位システム)機能のようで、木下先生が言っていらっしゃったことに時代が追いついたのかなという気がします。
長年培った戯曲と演出があったからこそできた舞台ですが、そこに新しい息吹を吹き込んでくれたスタッフ、キャストにもお礼を申し上げたいと思います。