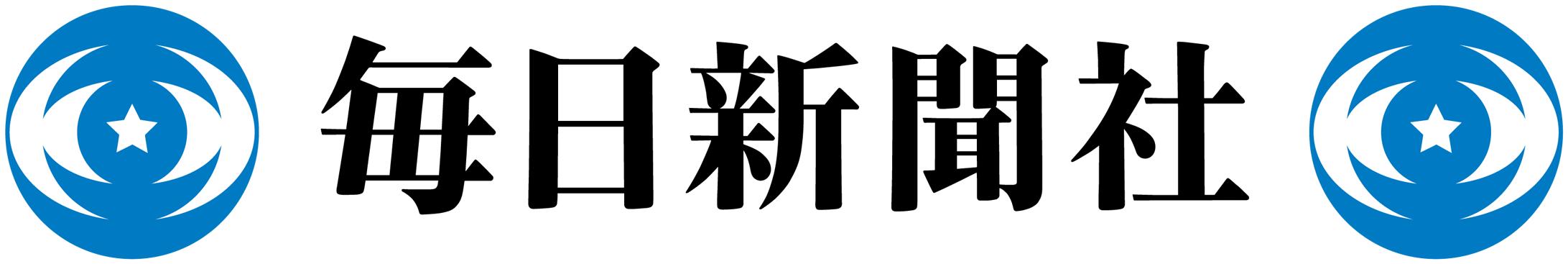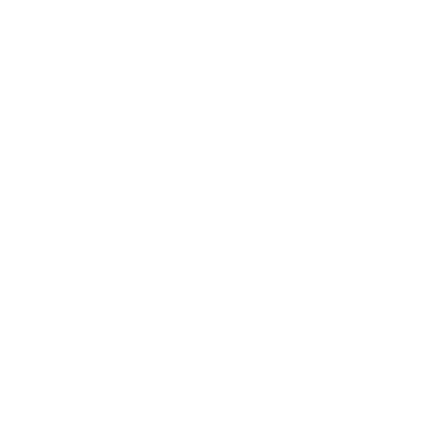第40回毎日農業記録賞《一般部門》最優秀賞・新規就農大賞
りんごと共に、私の生き方
高野寛子(32)=岩手県奥州市
農業との出会い

毎朝の通学は、最寄りのJR川崎駅から乗車する、上り京浜東北線の満員電車の中だった。神奈川県の川崎市で生まれた私は、両親と妹、どこにでもあるような、一般的な都会の核家族で育った。地元の中学を卒業後、何とか母の希望であった、都心の大学付属高校に入学した。当時は女子高校生が一大ブームを巻き起こしていたかのような時代。茶髪にルーズソックス、ポケベルにプリクラ。
それこそ、コギャルに援助交際という言葉も生まれた時だった。授業が終われば、制服のスカートを短くし、ルーズソックスに履き替え、ラルフローレンのベストに着替えて、友達と渋谷や新宿に遊びに行った。これが、私の日常であり、いわゆる青春時代だった。
高校2年にもなると、周囲の友達はより良い外部大学を目指すために、予備校に通い始めた。そして私も、真剣に将来のことを考えるようになった。しかし、考えれば考えるほど、やりたいことが見つからなかった。そんな私の不安やストレスは母へ矛先がいき、この頃から口さえ聞かなくなった。少しでも良い大学に行き、少しでも良い会社に勤めることが両親の希望であり、そしてそれが、私への重圧でもあった。
父の出身は東京だが、母の出身は岩手県の県北にある大野村(現・洋野町)だった。周囲は山々に囲まれ、酪農や農業が主だった地域産業。村には信号機が一つしかなく、商店は昔からある顔なじみの店ばかり。昔ながらの茅葺き屋根の家も村内には点々とあった。幼い頃、遊びに行っては、タイムスリップしたような感覚さえあり、堆肥の臭いがする村が私は大好きだった。
祖父母の家は、母の兄である伯父夫婦と4人で暮らしていた。農業で生計を立てており、りんごや山ブドウ、野菜や山菜、花卉などによる複合経営だった。
伯父夫婦は子供には恵まれなかったものの、いつも楽しそうに会話しながら、農作業をしていた。そして、伯父はよく「村への想い」を私に話してくれた。「小さな村だからこそ、一人一人の意見や想いで村が変わることができる」そんな信念を持って、村づくりへの想いを語っている伯父は、いつもキラキラ輝いていた。

高校の夏休みを利用して一人で訪れていた際、たまたま農作業を手伝うことになった。初めての農作業は、間伐するりんごの木の根っこをスコップで掘り起こす作業だった。夏の30度近い気温の中、一人でひたすら土を堀り続ける作業が続いた。想像以上の重労働だった。「10時のおやつだよ」と言う伯父の声に、汗びっしょりになっていた自分に気付き、軍手を絞ると汗が出てきた。そんな体験は初めてだった。
作業をしていると、太陽を見て時間が分かったり、小学校の音楽で習った「かっこう」の鳴き声も初めて聞いた。人として当たり前のことを知らない自分に気づかされた。仕事が終わると、伯父の軽トラの助手席に乗り、山を下りていく。少し高台になっている道路から、ちょうど夕焼けで村全体が赤くなっている景色は何よりも美しく、仕事を終えた自分への御褒美のようだった。
大学受験の準備を始めながらも、長期の休みがある度に、私は大野村に行き、農作業を手伝った。冬は雪の降る中、堆肥にするための藁を一週間切り続け、春には剪定したりんごの枝を一輪車で集めた。決して楽ではなかった。しかし、いつからか農業を自分の職業にしたいと思うようになり、伯父のような「生き方」をしたいと強く思うようになった。
ずっと口を聞かなかった娘が、突然、農業をしたいと言ったので、もちろん母は大反対し、父も現実逃避だと私に言った。高校の先生や近所の人からも好奇な目で見られ、「今の子だから、農業の大変さを知らないだけなのよね」と言われたこともあった。しかし、私は初めて「自分で決めた道」だったので、何度も両親を説得した。農業についてもいろいろと調べ歩き、都道府県に一つずつ農業大学校というものがあることを知った。そして、岩手の農業大学校で農業の知識を学んでから、伯父のもとで農業を始める夢を思い描いた。
「岩手のりんご、寛子が有名にしてね」とクラスメート全員から色紙にメッセージをもらい、父からは「寛子が作ったりんごが出来たら、真っ先に我が家に送ってほしい」という手紙を胸に抱いて、一人、家を離れ、岩手に行くことになった。
りんご作りへの強い想い

4月だというのに岩手では雪が残り、まだまだ寒い日が続いていた。果樹専攻は全部で8名。女子は私1人だった。都会から来た非農家の私を「よく来た、よく来た」と、特に歓迎してくれたのが、私のりんごの恩師でもある藤根研一先生だった。
先生は私にとても面白くりんごを教えてくれた。「お前には、りんごの声が聞こえていない」と現場の大切さを徹底して教えてくれた。初めて見たりんごの花、そして日に日に大きくなっていくりんごが本当に愛おしく、りんご作りへの想いはさらに強くなった。
早くりんごの声が聞こえるようになりたいと、私も必死で学んだ。りんごは永年作物のため、確かな技術が必要とされる。1年間、全ての管理、小さな技術の差一つで、りんごの味が変わってしまう。美味しいりんごを作る篤農家は、まさに技術者であり、職人のようだった。「口先で語るな、りんごで語れ」と恩師は私を技術者として育てようとしてくれた。
さまざまな人にも恵まれ、研修や勉強の場もいろいろ歩いた。県内のみならず、青森や秋田、宮城。そして、富山の農産法人や沖縄の花卉農家にも研修に行った。毎日が充実していた。卒業を控えた冬休み、りんごの剪定研修先で今の主人との出会いもあった。卒業後は、大野村で、伯父のもと農業に従事し、そしてその後、主人のもとへ嫁に行くことになった。
嫁として
嫁ぎ先の義父は江刺りんごのブランドを築きあげた有名な人だった。当時、「ふじ生誕60周年の品評会」で最高賞に輝き、実質日本一のりんご農家という名誉を授かった。その後も数々の賞に輝き、のちに黄綬褒章も受けることとなった。陰で支えていた義母の苦労は数知れず。でも、いつも何も言わず支え続けていた。
そんな偉大な両親を前にいつも私達夫婦は自信を無くしていた。りんごの個人専業農家としては大きい10ヘクタールの面積に、多くの雇用。長年の多くのお客さんとの信頼関係も構築されていた。嫁の私に何ができるのだろう。いつもそんな不安とプレッシャーの中で、子育てと仕事と何とか両立させながら、ただただ、目の前に置かれた状況をやりこなすことで精一杯だった。

3人目の子どもが1歳を過ぎ、保育園に預け始めたその頃、以前から興味のあった岩手大学のアグリフロンティアスクールの募集を普及センターから教えていただいた。月に2回程、農業経営を中心としたビジネス感覚を習得し、「アグリプロ」を育成するというスクーリングだった。月に2回とはいえ、私が仕事を休むことは、家族にも大きな負担がかかるため悩んでいた。でも、何かきっかけを見つけたいという気持ちが強く、主人や家族の理解のもと、通えることとなった。
人生の第二の転機は、大学に通い始めたことと言っても過言ではない。世代も20代前半から60代後半まで。さまざまな立場にいながらも、農業で新たな道を開拓したいという熱意ある人ばかりだった。忘れかけていた自分の原点を思い出し、忘れかけていた信念を再び思い起こした。「りんごへの強い想い」は誰にも負けないはず。きちんと現状と向き合って、一歩前に進もう。そんな強い気持ちが再び、私の背中を押してくれた。
経営者の嫁ではなく、私自身も経営者として。その後、家族経営協定を主人と結び、認定農業者の共同申請も行った。りんごの品評会にも私自身で選び、私の名前で出品した。義父を講師としたりんごの剪定研修会も企画し、60名の人が集まった。
地域の小学校の総合学習のりんご作業も自ら担当した。食育を通して、地元の江刺りんごの素晴らしさ、りんご作りの楽しさを伝えていけば、いつの日か必ず新たな後継者が生まれるはず。私にしかできないこと、私に与えられた役割を少しずつ行動に移した。そんな私の新たな行動は、胆江地方青年農業奨励賞という名誉 も頂き、大きな自信へと繋がっていった。
江刺りんご、そして岩手のりんご産業の発展へ

気がつけば、今年で嫁に来て10年目になった。自分自身を振り返り、180度違った生活から「りんご」と出会い、主人と出会い、3人の子どもたちにも恵まれた。そして今、江刺りんごというブランド産地の生産者として歩んでいる。
江刺りんごがブランドとして確立した月日は浅い。それこそ、義父が仲間と共に強い情熱と努力によってブランド産地を形成した。その多くの先人方は70歳を過ぎ、第一線から退くようになった。
本当の意味でのブランド力というものは、これからを担う若い私たちにかかっている。確かな技術は必ず継承されなければならないし、そして新たな戦略を取り込まなければ産地の発展には繋がらない。一人一人がプロとしての信念を持ち、産地強化ということを強く意識しなくてはならない。
しかし、今の農業政策では六次産業化や販路開拓など、個人経営力を強くすることが求められており、実際、その方向しか生き残れない現状がある。でも、このような時代だからこそ、地域や産地間での連携が必要で、農協や県全体の協力体制が何よりも攻めの農業になると思う。
そして今、義父が長年の月日をかけて育種してきた新しいりんごが出てきた。品種特性の課題は多いものの、岩手県オリジナル品種という最大の強みがある。栽培技術を確立して、江刺りんご、そして岩手のりんご産業の発展に貢献できる品種に成長してほしいと、現場で新たな課題に向き合い、挑戦する日々が続いている。
嫁として、私は本来の望まれている姿とは少し違うのかもしれない。主人や家族には改めて、感謝の気持ちでいっぱいである。主人は私に「日本一のりんご屋さんにはなれないかもしれないけど、日本一幸せなりんご屋さんになろう。」とプロポーズしてくれた。新たな経営方向に主人と共に乗り越え、技術者としても経営者としても一人前になって、今後も、日本一幸せなりんご屋さんになれるよう歩み続けたい。
たかの・ひろこ
約10ヘクタールの農園でサンふじ、シナノゴールドなどの栽培に力を注ぐ。2男1女の母。