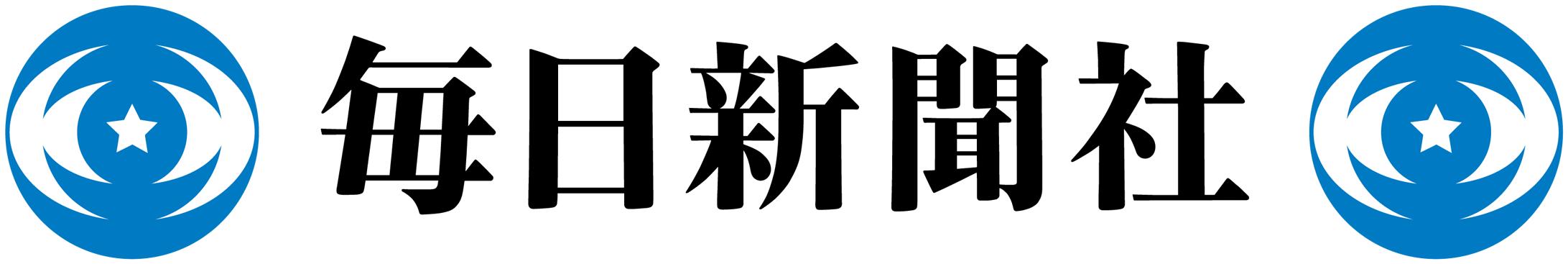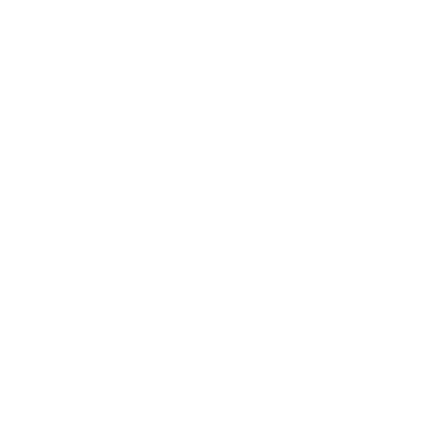第52回毎日農業記録賞《一般部門》最優秀賞・中央新委員長賞
食は命、守り続けたい農業
本山由加里(43)=岡山県鏡野町、農業

食糧危機に備えて、農学部に行きます!
高校生の時、私は絶望していた。勉強が難しすぎて、こんな苦しい日がいつまで続くんだろうと泣きたい気分だった。そんな私を救ってくれたのが、読書だった。勉強から逃げるために没頭した読書だったが、一冊の衝撃的な出合いがあった。「食糧危機」。一九七〇年代頃に書かれた古い本だ。当時は飽食の時代。食糧危機と言われても、ピンとはこない。でももしそうなったら怖いな、食べ物って大切だよな。この本との出合いが私の農学部進学の決め手となった。
大学時代は楽しかった。勉強もサークルもおもしろい。バイトも忙しく、毎日が充実していた。つらい高校時代を耐え抜いて、本当に良かったと思った。念願だった彼氏もできた。「日本の国を守る、条件は二つ。外から来る敵から国を守る防衛と、中から国を守るために食べ物を作る農業。この二つは最重要だ」。そう話す、彼の志は高かった。
日本の中心から農業を変えていく!
そうこうしているうちに、就職活動の時期がやってきた。食べ物や農業にかかわる仕事がしたい。でも当時は就職氷河期、ほとんどの会社に断られた。先に東京で農業関係の公務員に合格した彼と一緒に居たい気持ちと、花の東京へ行きたい気持ちの両方で、なんとか私も東京の農業関係の会社に就職した。「日本の中心から農業を変えていく!」という熱いいで一緒に上京した。
東京は刺激的で、楽しかった。会社からは新しいことをたくさん教えてもらった。
そして、結婚。新婚とはいえ、旦那様の帰宅は深夜。数時間だけ家で寝て、また満員電車で出勤。休日も出勤。ひどい職場だった。東京で働く公務員ってこんなに休めないんだと、驚いた。ふつうの生活を送れない、こんな働き方ってどうなの?と旦那様の職場に疑問を持ち始めていた。
北欧を満喫した新婚旅行から帰ってきた日、住んでいる宿舎に黄色と黒色の規制線が貼られていた。同じ宿舎の方が自ら命を絶ったそうだ。こんな身近なところで……。「東京から日本の農業を変えることはできない」。これが私たち夫婦の結論だった。
「土の無いところで、人は育たない」
それが、東京でわかったこと。第一子の妊娠が決定的だった。公務員をすっぱりと辞めて、地元の岡山へ帰った。
旦那様の実家、岡山県鏡野町でイチから農業をはじめることにした。大学時代に「農業はもうからない」と何度も聞いていたが、本当だった。東京で働いてためたお金はあっという間に底をついた。それでも真面目に米作りを続けているうちに、本当にたくさんの方から「うちの田んぼも作ってくれんか」とお声がけいただくようになった。平成二十年に一・三㌶ではじめた農業が、令和六年には三五㌶を作るまでに広がり、従業員三人、アルバイト数名、代表が私で、営業が主人の米専業の大規模農業経営の会社となった。
ドローンを導入したとはいえ、田んぼの中をトラクターやコンバインで走り回る、ほぼ従来型の農業を行っている。中山間地域のため、一つ一つの田んぼが小さく、は広く、田んぼの形もまちまちで、結局は人の手で植えて、育てて、管理して、刈っている。ぜんぜんスマートじゃない。でも、良いこともいっぱいある。
職業が農業だから、できること
まず、子だくさんになれる!
うちは子どもを六人も授かった。小さい子どもたちが家の中を走り回って、障子はボロボロ、ふすまは貫通させた穴をくぐり抜けて逃げ回り、かくれんぼしてキャーと叫ぶ。すると、二階で勉強している長女から「静かにして!」とLINEが届く(笑)。洗濯は大きいドラム式で一日に四回以上。
大変な生活だけど、職業が農業だったら、仕事をしながら子育てができる。職場の田んぼに子どもをつれていけるし、倉庫での作業も、お米の発送準備もできる。事務や経理は家でできる。急に子どもが病気になっても、すぐにお迎えにいけるし、学校の行事で仕事を休んでも大丈夫。
それから、食べ物に困らない!
野菜とお米は自家産。我が家の裏の畑では、自家用に多種の農作物を育てている。毎日が大忙しなので、家の裏へ出るだけで夕飯の食材が手に入ることは、買い物に行く手間が省けてとても助かる。農薬を使わず育てるので、健康面でも安心だ。
「買った方が安くない?」と友達から聞かれることがよくある。でも、お金じゃあないんです!って心の中では思ってる。いつも頭をよぎるのは、「食糧危機」の本。家族を守れるように、食べ物だけは作れるようにしておきたい。食べ物を作る土地と技術は、絶対に手放してはいけないと思う。今年の秋からは、毎年一本ずつ柿の木を植えるつもりだ。食べ物が不作の年でも、柿だけでも食べられるようにという田舎の政策だったように聞いたから。
周囲の人に食糧を提供し続ける、それが使命
令和の現在、戦争や気候変動で、農業の環境は激変している。
まずは物価高。食べ物がどんどん値上がりしている。気候変動も進んでいて、農作物を今までどおり育てることが難しい状況だ。どんなにお金を払っても、食べ物が手に入りづらくなる時は、もう目の前まで来ている。さらに、熊の相次ぐ出没。山の中で生態系が崩れて、熊の食べ物が無くなってしまい、人の暮らす場へ食べ物を探しに来ている。この熊の様子は、近い将来の人間の姿だと私は思っている。食べ物が手に入らず、都市から農村へ食べ物を探しさまよい歩く人間の姿に見えてならない。
米作りをしていると、たくさんの地元の人から、管理ができないから田んぼを買ってほしいと依頼がある。うちも管理や税金の支払いが大変だが、無理をしてでも買うようにしている。なぜなら、作物を作る田んぼや畑が無かったら、どうやって食べ物を作るの?と将来に不安を感じるからだ。身の回りの人にだけでも、食糧を提供し続けること、それが私たちの使命だと感じている。
わが家から農業を 変えていこう!
農繁期には従業員にもかなりの負担を強いているので、従業員が少しでも楽をできるよう、防除だけでなく、今後は田植えもドローンで代替して省力化を進めたい。キーワードとなるスマート農業には、機械の導入が必要で、その資金繰りに頭を悩ませるところだが。
草刈りは社内では手が回らず、作業委託していて多くの費用がかかる。知り合いは、田んぼの法面にも米を植えて、草刈りをしないチャレンジを始めた。うまくいけばまねしてみたい。
今年、農産物検査員の資格を取得できた。これからは米の検査も自社でできるので、お米の情報が行き交う場所にしたい。近隣の農業経営体と横のつながりも強化して、岡山県北ブランドのような価値も付加できたらいいな。
スマート農業と高付加価値化をわが家から始めて、県北の農業経営体へと広げていけば、より多くの人を食糧危機から守っていけるはず。
高校時代に出合った本、「食糧危機」。これから私が進むべき方向は、目前に迫る食糧危機へいかに対応するか、会社のかじ取りをしていくことだろう。
今回、この賞に応募することで、初心に帰ることができた。このことに感謝している。また、受験生の長男にも読ませたい。母も頑張るから、長男くんも頑張ってほしい!
第52回入賞者一覧に戻る