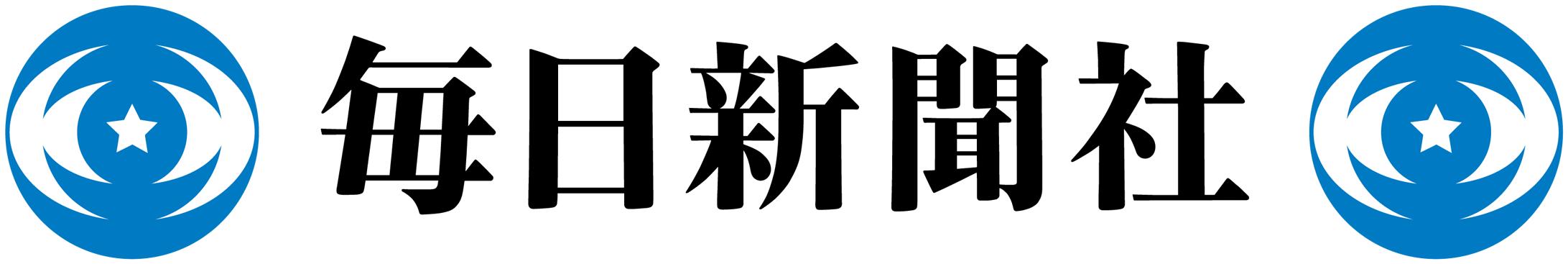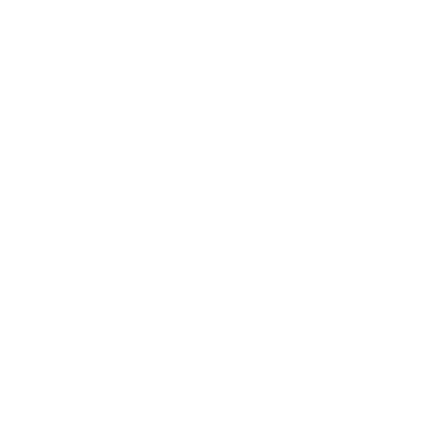第52回毎日農業記録賞《高校生部門》優秀賞
「もも1年」栗3年柿8年
青森県立柏木農業高2年 鎌田紗羅
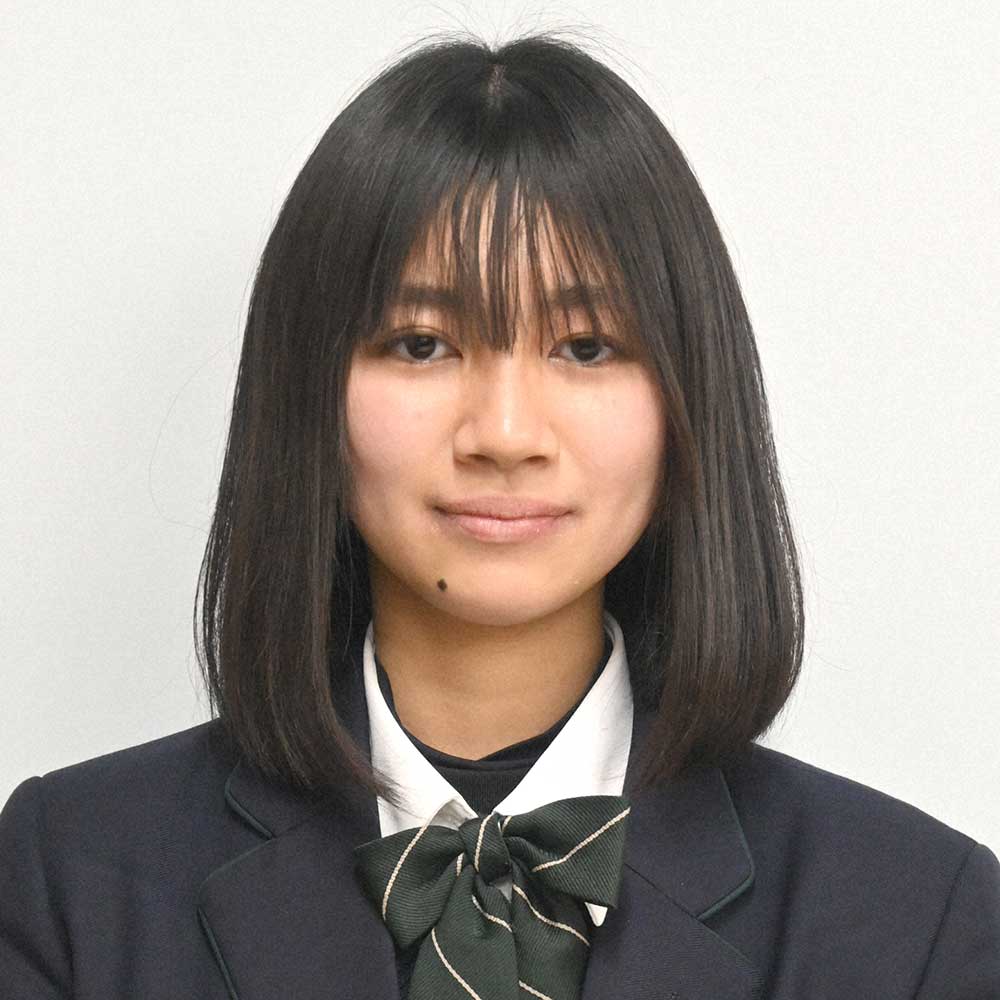
祖父が作る桃が大好きで、ある日、桃のドーナツ作りに挑戦した。失敗して泣いたが、皆は「おいしい!」。加工品を食べてもらう喜びを知り、食品科学科に入学。「りんご研究部」にも入り、県外販売や保育園児への食育、「高校生ボランティア・アワード」の全国大会に出場した。昨年の猛暑で柏農りんごが窮地に立った。日焼けや落果で作付けをやめる農家が続出する中、桃が代替になるのではと思い当たった。暑さに強く、夏から秋までの「品種リレー」による継続販売も可能だ。りんご農家13人を中心に栽培を開始。寒暖差や栽培方法の類似点が産地化にぴったりだった。定植当年から収穫可能な新潟県の「ももの大苗移植シンプル栽培」を知り、開発者から話を聞いた。栽培技術の「標準化」で簡単に栽培できる。学校が先頭に立って実践し、生産量向上や「津軽の桃」ブランド強化を目指して活性化に貢献したい。6次産業の農業経営者になり、自分の桃で世界中の人に喜んでもらうのが夢だ。
環境保全を礎に世界へ挑む仙台牛の挑戦
宮城県農業高3年 星碧虎(あおと)

祖父母は和牛の繁殖と稲作の専業農家。牛舎は幼い頃から遊び場だった。「仙台牛を日本一に」の夢を抱いて入学したが、牛が出すメタンガスには二酸化炭素の25倍以上の温室効果があり、牛が気候犯罪者と呼ばれていることを知った。メタンガスの削減方法を探す中で北里大学の研究者を知り、ルミナップという餌の存在を聞く。メタンガスを抑えると少ない餌でも効率的に吸収して牛は大きくなり、餌代の削減につながることも学んだ。実際に給餌し、最大30%のメタンガスの削減を確認した。日本の消費者ニーズは肉質の方を向いているが、視察に行った豪州では環境に対するニーズが高いことを知った。ならばと、これまでメタンガスに関心がなかった農家に提案、取り組みを継続している。脱プラスチック肥料による稲作と、それでできたワラを使って和牛を飼育し、「和牛甲子園」に出品した。環境保全と肉質の両方が認められた。持続可能な農業で、地域再生と夢の実現につなぐ。
秋田県再建の一歩は「循環型農業だ‼」
秋田県立大曲農業高2年 関口宗浩

地域の未利用資源を研究した。目をつけたのは生産量全国4位の菌床シイタケだ。秋田県横手市では年間360万個の菌床を産業廃棄物として処分し、5000万円の費用がかかっている。おがくずが主原料の廃菌床は再利用可能な有機物だが、発酵に時間がかかり栄養成分のバランスも悪く、あまり活用されていない。そんな中、市内の会社が、廃菌床をカブトムシの幼虫飼育の餌「Kマット」にし、ヘラクレスオオカブトの飼育や販売をしていることを知る。幼虫のフンを加えたKマットを調べると、成分バランスがよく、軽くて臭いもほぼないことが分かった。ヘラクレスオオカブトの幼虫をKマットで飼育し、一緒にレタスを栽培する食農教材を作った。循環で奇跡を起こすという意味の「くるくるミラクルキット」と命名。保育園などに配り説明の紙芝居も制作。農業科学館などで多くの人に見てもらい、循環型農業に興味を持つ人が増えた。農業教員になって課題解決に貢献する生徒を育てたい。
無人販売から始まった、地域密着型農業
山形県立村山産業高2年 沓澤魁良(かいら)

水田に太陽が照り返す中、祖父が動かす田植え機がかっこよく、自分も挑戦した。褒められたことがうれしくて、家の10㌃を借りて農業をスタートした。ナスやピーマンが中心。中学生活はコロナ禍の休校で始まったが、友達らと中学生農業グループを結成。作付けを維持し、品目を増やした。「消費者は農産物を盗まない」「生産者は安全なものを生産している」。この「信用と信頼」に裏打ちされた無人販売所ならば、通学しながら販売もできると確信。売れ行きは絶好調で、意見箱には「楽しみにしている」という声が寄せられ、生産物が消費者に届く手応えを感じた。ただ、中学卒業で仲間はバラバラになり、自分だけでは農地を管理しきれなかったが、転機が来た。高校で農薬散布のドローン講習会があり、これに参加して免許を取得。近所の農家から農薬散布の依頼が殺到し、高齢化が進む地域への貢献を実感した。今も10㌃でキャベツを栽培する。「地域に愛される農家」になりたい。
乳牛のオスの運命
神奈川県立中央農業高3年 柳沢桃音

ゲロロが生まれた日を鮮明に覚えている。母牛は初産のため、分娩(ぶんべん)介助をした。子牛が出てくると「あー、オスか……」とがっかりした声が聞こえた。ブラウン・スイス種のような飼育数が少ない乳牛のオスは、小柄で肉量が少なく、飼育もしづらいため需要がない。数年の飼料価格高騰で行き場がなくなり、安楽死が増えたと聞く。ゲロロを育てるため先生に何度も提案し、「低コストで和牛に負けない高品質の肉を作る」をテーマに、酪農専門研究部で肥育試験ができることになった。飼料コスト削減のため、米屋から米ぬかを無料で、酒蔵からは酒かすを安価で譲ってもらった。希少乳牛の現実を知ってもらうため、親子酪農体験教室でゲロロとふれあってもらった。性格は温厚で今ではお辞儀もできる。順調に成長し、他の牛に比べて増体の結果が最もよかった。希少種乳牛のオスが経済的にも価値があると証明したい。順調にいくと来秋には出荷だ。飼育管理を頑張り、オスたちの命を人へとつなぐ方法を模索していく。
南信州から紡ぐ、竹取再生物語
野県下伊那農業高3年 鈴木怜(さと)

多くの観光客が美しい景観を求めて、天竜川の鵞流峡を訪れる。近年はうっそうとした竹やぶが目立つ。日用品や建築資材などの需要減少によって、竹林が放置されている。他の樹木の成長を妨げて森林崩壊や土砂崩れにつながる危険がある。整備を持続させるには竹の利活用と循環する仕組み作りが大切だ。文化祭は「和」をテーマにし、学校を竹で装飾した。使用後の竹は燃料にし、灰は畑の肥料にした。明治大学の建築・アーバンデザイン研究室と連携し、竹を使った「チキントラクター」を開発した。ニワトリを動力にしたトラクターで、移動式の鶏舎にニワトリを入れて畑に放つと、フンなどを落として「肥料散布」をしてくれる。餌のミミズを求めて「耕運・除草作業」もしてくれる。ブランド地鶏「信州黄金シャモ」を使ったオリジナルラーメンも開発。竹林整備から生まれた竹を使った地元・伊那谷産メンマ「いなちく」を活用した。「竹害」は「竹財」に変わる。活動は地域に広がり始めた。
ワサビと共に生きる~梅ケ島を救うワサビジネス~
静岡県立静岡農業高3年 秋山賢介

南アルプスのふもと・梅ケ島(静岡市)で江戸時代から続くワサビ農家。6代目を継ぐのが夢だ。両親と小さい頃からワサビ田の世話をしてきたが、梅ケ島の人口は300人を下回り、耕作放棄地も増えた。ワサビは害獣被害が多く、対策に費用がかかる。父の代で近隣の放棄地を整備して栽培面積を広げた。専業でやっていきたい。農業簿記を学び、近隣のワサビ農家でインターンシップをした。ワサビは栽培環境が限られており、栽培方法も特殊だ。地域で協力し合うことが必要だ。共同経営をして農業法人を設立することが夢だ。人材育成がしやすくなる。ノウハウを共有して栽培マニュアルを作成し、技術を後世に伝えていく。観光農園も開設したい。現在の耕作放棄地は500㌃を超す。会社設立から10年後までに栽培面積500㌃、年産量10㌧、売り上げ1億円が目標だ。「辛くて苦いから嫌い」と言われるワサビだが、一人でも多くの人に本物を食べてもらうことが意識改革の第一歩だ。
農家with気候変動~長良ブドウで描く私の夢~
岐阜県立岐阜農林高2年 山田美乃
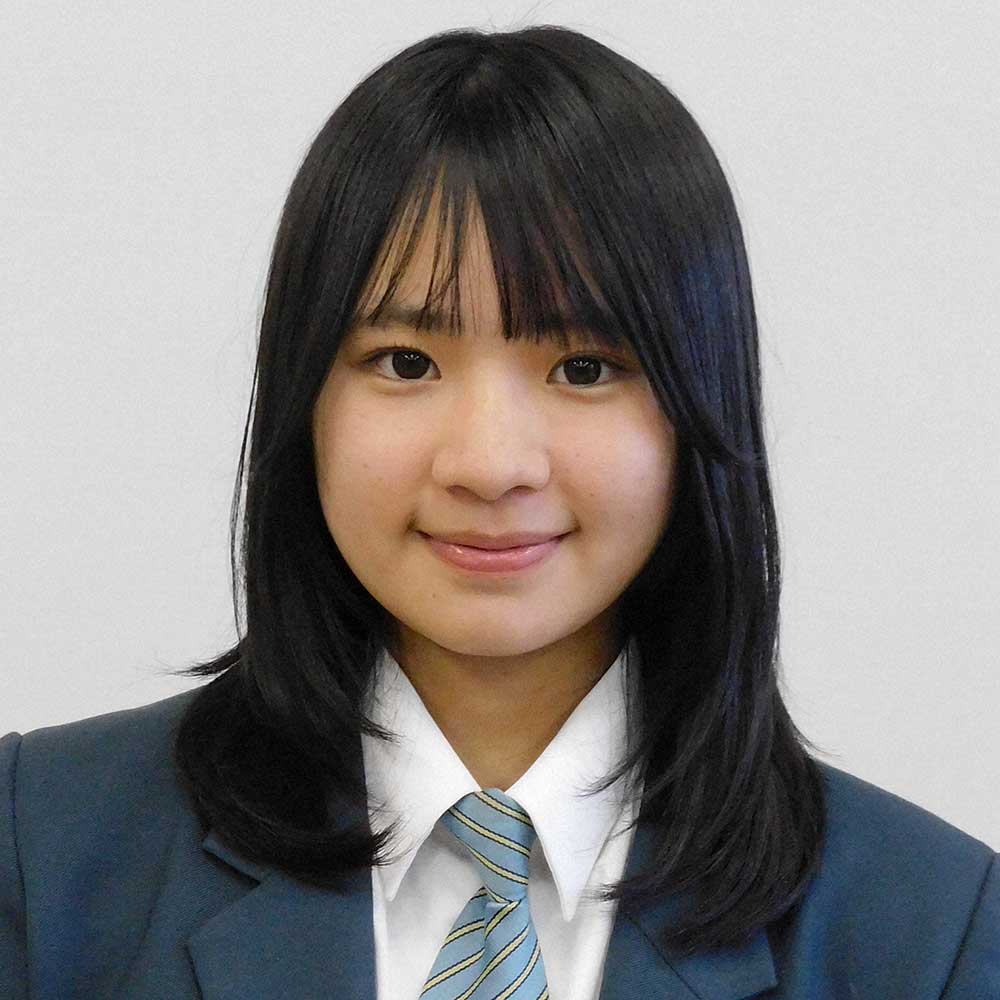
岐阜城を望む長良川の河畔に、ブドウ畑が広がる。糖度の高いブドウは「長良ブドウ」として愛されている。ブドウ農家の次女だ。ここ数年、売り上げの5割を占めるデラウェアが不調だ。授業で気候変動が理由だと分かった。長良ブドウの栽培が始まった年から約100年間に約4度も気温が上昇していた。環境省の目標は2030年度に温室効果ガス13年度比46%削減だが、農家は今すぐ行動しなければと、強く感じた。そんな時、食品加工で「糖蔵」を学んだ。食品を砂糖漬けにして長期保存する技術だ。試しに廃棄ブドウを使ってコンポートを作った。ブドウの食感がしっかりと残り、同じ分量の場合、ジャムよりもブドウの消費量が少ないため原価を安く抑えられる。火加減の調整を重ねて見た目も味もよいものができ、お客さんに喜んでもらえた。年間約80万円の利益が出る試算だ。6次産業化による長良ブドウ存続の道筋が見えた。法人化を目指し、地域の人を雇用して地域全体の活性化につなげたい。
卵が先か、ひよこが先か。~一人前の養鶏家を目指して~
滋賀県立八日市南高3年 西村恵音(けいと)

家は琵琶湖に面する滋賀県近江八幡市で養鶏を営む。家業を継ごうと考えていたが、その気持ちがはっきりした。ある養鶏場に実習に行ったことがきっかけだ。ウインドレス鶏舎で飼養管理され、開放型鶏舎の我が家とは対照的だった。「君の考える経営規模で利益を出せるようにならないと。それが家を継ぐということや」と言われた。勉強のため、別の養鶏場に実習に行った。鶏舎作業は自動化され、働き方も効率化されていた。ひよこから育てている養鶏農家は、県内ではこの養鶏場と我が家だけだ。一般的な農家では、卵を産む少し手前の鶏を導入する。ひよこには手間やリスクがあるからだが、父は「良い卵を作るということは、良い鶏を作るということや」と言う。ひよこの時期に走り回ってしっかり餌を食べれば、良い鶏になる。何万羽クラスの鶏を扱う大手にはまねができない。父は養鶏家としても経営者としても立派だ。「家を継ぐ」という意味が理解できた。
第52回入賞者一覧に戻る