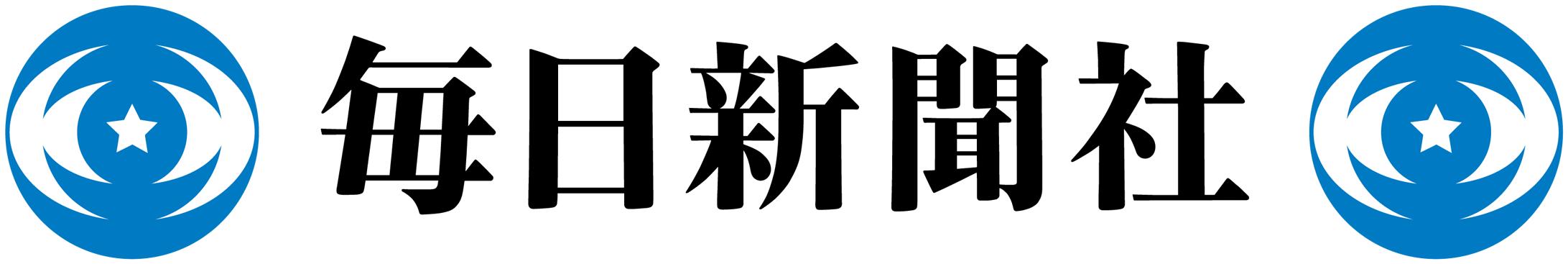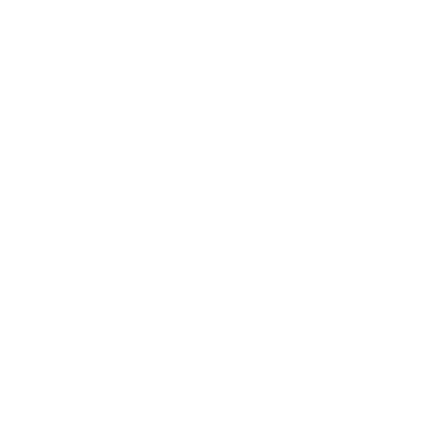第52回毎日農業記録賞《一般部門》最優秀賞
「美味しい」の言葉に支えられて
川瀬保子(59)=北海道津別町、農業

非農家育ち。1986年に畑80ヘクタール、ホルスタイン肥育牛400頭の大家族農家に嫁いだ。「仕事が趣味」の義父を中心に家族は皆、働き者。北海道ではまだされていなかった黒毛和種の肥育に取り組み、東京食肉市場への出荷を開始。90年に夫が事業を継承し、近隣農家と「流氷牛」のブランド化を進めている。子供4人を授かり「四刀流」の仕事と家業に追われたが、子が巣立った後は喪失感に襲われた。そんな時、牛肉の加工場を作ってみたい、との夫の言葉をチャンスに、東京農業大の創成塾に応募。受講を経て牛肉商品の直売所を開業した。夫が育てた牛肉のフランクフルトを町の小麦のパンで挟むホットドッグが評判で、週末カフェもオープン。千葉県船橋市の子供たちをステイに迎え、酪農学園大の学生実習も受け入れた。2009年、津別町グリーンツーリズム運営協議会の発足に合わせて簡易宿泊業の営業許可を取り、大阪の専門学校生や高校生らの受け入れも始めた。手作り弁当を「美味(おい)しい」と言ってくれることが大きな喜びだ。
いちご農家にしかできないことをやりたい
~6次産業化による多角化経営でいちごの魅力を発信~
篠原和香子(59)=栃木県小山市、農業

50年ほど前から続くいちご専業農家。2013年に法人化した。息子が3代目。53アールで「とちおとめ」など2品種を栽培している。6次産業化のきっかけになったのは、規格外を生かしたい、完熟いちごのおいしさを伝えたい、という2点だ。自分の夢とパティシエ資格を取った娘の夢をかなえるため、17年に洋菓子店をオープンした。補助金申請は採択されず自己資金でまかなう苦しいスタートだったが、開店と同時に店は満席。自分のビジョンとお客が求める価値が同じであることを確信した。他店とは違う夏場の商品開発に挑戦。1000万円のイタリア製マシンを購入し、県産生乳を使ったジェラート製造に成功した。完熟いちごを直接販売する新たな専門店を田んぼの中に出店した。20人を雇用し、個々の能力を引き出す職場を作っている。10年前、6次産業化実践セミナーの受講生の一人だった自分が、今は研修を行う立場になった。「やるか、やらないか」で人生は変わる。
夫と歩んだ半世紀
小野民子(75)=静岡県沼津市、農業

今年、金婚式を迎えた。103歳の認知症の義父を世話している。結婚前は都市銀行や大阪万博の情報通信課に勤務した。夫は自動車販売会社の検査員で「一緒に旅しよう」の一言で結婚。義父母は2.5ヘクタールの田畑で茶やみかん、米、野菜を作っていた。長男が3歳の年に夫は会社を辞め、農業を始めた。買い求めた土地の借金があった。整地作業にあけくれ、自分もダンプを運転し、機械操作をするようになった。借金とのいたちごっこの中、実母が亡くなった。弱音は吐くまいと頑張った自分に、義姉から「しゅうとめは民ちゃんをずっと心配していたよ」と聞かされた。その思いをつづり、教育雑誌の作文コンクールで入賞。表彰式で5人の農婦と出会い、堂々と物を言えるプロになろうと決めた。献上茶の指定茶園に選ばれ、農地は5倍に増え町内一の農家になった。夢の製茶工場も実現した。のんびり余生を、と思っていたが、夫は前より大きい作業場を建てた。多くの仕事が、自分を強くたくましく育ててくれた。
野菜の新たな価値創造
鈴木彩(46)=神戸市、農業

2030年に仏ルーブル美術館で野菜のアートを展示するのが夢だ。夫が「農業を始めようと思う」と言った。「私は手伝わない」が条件だった。11年に夫と夫の両親で始めたが、義母の病気で、義務感から手伝うことにした。就農2年目の夏、ゲリラ豪雨で2000株のトマトが全滅したのをきっかけに少量多品目栽培に切り替えた。世界の野菜の種を取り寄せ、年間365品種を栽培。農薬、化学肥料は使わない。野菜をあえて小さく作ろうと発想を転換。1ヘクタールから就農当初の30㌃に戻し、丁寧に向き合っている。花屋に勤めていた夫の経験をいかした「野菜ブーケ」を開発。女性農業次世代リーダー育成塾で学び、東アジア最大の食品展示会「FOODEXJAPAN」に出展した。「こんな野菜の使い方は自分の国でも見たことがない」という言葉を海外の人からもらった。コロナ禍後、神戸市北区の古民家と農地に移住、念願の個展「野菜博物館ZERO」を同市で開催。ほ場の一角に「野菜植物園OZO」をオープンさせた。
梨でつながる次世代農業を目指して
前田有美(50)=佐賀県伊万里市、農業

介護士から梨農家へ。夫婦で23年続けてきた。義父の病気を機に結婚4年後に就農した。土地から購入したハウスなどさまざまな借金があり、経営は経費が6割。梨は定植後、5年間の未収益期間が長い。複式簿記の講習を必死で受け、借り換えや小口負債の一本化に取り組み、自分のライフプラン設計に合わせた目標を設定した。安心材料が増え、不安が払拭(ふっしょく)され経営が分かりやすくなった。栽培の技術取得も必死。「百姓で作った借金は百姓でしか返せん」という言葉を胸に刻んだ。夫婦それぞれで作業日誌を書く。目標に向かう仲間のような感覚だ。当初の梨園は傾斜地で苦労が多く、収穫1週間前に10頭以上のイノシシが押し寄せ、1個も収穫できず泣いたこともあった。仲間との「もやい作業」で、人との出会いやつながりができた。「ふるさと先生」として子供たちに食と農の大切さを伝える活動をしている。県農業士として、農業の素晴らしさを伝えることがこれからの楽しみだ。
第52回入賞者一覧に戻る