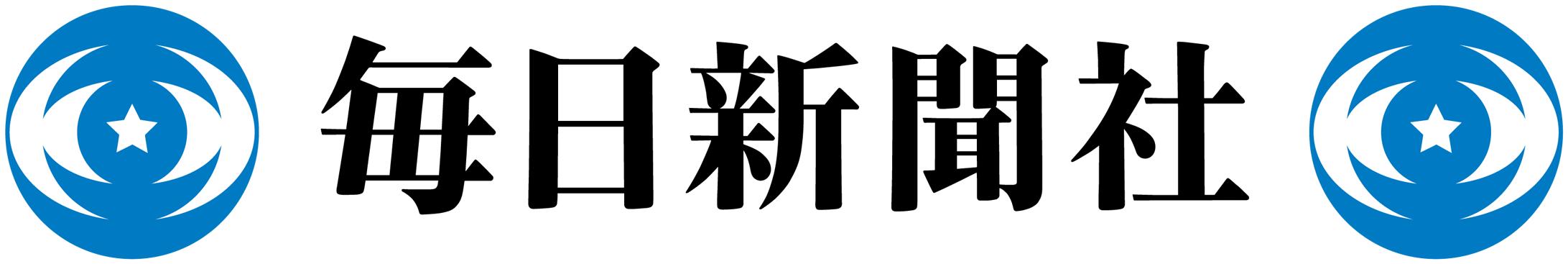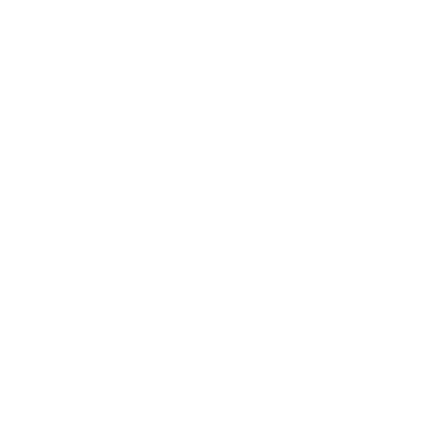クボタ・毎日地球未来賞
「第15回クボタ・毎日地球未来賞」受賞12団体決まる
毎日地球未来賞(大賞)は「学校法人アジア学院」と「宮城県農業高等学校 桜プロジェクトチーム」
21世紀の地球が直面する「食料」「水」「環境」の問題解決に取り組む団体・個人を顕彰する「第15回クボタ・毎日地球未来賞」の受賞者が決まりました。
受賞記念活動報告会を2月14日(土)午後2時から、毎日新聞大阪本社オーバルホールで開催、その模様をYouTubeで配信します。
総合司会は、吉本興業所属の芸人「浅越ゴエ」さんです。
受賞者によるプレゼンテーションやトークセッションを是非ご覧下さい。
報告会開催日時:2月14日(土)14時~16時半(予定)
視聴URL:https://youtube.com/live/Esh_i9X7f8Y


受賞者一覧
毎日地球未来賞(大賞)
一般の部
学校法人アジア学院(栃木県那須塩原市)
約50年にわたり、開発途上国から学生などを受け入れて農村指導者を養成。寮生活を送りながら農村で活動するための指導論、持続可能な農業技術、共同体形成などについて学び、帰国後は農村地域の課題解決に貢献する人材を輩出してきた。
キャンパス内外の田畑で無農薬による循環型有機複合農業を実践し、90%を超える学内食料自給率を維持。地域の食料残渣を家畜飼料として活用したり、地域の持続的な循環型フードシステム構築のモデルケースを学生たちに示したり、ジェンダーエクイティ(男女公正)と平和構築にも取り組むなど、多岐にわたるSDGsカテゴリーに挑んでいる。
学生の部
宮城県農業高等学校 桜プロジェクトチーム(宮城県名取市)
東日本大震災の津波により全壊した校内に残った1本の桜の木の保護をきっかけに活動を始め、桜の植樹や育成活動を通じて地域振興に貢献してきた。
高温障害を被る桜に「酢酸」を使用することで、高温・乾燥・塩害の三つの環境耐性効果を同時に引き出すことができることを突き止めた新資材を「桜色活力剤」と名付けて、これを使用した植樹、地域振興が評判を呼んでいる。
クボタ賞
一般の部
オクオカ竹資源活用協議会(愛知県岡崎市)
地元事業者や地域住民が中心となって協議会を設立し、放置竹林の増加でやっかいものとなっている竹を有効活用することで、放置竹林解消、環境・景観改善、まちづくり活動の活性化、地域経済の循環を目指す「オクオカ竹プロジェクト」を推進している。
荒廃した竹林を整備しながら、竹炭を餌に添加して育てたブランド豚、タケノコの加工食品、土壌改良材等の新商品を開発し、竹の新たな価値を生み出すことで、国土保全や地域経済に貢献している。
取組みを行う住民等に地域内店舗のみで使用可能な地域通貨券を発行し、地域の竹林整備を促進する体制も構築している。
学生の部
千葉県立安房拓心高等学校 安房拓心サトウキビ組合(南房総市)
南房総は温暖な気候に恵まれるが、少子高齢化や過疎化により農業従事者が減少し耕作放棄地が増加している。そうした中、温暖な気候に適したサトウキビの栽培方法を研究し、肥料の種類や量、植え付け時期を工夫して、沖縄の約3倍という高い収量、高品質(高糖度)を実現。地域企業や行政、学校などと連携を図り、サトウキビを新たな特産品にするプロジェクトを進める。
サトウキビを絞った後の残りかす(バガス)を牛の飼料や畑の肥料として活用し、廃棄物を減らす循環型農業も実践する。
小学校への出前授業、農家実習を通じて農業の重要性を伝え、地域の担い手育成にも注力している。
SDGs未来賞(学生の部のみ)
京都府立宮津天橋高等学校フィールド探究部(京都府宮津市)
宮津市を南北に貫く大手川は2004年の台風被害後の改修で川の流れが弱くなり下流に砂が堆積するなど構造や環境が変化、改修前に生息していたフナやナマズが見られなくなった。改修時に作られたが管理されず草木が生い茂っていた子供たちの遊び場であるはずの公園を再生し、土木事務所や地元企業の協力を得てワンドを造成、ハーブ工を設置するなど生き物の住処づくりに取り組んだ。
「みんなの川塾」を開催し、様々なワークショップや体験活動を通じて川の大切さを認識する機会を生み出し、地域活性化、世代を超えた交流に繋がっている。
徳島県立小松島西高等学校 TOKUSHIMA雪花菜工房(徳島県小松島市)
海水温の上昇によって食害魚が増加、藻場が失われて小魚の隠れ家は消失し、漁獲量が減少している。そうした中、ブダイカレーなど食害魚を活用した商品開発に取り組み、販売収益の一部を藻場再生に寄付して「買って食べることが環境活動につながる」モデルを構築している。
特産しいたけの廃菌床にウニ殻、鉄分、酒粕を混合して藻場に必要な栄養を補給する肥料を開発。麻袋に詰めて海へ投下し、廃棄物削減と資源循環を同時に推進している。
補助金に頼らない持続可能な藻場再生活動を目指し、ブルーカーボンクレジットの申請にも挑戦中。
大分県立久住高原農業高等学校 おいしい“たけた”研究会(大分県竹田市)
サフラン・紫草・チョロギ・岡大豆・温泉といった竹田市の地域資源を、単なる保全ではなく「地域循環ブランド」として再生させることを目的とした取り組み。サフランを活かした化粧水や美容液を旗艦商品とし、地域資源を組み合わせた商品群を開発。OEMメーカーと連携して製造、大学・研究機関と共同研究を行い、安全性・機能性も科学的に裏付ける。
クラウドファンディングやビジネスプランコンテストへの挑戦を通じて、資金調達や販路拡大を実践。「おいしいたけた研究会」(法人化予定)を母体に、生産者・市民・企業・行政が協働する仕組みを構築している。
奨励賞(学生の部のみ)
北海道更別農業高等学校 地域資源活用分会(北海道河西郡更別村)
更別村では1年間に4千トンもの林地残材が発生。その未利用木材と規格外さつまいもを活用し「バルサミコ酢風」の調味料を開発した。ぶどうの代わりにさつまいもを、熟成のための木の樽の代わりに林地残材を利用。
短い熟成期間で高品質な酢を製造し、特許出願やパテントコンテストで優秀賞を受賞するなど評価を得ている。
今後は製品化、販売による未利用資源のさらなる活用が期待される。
北海道真狩高等学校 有機農業コース RO分会(北海道虻田郡真狩村)
リジェネラティブ農業(環境再生型農業)を実践。不耕起とカバークロップ、輪作を組み合わせることにより、土壌機能の向上や、自然環境の回復が見込め、化学肥料・農薬を使用しない「リジェネラティブ・オーガニック」に挑戦している。大学や企業と連携し、栽培試験を実施、リジェネラティブ農業に適した作物の栽培時期の調査や土壌変容と炭素貯留量の調査などでデータを蓄積し、農家への普及を目指している。
群馬県立藤岡北高等学校 環境工学部(群馬県藤岡市)
絶滅危惧種ヤリタナゴの保護活動に取り組む。校内にビオトープを造り、生息魚類の観察やヤリタナゴについての説明を園児や小中学生に行うなど、環境教育の拠点となっている。
河川のモニタリング調査から市内の6河川の特徴を魚類から把握し、ヤリタナゴの生息にはどの河川が相応しいか定量的に突き止めたり、外来種の駆除も同時に実施しアメリカザリガニの繁殖特性を調査、効果的な駆除方法を発見した。
地域振興のために、「ヤリタナゴの里」を創出し、無農薬・無肥料でフナ農法を取り入れたタナゴ米を栽培、販売。生物多様性、生態系豊かな地域づくりを地域住民らとともに構築しようとしている。
広島県立世羅高等学校 農業経営科(広島県世羅郡世羅町)
平和大通り沿いの商店街活性化委員会から都市養蜂の実験依頼を受け、駐車場で囲いをしたスペースでミツバチの飼育を開始。翌年はビルの屋上に巣箱を設置し、通常巣箱1つから採れる蜂蜜の年間平均量は9~27㎏と推定されているが、女王蜂を隔離する短期採蜜法により50㎏の採取に成功した。蜂蜜から得られる収入の一部を街路樹保全に寄付している。
養蜂を学ぶ海外研修事業の日本代表としてモンゴルや韓国の研修に参加し、知見を拡大するなど活躍の場を広げている。
熊本県立北稜高等学校 造園科(熊本県玉名市)
樹木管理の授業で排出される剪定くず。それらの焼却による温室効果ガスの発生を危惧し、廃棄物を有効活用することで持続可能な造園を目指している。
造園業者から排出された剪定くずをチップ化し、おがくずの代替として利用しヒラタケやエノキの栽培に成功。栽培後の栽培地も米ぬかを混ぜて腐葉土として再利用、販売している。キノコも腐葉土も原材料コストはほぼ0円。地域イベントや施設で販売し、好評を得ている。
入選
第15回から、さらなる活動の発展と継続を願い、最終選考に残りながら惜しくも入賞には至らなかった団体・学校を「入選」とし顕彰します。
一般
いちかい里山くらぶ(栃木県芳賀郡市貝町)
認定特定非営利活動法人びわ湖トラスト(滋賀県大津市)
特定非営利活動法人eワーク愛媛(愛媛県新居浜市)
一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会(福岡県北九州市)
特定非営利活動法人ツシマヤマネコを守る会(長崎県対馬市)
学生
澤﨑わかな(岩手県盛岡市)
栃木県立矢板高等学校 農業経営科農業技術部(矢板市)
麗澤中学・高等学校 SDGs研究会「EARTH」(千葉県柏市)
京都府立桂高等学校 TAFS第2研究群 芝研究班(京都市西京区)
奈良県立磯城野高等学校Seeds(卒業生)&Flowers(在校生)(磯城郡)
鳥取県立倉吉農業高等学校 生物科 野菜クラブ(倉吉市)
盈進中学高等学校 環境科学研究部(広島県福山市)
香川県立石田高等学校 ISDGs班(さぬき市)
愛媛県立川之石高等学校(八幡市)
長崎県立対馬高等学校 ユネスコスクール部(対馬市)
沖縄県立中部農林高等学校 園芸科学科(うるま市)
| 主催 | 毎日新聞社 |
|---|---|
| 後援 | 文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省 |
| 協賛 | 株式会社クボタ |